 アレルギーに関する解説
アレルギーに関する解説 腸内環境改善の専門家
 アレルギーに関する解説
アレルギーに関する解説
腸内環境改善の重要性
近年、腸内環境の乱れが様々な病気の原因になることがわかってきています。腸内環境が悪化すると、腸内細菌のバランスが崩れ、悪玉菌が増えて善玉菌が減ってしまいます。これにより、消化吸収機能が低下したり、有害物質が体内に取り込まれたりして、健康被害を引き起こすのです。
腸内環境を改善するためには、食生活の改善が大切です。食物繊維や乳酸菌などの善玉菌を増やす食品を積極的に摂り、悪玉菌を増やす食品を控えることで、腸内環境を改善することができます。また、適度な運動やストレスを溜めないことも、腸内環境を改善するのに役立ちます。
腸内環境を改善することで、アレルギー様食中毒のリスクを下げることができます。アレルギー様食中毒は、魚介類などに含まれるヒスタミンを多量に摂取することで起こる食中毒です。ヒスタミンは、腸内細菌によって生成される物質で、腸内環境が悪化すると、ヒスタミンを生成する細菌が増えてしまいます。これにより、ヒスタミンが体内に取り込まれてアレルギー様症状を引き起こすのです。
腸内環境を改善することで、アレルギー様食中毒のリスクを下げることができます。腸内環境を改善するためには、食生活の改善、適度な運動、ストレスを溜めないことが大切です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康 ~連鎖球菌の役割とは~
腸内環境改善と健康『連鎖球菌(直径 1µm程度のグラム陽性の球菌で、形状は、個々の菌体が規則に直鎖状に並んだ配列をしている。 通性嫌気性または偏性嫌気性で、生化学的には、カタラーゼ陰性。一般に乳酸発酵によってエネルギーを得る。栄養要求性が厳しい(特異的)のも特徴のひとつである。)』
連鎖球菌とは?
連鎖球菌とは、 диамет 1µm程度のグラム陽性の球菌であり、形状は、個々の菌体が規則に直鎖状に並んだ配列をしている。通性嫌気性または偏性嫌気性で、生化学的には、カタラーゼ陰性である。一般に乳酸発酵によってエネルギーを得る。
栄養要求性が厳しく(特異的)のも特徴のひとつである。連鎖球菌は、人間や動物の口や腸内に常在する細菌であり、通常は病気を引き起こさない。しかし、特定の条件下では、連鎖球菌は、溶血性連鎖球菌感染症、蜂窩織炎、肺炎、猩紅熱などの病気を引き起こすことがある。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『グラム陽性とグラム陰性』
グラム陽性菌とグラム陰性菌の違い
グラム陽性菌とグラム陰性菌は、グラム染色による細菌の分類方法に基づく2つの主要なグループです。グラム陽性菌は、グラム染色法によって紫色に染まる細菌で、細胞壁に厚いペプチドグリカン層を持ちます。一方、グラム陰性菌は、グラム染色法によって赤またはピンク色に染まる細菌で、細胞壁にペプチドグリカン層と外膜を持っています。グラム陽性菌の例には、乳酸菌、ビフィズス菌、ブドウ球菌、連鎖球菌などが挙げられます。グラム陰性菌の例には、大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌、肺炎桿菌などが挙げられます。グラム陽性菌とグラム陰性菌は、細胞壁の構造や染色性の違いに加えて、代謝経路、抗生物質への感受性、病原性など、様々な点で異なります。
Read More
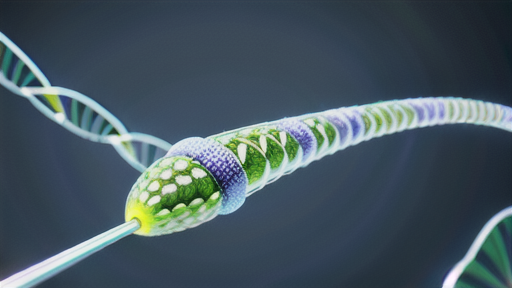 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康~ピロリ菌を制す~
ピロリ菌は、ヒトの胃内に存在する細菌で、正式名称はHelicobacter pylori(ヘリコバクター・ピロリ)といいます。1983年にオーストラリアのWarrenとMarshallにより発見されました。ねじれた螺旋型の形状(helico-)をしていることと胃の幽門付近に存在すること(pylori)に因んでHelicobacter pyloriという名称が与えられました。両博士はこの発見で2005年にノーベル生理・医学賞を受賞しています。ピロリ菌はヒトの慢性胃炎、胃潰瘍のみならず胃がんやMALTリンパ腫などと密接に関連していることが指摘され、プロトンポンプ阻害剤+抗生物質の併用による除菌治療が推奨されています。ただしピロリ菌に感染していても約7割のヒトは症状が現れない健康保菌者です。こうした健康保菌者に関しては耐性菌や副作用の問題から除菌治療より、ピロリ菌に有効な食品などによる菌の抑制、維持療法なども提案されています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ガラクトオリゴ糖』
ガラクトオリゴ糖とは、小腸で消化吸収されにくい性質を持つオリゴ糖の一種であり、大腸に到達してビフィズス菌の増殖を促進する、いわゆる「プレバイオティクス」の代表例の一つである。
ガラクトオリゴ糖は、砂糖(スクロース)よりも甘く、砂糖の約70%の甘さを持つ。また、でん粉(デキストリン)よりも粘性が高く、食品の保水性や保形性を向上させる効果がある。
ガラクトオリゴ糖は、乳糖やラフィノース、スタキオースなどの天然のオリゴ糖として存在するほか、ガラクトースから人工的に合成することもできる。ガラクトオリゴ糖は、食品添加物として様々な食品に使用されており、食品の甘味や粘性、保水性などを向上させる役割を果たしている。
ガラクトオリゴ糖は、ビフィズス菌などの有益な腸内細菌の増殖を促進し、腸内環境を改善する効果があることが知られている。ガラクトオリゴ糖は、大腸に到達すると、ビフィズス菌などの有益な腸内細菌によって分解されて短鎖脂肪酸(酢酸、プロピオン酸、酪酸など)を産生する。
短鎖脂肪酸は、腸内環境を整え、腸の蠕動運動を促進する効果がある。また、短鎖脂肪酸は、大腸の粘膜細胞のエネルギー源となり、大腸の健康維持に役立つ。
ガラクトオリゴ糖は、腸内環境を改善し、健康維持に役立つオリゴ糖の一種である。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康
アミノ酸とは、単にタンパク質を構成する最小の単位である。タンパク質は生命活動に欠かせない栄養素ですが、その構成要素であるアミノ酸も同様に重要な役割を果たしています。アミノ酸は、20種類のアミノ酸から構成され、それぞれのアミノ酸には個性的な特徴があります。また、アミノ酸は、体内でタンパク質に結合して利用されますが、タンパク質を構成していない「非タンパク質アミノ酸」と呼ばれるアミノ酸も存在する。これらの非タンパク質アミノ酸は、神経伝達物質やホルモンの構成成分として働いています。
Read More
 その他
その他 腸内環境改善と健康『ロコモティブシンドロームとの関連性』
運動器に障害を起こし、歩行や日常生活に不自由をきたすロコモティブシンドロームとはどのようなものなのでしょうか。ロコモティブシンドロームは、骨粗鬆症、変形性関節症・変形性脊椎症、サルコペニアなどの疾患をまとめて指す言葉です。骨粗鬆症は、骨がスカスカになってもろくなり、転倒などで骨折しやすくなる病気です。変形性関節症・変形性脊椎症は、関節や脊椎の軟骨がすり減って痛みが出たり、動かしにくくなったりする病気です。サルコペニアは、筋肉量が減少して身体機能が低下する病気です。ロコモティブシンドロームは、健康寿命を短縮させ、介護が必要になる原因となることもあります。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境改善と健康
フレミングが1929年に抗生物質を発見し、代田 稔が予防医学の重要性を提唱した1929年から1953年頃、日本では多くの感染症が流行していました。結核、赤痢、コレラ、腸チフス、パラチフスなどがその代表です。これらの感染症は、死亡率が高く、国民の健康を脅かしていました。
代田 稔は、感染症の予防には、腸内環境を整えることが重要であると考えました。腸内には、善玉菌と悪玉菌がいて、善玉菌が優勢であれば健康に良いとされています。しかし、ストレスや食生活の乱れなどによって、悪玉菌が増えると、腸内環境が悪化し、感染症にかかりやすくなります。
代田 稔は、腸内環境を整えるために、ラクトバチルス カゼイ シロタ株を開発しました。ラクトバチルス カゼイ シロタ株は、腸内の悪玉菌を抑制し、善玉菌を増やす効果があります。シロタ株を摂取した人々は、感染症にかかりにくくなるという報告があります。
Read More
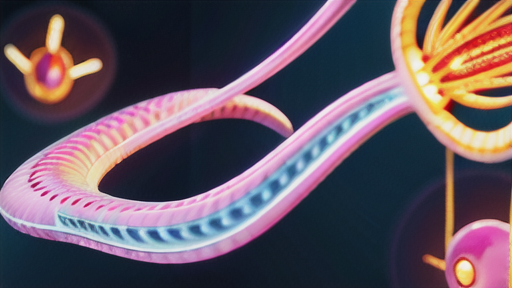 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『放射線殺菌』について
放射線殺菌は、食品の安全性を確保するために用いられる技術であり、食品の品質を低下させることなく、細菌などの微生物を殺菌することができる。海外では、香辛料や乾燥野菜の殺菌、国内では、じゃがいもの発芽抑制などに5~10Kgyの放射線の照射が行われている。
放射線殺菌が消化器系に及ぼす影響については、多くの研究が行われており、放射線殺菌食品を摂取しても、消化器系の機能に悪影響を及ぼすという報告はない。また、放射線殺菌食品を摂取しても、腸内細菌叢に悪影響を及ぼすという報告はない。
放射線殺菌食品は、安全性の高い食品であり、安心して摂取することができる。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 カリウムで腸内環境を改善して健康に!
カリウムとは、元素記号K、原子番号19、原子量39.0983、周期表の1族に属する元素です。元素の中で最も反応しやすい元素の一つであり、水と激しく反応して水酸化カリウムを生成します。カリウムは、細胞内液に多く含まれており、細胞外液に多く含まれるナトリウムと拮抗して細胞の浸透圧の維持や神経伝達にかかわっている電解質です。また、筋肉の収縮や心臓の鼓動を正常に機能させるためにも必要なミネラルです。カリウムは、果物や野菜、肉類などに多く含まれています。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境と健康
腸内環境の改善は、角層水分含量を高めることで、健康的な肌を維持するのに役立ちます。腸内環境を改善するには、バランスのとれた食事をとることが重要です。発酵食品や食物繊維を多く含む食品を積極的に摂取すると、腸内細菌のバランスが整いやすくなります。また、適度な運動や十分な睡眠も、腸内環境の改善に効果的です。さらに、ストレスをためないようにすることも大切です。ストレスは腸内環境に悪影響を及ぼすため、リラクゼーションや趣味など、ストレスを解消する方法を見つけることが大切です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『骨密度』について
腸内環境と骨密度の関係
腸内環境は、骨密度に影響を及ぼすことが知られています。腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸(SCFA)は、骨の形成を促進する効果があることがわかっています。また、腸内細菌が産生するビタミンKは、骨のカルシウム沈着を促進する効果があります。さらに、腸内細菌が産生するセロトニンは、骨の形成を促進する効果があることがわかっています。
逆に、腸内環境が悪化すると、骨密度が低下する可能性があります。腸内細菌が産生する有害物質は、骨の形成を阻害する効果があることがわかっています。また、腸内細菌が産生する炎症性サイトカインは、骨の形成を阻害する効果があることがわかっています。さらに、腸内細菌が産生する活性酸素は、骨の形成を阻害する効果があることがわかっています。
これらのことから、腸内環境を改善することは、骨密度を高めるために重要であると考えられます。腸内環境を改善するために、食物繊維を多く含む食品を摂取したり、運動をしたり、ストレスを軽減したりすることが効果的です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『胃酸』
胃酸は、胃液の主成分の一つです。 その強酸性(pH 1~2)により、食物と一緒に胃に入ってきた細菌を殺菌します。また、食物中のタンパク質を変性させることで、消化酵素による消化を助けます。このような機能を有する胃酸の正体は塩酸(HCl)です。この塩酸は体内に存在しているわけではなく、胃壁から別々に分泌された水素イオン(H+)と塩化物イオン(Cl-)が胃内部で混ざって塩酸になるのです。胃酸の分泌は主に、食物が胃に入ることで産生される消化管ホルモン(ガストリン等)の働きにより促進されますが、アルコールやカフェインの摂取でも促進されます。そのため、これらを摂り過ぎると胃を傷めてしまうことがあります。
Read More
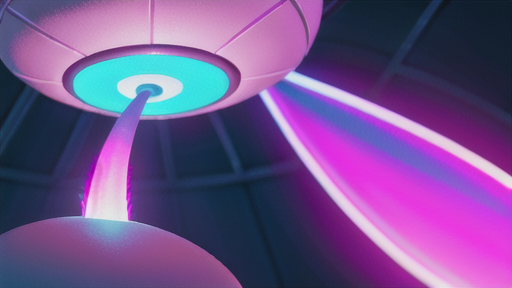 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康を支える紫外線
紫外線による腸内環境改善効果とは、紫外線によって腸内の細菌叢を変化させ、腸内環境を改善することです。紫外線は、殺菌作用があるため、腸内の有害な細菌を死滅させることができます。また、紫外線は、腸内環境を改善する善玉菌を増やす効果もあるとされています。
腸内環境が改善されると、さまざまな健康上の効果が期待できます。例えば、腸内環境が改善されると、便秘や下痢などの腸のトラブルが改善されることがあります。また、紫外線は、免疫力を高める効果もあるため、紫外線による腸内環境改善効果は、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりにくくなることにつながると期待できます。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で周術期感染予防
周術期(周術期とは、ある手術を行うにあたり、その手術にかかわる入院から麻酔、手術、回復までを含めた術前・術中・術後の一連の期間の総称です。)感染症対策の重要性が高まっています。なぜなら、手術後の腸内細菌による感染症は、患者の予後を左右する最も大きな問題となっているからです。腸内細菌叢のバランスを正常に保つことの重要性が注目されています。近年では、腸内細菌叢、腸内環境、腸管機能を正常に保つ作用のある特定のプロバイオティクスやシンバイオティクスが周術期感染防御に有用であることが示されており、医療現場においてその効果が期待されています。
Read More
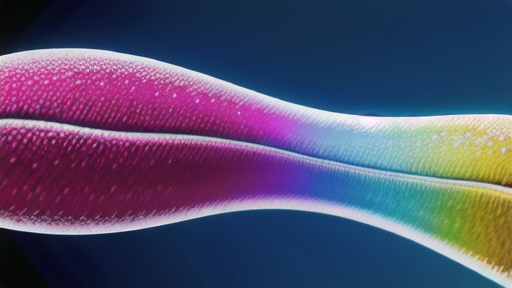 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『グラム染色法』
グラム染色法とは、ハンス・グラムによって発明された細菌の染色法です。この方法により、細菌は大きく2種類に分類されます。
紫色に染色される細菌はグラム陽性、赤色に染色される細菌はグラム陰性と呼ばれます。
この染色性の違いは、細胞膜の性質の違いに起因しており、2つのグループの細菌の生物的な特性の違いを表しています。
グラム陽性菌は細胞膜に厚いペプチドグリカン層を持ち、グラム陰性菌は細胞膜に薄いペプチドグリカン層を持ち、その上に外膜を持っています。
この外膜がグラム陰性菌をグラム陽性菌よりも抗生物質に対してより耐性があるものにしています。
Read More
 検査に関する解説
検査に関する解説 腸内環境を改善して健康に→ フローサイコメトリー法で解き明かす腸内細菌
腸内環境と健康の関係とは?
腸内環境は、私たちの健康に大きな影響を与えています。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌という3種類の菌が住んでおり、これらがバランスよく保たれていることが理想的です。善玉菌は、腸内を健康に保ち、悪玉菌の増殖を抑える働きがあります。悪玉菌は、毒素を産生し、腸内環境を悪化させます。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらの勢力が強い方に味方する菌です。
腸内環境が乱れると、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。例えば、便秘、下痢、腹痛、ガスが溜まる、消化不良、口臭、肌荒れ、アレルギー、肥満、糖尿病、心臓病、がんのリスク上昇などが挙げられます。
腸内環境を整えるためには、バランスの良い食生活、適度な運動、ストレスをためないことが大切です。また、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌を積極的に摂ることも効果的です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『レンネット』について
レンネットとは、チーズ製造時に使用される、母乳の消化のために数種の哺乳動物の胃で作られる酵素の混合物のことです。別名、凝乳酵素とも呼ばれています。レンネットは、牛乳中のタンパク質であるカゼインを凝固させ、チーズの基となるカードを作ります。レンネットは、子牛、ヤギ、ヒツジなどの哺乳動物の胃から抽出され、チーズ製造以外にも、ヨーグルトやアイスなどの乳製品の製造にも使用されています。
レンネットには、動物性レンネットと植物性レンネットの2種類があります。動物性レンネットは、子牛、ヤギ、ヒツジなどの哺乳動物の胃から抽出されるレンネットであり、伝統的なチーズ製造に使用されています。植物性レンネットは、アザミやイチジクなどの植物から抽出されるレンネットであり、動物性レンネットの代替品として使用されています。
レンネットは、牛乳中のタンパク質であるカゼインを凝固させて、チーズの基となるカードを作ります。カードは、その後、ホエイと分離され、チーズが作られます。レンネットは、チーズの風味や食感に影響を与えます。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ラクチュロース』
ラクチュロースとは、 難消化性オリゴ糖の一種で、フルクトース4位のヒドロキシル基にガラクトースがβ結合した二糖類です。一般に、乳糖を出発物質として異性化法によって工業的に生産されており、天然には存在しないとされていますが、生乳を殺菌して得られる牛乳等には微量に含まれています。食品として利用される場合はラクチュロース、医薬品として利用される場合はラクツロースと表記されることが多いです。ラクチュロースは、1957年に経口摂取によって便中のビフィズス菌を増やすことが初めて見いだされ、現在はプレバイオティクスの1種に位置づけられています。1960年にはラクチュロースが配合された育児用調製粉乳(粉ミルク)が国内において上市されました。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康課題『好乾性カビ』
好乾性カビ(=低湿性カビ。多くのカビが湿気を好むのに対して、乾燥を好むカビで水分活性が0.65~0.8の範囲でのみ生育するカビ。風呂場など湿気の多い場所ではなく通常の室内に普通に存在し、ハウスシックの原因のひとつではないかと言われている。)は、室内の乾燥した場所に生息するカビです。一般的なカビは湿気を好みますが、好乾性カビは乾燥を好みます。水分活性が0.65~0.8の範囲でのみ生育します。お風呂場など湿気の多い場所ではなく、通常の室内に普通に存在します。ハウスシックの原因の一つではないかと言われています。
好乾性カビは、ダニや花粉などのアレルゲンを吸着して、それらを空気中に放出します。このため、ハウスシックの症状を引き起こすことがあります。ハウスシックの症状としては、鼻水、くしゃみ、咳、目の痒み、皮膚のかゆみ、頭痛、吐き気、下痢などがあります。
好乾性カビを予防するには、室内の湿度を低く保つことが大切です。また、定期的に掃除をして、カビの繁殖を防ぐことも大切です。
Read More
 免疫力アップに関する解説
免疫力アップに関する解説 腸内環境を整えて健康に!マイクロバイオームってなに?
マイクロバイオームとは、土壌や腸内といった特定の環境に生息する微生物の集団全体とそのゲノム情報を指す言葉です。よく似た言葉に「腸内フローラ」がありますが、「腸内フローラ」が主に腸の中の細菌(乳酸菌やビフィズス菌など)といった一部の集団を対象とするのに対して、「マイクロバイオーム」は細菌だけではなく真菌(カビのなかま)、古細菌、バクテリオファージ(細菌にのみ感染するウイルス)なども含めた、大きな生物集団を対象にしています。2000年代後半に登場した次世代シークエンサーと呼ばれる遺伝子解析装置により、以前のように細菌を培養することなく、微生物集団全体の遺伝子を一度にまとめてとらえることができるようになりました。こうした測定技術の進歩により、昨今では微生物集団全体のゲノム情報を余すことなく研究することのできるマイクロバイオーム研究が盛んに行われるようになってきています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善に好塩菌!?
腸内環境と健康の関係
腸内環境は、ヒトの健康に大きな影響を与えています。腸内には、善玉菌と悪玉菌が住んでおり、そのバランスが健康を維持する上で重要です。善玉菌は、食物繊維を分解して短鎖脂肪酸を生成したり、ビタミンを合成したり、免疫機能を強化したりする働きがあります。一方、悪玉菌は、有害物質を産生したり、腸の粘膜を傷つけたり、感染症を引き起こしたりする働きがあります。
腸内環境が乱れると、善玉菌が減少して悪玉菌が増加します。この状態が続くと、下痢や便秘、腹痛などの消化器症状が現れたり、肌荒れや肥満、糖尿病などの生活習慣病のリスクが高まったりします。また、腸内環境の乱れは、うつ病や自閉症などの精神疾患にも関連していることがわかっています。
腸内環境を整えるためには、食物繊維を多く含む食品や発酵食品を積極的に摂ることが大切です。また、ストレスを軽減したり、適度な運動をしたり、十分な睡眠をとったりするなど、生活習慣を見直すことも重要です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善する食品
F値とは、缶詰・レトルト食品などの殺菌工程管理に使われる数値です。全工程を通した加熱効果が、121℃で何分間の殺菌効果に相当するかを表しています。F値の単位は分です。通常、F値はボツリヌス菌に対する12Dを基準として計算されます。D120値0.2分として、12Dは0.2×12=2.4となります。
F値を求める式は次の通りです。
F値 =加熱時間(分) × 温度係数
温度係数は、加熱温度によって決まります。例えば、121℃の温度係数は1.0、110℃の温度係数は0.68、100℃の温度係数は0.4です。
F値は、缶詰・レトルト食品の殺菌工程管理に欠かせない数値です。F値を適切に設定することで、食品の安全性を確保することができるのです。
Read More
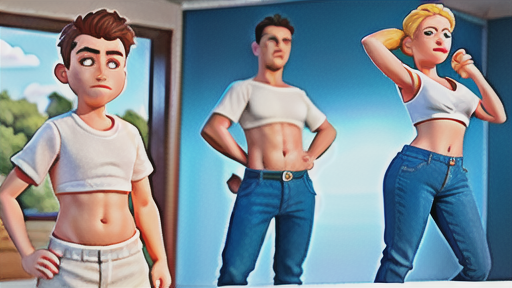 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境を整えて体脂肪率を減らす
腸内環境と体脂肪率の関係
腸内環境が肥満に関連しているという研究報告が数多くあります。腸内には善玉菌と悪玉菌が存在し、バランスを取りながら共存しています。善玉菌は腸内環境を健康に保ち、悪玉菌は腸内環境を悪化させます。近年、肥満傾向にある人は、善玉菌が少なく、悪玉菌が多いということがわかってきました。また、腸内環境を改善することで、体脂肪率を減少させることができることが報告されています。
善玉菌は、腸内の悪玉菌を抑え、腸内環境を健康に保つ働きがあります。善玉菌を増やすためには、食物繊維を多く含む食品や発酵食品を積極的に摂取することが大切です。食物繊維は善玉菌のエサとなり、腸内環境を改善するのに役立ちます。発酵食品には善玉菌そのものが含まれているため、腸内環境の改善に直接役立ちます。
悪玉菌は、腸内の善玉菌を殺し、腸内環境を悪化させる働きがあります。悪玉菌を増やす原因となる食品は、肉類、乳製品、高脂肪食品、砂糖が多い食品などです。これらの食品は、腸内の悪玉菌を増やし、腸内環境を悪化させます。
肥満を予防するためには、腸内環境を改善することが大切です。腸内環境を改善するには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らす必要があります。善玉菌を増やすためには、食物繊維を多く含む食品や発酵食品を積極的に摂取することが大切です。悪玉菌を減らすためには、肉類、乳製品、高脂肪食品、砂糖が多い食品を控えめにすることが大切です。
Read More









