 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善の専門家
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説
腸内環境の重要性
近年、腸内環境の重要性が注目されています。腸内環境とは、腸の中にすんでいる細菌叢のことです。細菌叢は、主に善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3つに分けられます。善玉菌は、腸内を健康に保ち、悪玉菌の繁殖を抑える働きがあります。悪玉菌は、腸内を悪化させ、病気の原因となる働きがあります。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらが優勢かによって、善玉菌側に加わったり悪玉菌側に加わったりする菌です。
腸内環境が乱れると、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。例えば、肥満、糖尿病、高血圧、動脈硬化、心疾患、脳卒中、がん、アレルギー、自己免疫疾患などです。また、腸内環境は、精神状態にも影響を与えることがわかっています。
腸内環境を改善するために、できることはたくさんあります。そのひとつが、食物繊維を多く摂ることです。食物繊維は、善玉菌のエサとなり、腸内環境を改善するのに役立ちます。食物繊維は、野菜、果物、豆類、玄米などに多く含まれています。また、ヨーグルトや納豆などの発酵食品を摂ることも効果的です。発酵食品には、善玉菌が含まれており、腸内環境を改善するのに役立ちます。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境と健康 慢性炎症
慢性炎症とは、本来一過性で治まるはずの炎症反応が低レベルではあるものの、長期間持続して慢性化した状態を指します。 このダラダラとくすぶるような炎症状態が持続すると、生体組織の機能や構造に異常が生じてさまざまな疾患の原因になることが知られています。とくに、非感染性疾患と総称される生活習慣病やがんなどを引き起こす要因として、慢性炎症が注目されています。慢性炎症が生じるメカニズムについては不明な点が多く、研究途上にありますが、最近では腸内フローラの乱れやそれに伴うリポ多糖などの菌体成分の体内への移行が関与する可能性が指摘されています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『アフラトキシン』について
アフラトキシンとは、カビ毒(マイコトキシン)の一種で、主にアスペルギルス属のAspergillus flabus、A. parasiticus、A. nomiusが産生する毒素です。最强の発癌性物質として知られており、その化学構造によりB1、B2、G1、G2など10数種類に分類されます。アフラトキシン産生株は主に熱帯、亜熱帯地域に生息し、当該地域で収穫された米、麦類、トウモロコシ、ナッツ類、香辛料からアフラトキシンが検出されることが多いです。
Read More
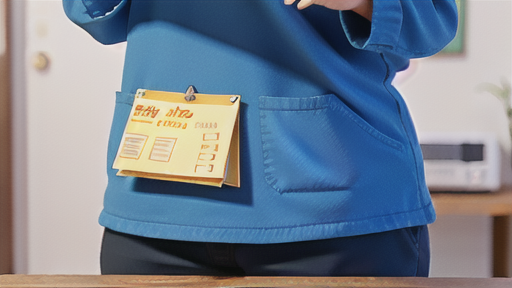 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で健康に!炎症性腸疾患とは?
腸内環境改善と健康
近年、腸内環境が健康に与える影響が注目されています。腸内環境には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類が存在し、それぞれのバランスが健康を維持する上で重要です。善玉菌は、有害な物質を分解して無害なものにする、免疫力を高める、ビタミンの合成を助けるなどの働きをします。悪玉菌は、有害な物質を産生して腸内環境を悪化させ、感染症の原因となることがあります。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらが増加しても、どちらかの勢力に加わる菌です。
腸内環境が悪化すると、腸内細菌のバランスが崩れ、悪玉菌が増加してしまいます。すると、腸内環境が悪化して有害物質が産生され、腸の粘膜が炎症を起こしてしまいます。これが、炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease IBD)の原因の一つと考えられています。IBDは、潰瘍性大腸炎とクローン病の2種類に分類されます。潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜がびらんを起こし、潰瘍を形成する病気です。クローン病は、消化管のどの部分でも炎症を起こす病気です。両方の病気とも、腹痛、下痢、血便などの症状が現れます。
Read More
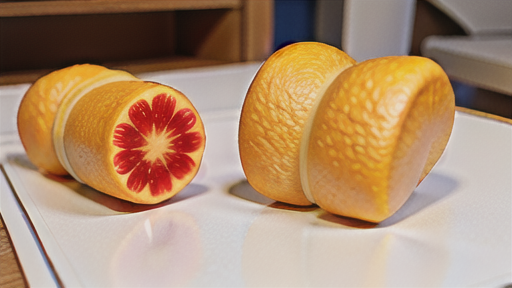 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『炭水化物』
炭水化物は、人間が生きていく上で必須の栄養素であり、エネルギー源や細胞を構成する成分として重要な役割を果たしています。 炭水化物には、単糖類、二糖類、多糖類の3種類があり、それぞれ構造や性質が異なります。単糖類は、炭素原子数が3つ以上の糖であり、その中に最も簡単な糖であるブドウ糖が含まれます。二糖類は、2つの単糖類が結合したもので、砂糖や麦芽糖などが含まれます。多糖類は、多数の単糖類が結合したもので、デンプンやセルロースなどが含まれます。
炭水化物の種類の中で、特に重要なのが食物繊維です。 食物繊維は、人間が消化できない糖の一種であり、腸内で水分を吸着して膨らみ、便通を改善する働きがあります。また、食物繊維は、腸内細菌の餌となり、善玉菌を増やして腸内環境を改善する働きもあります。
炭水化物を多く含む食品としては、米、小麦粉、芋類、とうもろこし、砂糖などがあります。これらの食品をバランスよく摂取することで、健康的な体づくりをサポートすることができます。
Read More
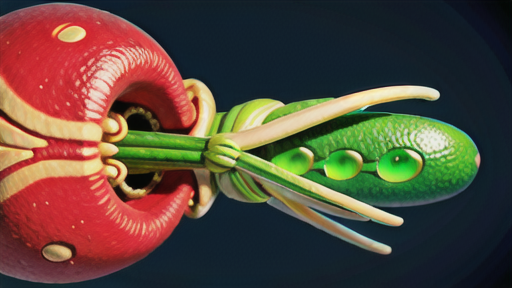 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸管免疫システム~健康を守る微細な兵士たち~
腸管免疫システムとは?
腸管免疫システムは、腸内環境を維持し、健康を維持するための重要な役割を果たす免疫システムであり、腸管粘膜の表面に存在するパイエル板、粘膜上皮細胞、粘膜固有層の免疫担当細胞などから構成されています。腸管免疫システムは、腸内細菌や食物などの異物を識別し、免疫応答を調整することで、腸内環境のバランスを維持しています。また、腸管免疫システムは、病原体の侵入を防ぎ、感染症から体を守る役割も担っています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境と健康
食中毒とは、有害物質に汚染された食品を摂ることで起こる健康障害です。 多くは、おう吐、腹痛、下痢などの症状を起こします。
食中毒は、その原因により細菌性、ウイルス性、自然毒、化学物質によるものに大別されます。従来、日本では発生件数、患者数ともに細菌性食中毒が多く、温度、湿度が高い夏季に多発しますが、最近では冬季のウイルス性食中毒が増えています。食中毒の原因には、食肉、穀類や魚介類に混入したサルモネラ、ウェルシュ菌、病原性大腸菌、腸炎ビブリオ、ノロウイルスなどが胃腸内で増殖することによる場合と、食品中でブドウ球菌などが作る毒素を摂る事で引き起こされる場合があります。食中毒の予防には、つけない(手指や調理器具はよく洗って清潔にする)、増やさない(食品は長時間外に放置しない、冷蔵保存する)、殺す(食品を十分に加熱する)が有効です。それでも、食中毒が疑われる症状がでた場合には、早めに医療機関を受診するようにしましょう。
食中毒は、その原因により細菌性、ウイルス性、自然毒、化学物質によるものに大別されます。従来、日本では発生件数、患者数ともに細菌性食中毒が多く、温度、湿度が高い夏季に多発しますが、最近では冬季のウイルス性食中毒が増えています。食中毒の原因には、食肉、穀類や魚介類に混入したサルモネラ、ウェルシュ菌、病原性大腸菌、腸炎ビブリオ、ノロウイルスなどが胃腸内で増殖することによる場合と、食品中でブドウ球菌などが作る毒素を摂る事で引き起こされる場合があります。食中毒の予防には、つけない(手指や調理器具はよく洗って清潔にする)、増やさない(食品は長時間外に放置しない、冷蔵保存する)、殺す(食品を十分に加熱する)が有効です。それでも、食中毒が疑われる症状がでた場合には、早めに医療機関を受診するようにしましょう。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 再生不良性貧血と腸内環境
再生不良性貧血とは、骨髄中の多能性幹細胞が障害されるため、骨髄の低形成を来し、末梢血での赤血球、白血球や血小板の減少などいわゆる汎血球減少症を呈する疾患です。顆粒球数、血小板数及び網赤血球数により重症度分類が行われます。重症では、顆粒球が500個/μL未満、血小板数が20,000個/μL未満、及び網赤血球が20,000個/μL未満の2または3項目を満たすものをいいます。中等症は顆粒球が1,000個/μL未満、血小板数が50,000個/μL、及び網赤血球数が60,000個/μL未満の2または3項目を満たすものをいいます。
原因は先天性と後天性に分けられます。遺伝子異常による先天性再生不良性貧血はFanconi貧血とよばれます。後天性再生不良性貧血の原因として、ウイルス、薬物(クロラムフェニコールなど)、鎮痛薬、抗炎症薬等や放射線等が挙げられています。血液検査では正球性正色素性貧血を呈す。血清鉄および血中エリスロポエチンは増加する。
治療方法は、輸血(白血球除去赤血球)、G-CSFを投与する。また、20歳以下の重症例では、骨髄移植が行われる。20~45歳では、免疫抑制療法、タンパク同化ホルモン療法などが選択されます。
原因は先天性と後天性に分けられます。遺伝子異常による先天性再生不良性貧血はFanconi貧血とよばれます。後天性再生不良性貧血の原因として、ウイルス、薬物(クロラムフェニコールなど)、鎮痛薬、抗炎症薬等や放射線等が挙げられています。血液検査では正球性正色素性貧血を呈す。血清鉄および血中エリスロポエチンは増加する。
治療方法は、輸血(白血球除去赤血球)、G-CSFを投与する。また、20歳以下の重症例では、骨髄移植が行われる。20~45歳では、免疫抑制療法、タンパク同化ホルモン療法などが選択されます。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善にフラクトオリゴ糖
フラクトオリゴ糖とは?
フラクトオリゴ糖は、スクロース(GF)に1~3分子のフラクトースが結合した3~5糖のオリゴ糖です。天然界では、タマネギ、チコリ、バナナ、ゴボウなどに含まれています。フラクトオリゴ糖は、人間の消化酵素では分解されないので、小腸をそのまま通過し、大腸まで届きます。大腸では、フラクトオリゴ糖を分解する有益な菌が増殖し、腸内環境を改善する効果があります。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『好塩性酵母』
好塩性酵母(耐塩性酵母)とは、13%以上の食塩濃度でも生育可能な酵母のことです。好塩性酵母は、耐塩性を持つものが多いですが、耐糖性を持つものも多数存在します。耐塩性と耐糖性は、どちらも浸透圧ストレスに対する耐性です。浸透圧ストレスとは、細胞と細胞外環境との間に浸透圧差が生じることで、細胞が水を求めて膨張して破裂してしまうことです。好塩性酵母は、この浸透圧ストレスに耐えることができるのです。代表的な好塩性酵母としては、味噌や醤油の醸造に関わるZygosacch rouxiiなどがあります。
Read More
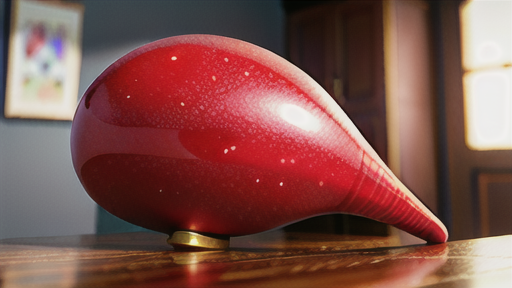 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康 〜出血性大腸炎〜
出血性大腸炎とは、抗生物質を服用した後に起こる大腸の炎症です。抗生物質は、細菌の感染症を治療するために使用されますが、腸内細菌叢にも影響を与えます。抗生物質を服用すると、腸内細菌叢のバランスが崩れ、有害な細菌が増殖することがあります。この有害な細菌が腸の粘膜を攻撃することで、出血性大腸炎を発症します。出血性大腸炎の主な症状は、水様性の下痢、腹痛、血便です。また、発熱や悪寒を伴うこともあります。出血性大腸炎は、通常、抗生物質を中止すると改善します。ただし、重症の場合は、入院して治療が必要になることもあります。出血性大腸炎を予防するためには、抗生物質を正しく服用することが大切です。抗生物質は、医師の指示通りに服用し、途中で服用を中止してはいけません。また、抗生物質を服用中は、ヨーグルトや納豆などの発酵食品を積極的に食べるようにしましょう。発酵食品には、腸内細菌叢のバランスを整える効果があります。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康
腸と皮膚の関係(皮膚腸相関)
腸と皮膚は、脳や心臓などの他の臓器と同様に、相互に関係しています。この関係は、皮膚腸相関と呼ばれています。皮膚腸相関は、腸内細菌叢が皮膚の健康に影響を与えることを意味します。腸内細菌叢とは、腸の中に住む細菌の集合体のことです。腸内細菌叢は、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類に分類することができます。善玉菌は、健康に良い働きをする細菌です。悪玉菌は、健康に悪い働きをする細菌です。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらにもなり得る細菌です。腸内細菌叢が乱れると、皮膚が炎症を起こしたり、アトピー性皮膚炎や乾癬などの皮膚疾患を発症しやすくなったりします。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康
腸内細菌叢とは、人体に生息する腸内細菌の集合体のことである。腸内細菌は、口から摂取した食物を分解したり、ビタミンやアミノ酸を合成したり、免疫機能を調節したりするなど、人体にとって重要な働きをしている。腸内細菌叢のバランスが乱れると、下痢や便秘、腹痛などの消化器症状だけでなく、うつ病やアレルギー、肥満などの全身疾患を発症するリスクが高まる。
腸内細菌は、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類に分類される。善玉菌は、乳酸や酢酸などの有機酸を産生して腸内を酸性にし、悪玉菌の増殖を抑える働きをしている。また、ビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌は、腸の粘膜を強化して、病原菌や有害物質の侵入を防ぐ役割も果たしている。悪玉菌は、腐敗物質を産生して悪臭や有害物質を発生させ、下痢や腹痛などの症状を引き起こす。日和見菌は、免疫力が低下しているタイミングや、善玉菌・悪玉菌のバランスが崩れた際に悪玉菌化して悪さをすることもあるが、普段は善玉菌や悪玉菌をコントロールする役割を担っている。
腸内細菌叢のバランスは、年齢や食生活、ストレス、薬物投与などさまざまな要因によって変化する。また、腸内細菌叢の乱れは、肥満、糖尿病、心臓病、がん、うつ病などのさまざまな疾患の発症リスクを高めることがわかっている。そのため、腸内細菌叢のバランスを良好に保つことが、健康の維持増進に重要である。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康 ~抗原と抗体の関係性~
腸内細菌叢と免疫システムの関係
腸内細菌叢は、腸内に生息する細菌の生態系のことです。腸内細菌叢は、人間の健康に重要な役割を果たしており、免疫システムの働きをサポートしています。腸内細菌叢は、免疫細胞を活性化したり、免疫グロブリンを産生したりすることで、感染症を防いでいます。また、腸内細菌叢は、腸内環境を改善することで、炎症を抑えたり、腸の機能を維持したりしています。
腸内細菌叢のバランスが崩れると、免疫システムの働きが低下し、感染症にかかりやすくなったり、アレルギーを発症したりするリスクが高まります。また、腸内細菌叢のバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、炎症が起こったり、腸の機能が低下したりする可能性があります。
腸内細菌叢のバランスを維持するためには、食生活や生活習慣に気を付けることが大切です。腸内細菌叢に良い影響を与える食品を積極的に摂り、腸内細菌叢に悪い影響を与える食品を避けることが重要です。また、適度な運動や睡眠、ストレスを溜めないことも腸内細菌叢のバランスを維持するのに役立ちます。
Read More
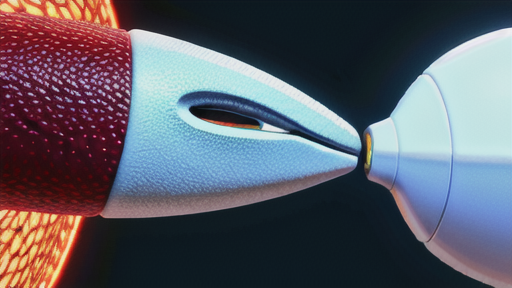 腸内環境に関する解説
腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康を守る酵素の役割とは?
酵素とは、生体内で化学変化を触媒するタンパク質です。 酵素は、反応を加速し、反応に必要なエネルギーを下げます。酵素は、消化、呼吸、代謝など、あらゆる生命活動を維持するために必要です。
酵素には、さまざまな種類があり、それぞれが特定の反応を触媒します。酵素の種類は、反応の種類によって分類されます。例えば、消化酵素は、食べ物を分解する反応を触媒し、代謝酵素は、エネルギーを産生する反応を触媒します。
酵素は、生体内で合成されます。酵素の合成は、遺伝子によって制御されています。酵素の量は、食事や環境によって変化します。例えば、タンパク質を多く摂取すると、消化酵素の量が増加します。また、運動をすると、代謝酵素の量が増加します。
酵素は、健康に重要な役割を果たしています。酵素が不足すると、化学反応が遅くなり、生体機能に障害が起こります。例えば、消化酵素が不足すると、食べ物を消化できなくなり、栄養失調になります。代謝酵素が不足すると、エネルギーを産生できなくなり、疲労や倦怠感などの症状が現れます。
酵素を多く摂取することは、健康に良いとされています。 酵素を多く摂取すると、化学反応が促進され、生体機能が活性化します。酵素を多く摂取する方法は、発酵食品や生野菜、果物を多く食べることです。また、サプリメントで酵素を摂取することも可能です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『トリプトファン(Trp)』
トリプトファンとは?
トリプトファンは、糖原性・ケト原性のアミノ酸の一種であり、必須アミノ酸に分類されます。必須アミノ酸とは、人間の体内では合成できないため、食事から摂取する必要があるアミノ酸のことです。トリプトファンは、タンパク質を構成する20種類のアミノ酸のうち、8番目に多いアミノ酸です。トリプトファンは、インドール核をもつ芳香族のアミノ酸で、わずかに苦味があり、水に溶けにくいという特徴があります。また、トリプトファンは、セロトニン、メラトニン、ナイアシンなどの生合成の前駆体として重要な役割を果たしています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ビタミンK』
ビタミンKは、腸内フローラを整え、消化器系を改善するのに役立つ脂溶性ビタミンです。ビタミンKは、骨や血管の健康維持にも重要であり、骨粗しょう症や動脈硬化の予防にも役立っています。ビタミンKは、納豆や青菜、ブロッコリーなど、発酵食品や緑黄色野菜に多く含まれています。腸内環境を整えるには、ビタミンKを積極的に摂取すると良いでしょう。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ネト』
ネトについて知っておくべきこと
ネトは、食品の表面に特定の微生物が増えることによって生じる粘り気のある物質のことです。主にシュードモナス属細菌が原因で、通常、ネトは初期には細い糸引きから始まり、完全に腐敗したときには太い糸引き状態になります。ネトは、食品の品質を低下させ、人体に害を及ぼす可能性があるため、食品の安全性を確保するためには、ネトを予防することが重要です。ネトの予防には、食品を清潔な環境で取り扱い、保存する必要があります。また、食品を適切な温度で保存し、食品の腐敗を防ぐことも重要です。食品がネトを生じたら、すぐに廃棄することが大切です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康:細胞膜を整えることで、健康を維持しよう
細胞膜とは、細胞を包んでいる膜構造の総称であり、細胞内外の低分子物質の障壁となっている細胞質膜とその外側の細胞壁や細胞外被などの構造も含みます。細胞質膜は、主にリン脂質とタンパク質で構成されており、細胞の構造を維持し、細胞内外の物質の輸送を制御しています。
細胞壁は、主にセルロースやペクチンなどの多糖類で構成されており、細胞に強度と保護を与えています。細胞外被は、主に糖タンパク質で構成されており、細胞を保護し、細胞同士の接着を促進しています。
細胞膜は、細胞の生存に不可欠な役割を果たしており、細胞の機能を維持するために、常に健全な状態に保たれている必要があります。細胞膜が損傷すると、細胞の機能が低下したり、死滅したりする可能性があります。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境の改善と健康『一日摂取許容量』とは?
一日摂取許容量(ADIAcceptable Daily Intake)とは、食品添加物など食品に添加もしくは含まれる物質について、ヒトが毎日摂取しても影響が出ないであろうと思われるその物質の1日の接取許容量を意味する。この値は、動物実験などの安全性の試験結果をもとに算出され、食品の安全性を確保するために用いられている。ADIは、食品添加物のほか、農薬、医薬品、化粧品などの化学物質についても設定されている。ADIは、食品の安全性確保にとって重要な指標であるが、その値はあくまでも推定値であることに注意が必要である。ADIは、動物実験の結果をもとに算出されているため、ヒトへの影響が正確に予測できるわけではない。また、ADIは、食品の摂取量や個人の体質などによって異なる可能性がある。したがって、食品を摂取する際には、ADIを目安にしながら、過剰摂取に注意することが大切である。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『カロテン』
腸内環境と健康の関係
近年、腸内環境と健康の関係が注目されています。腸内環境とは、腸内に生息する細菌のバランスのことを指し、このバランスが乱れるとさまざまな病気を引き起こすことが知られています。例えば、腸内環境の乱れは、肥満、糖尿病、高血圧、動脈硬化などの生活習慣病の原因となることが分かっています。また、腸内環境の乱れは、アトピー性皮膚炎や花粉症などのアレルギー疾患、さらにはうつ病や自閉症などの精神疾患の原因ともなることが指摘されています。腸内環境が健康に与える影響は非常に大きく、その改善は、さまざまな病気の予防や治療に有効であると考えられています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 EPECと健康:腸内環境改善の重要性
腸内環境改善と健康「病原血清型大腸菌」
EPECとは何か?
EPECは、病原性大腸菌の一種であり、小児下痢症を引き起こす主要な原因菌です。 EPECは、腸管管腔内で付着して増殖し、毒素を産生して腸管細胞を傷害することで下痢を引き起こします。EPECは、世界中で下痢症を引き起こしていますが、特に発展途上国での罹患率が高いです。EPECは、乳幼児に感染することが多く、感染すると、発熱、嘔吐、下痢などの症状を引き起こします。EPECによる下痢症は、通常は数日で治癒しますが、重症化すると、脱水症や電解質異常を引き起こすことがあります。EPECによる下痢症を予防するためには、手指の洗浄や、食品の加熱調理を徹底することが重要です。また、EPECに感染した場合は、早期に受診することが大切です。
Read More
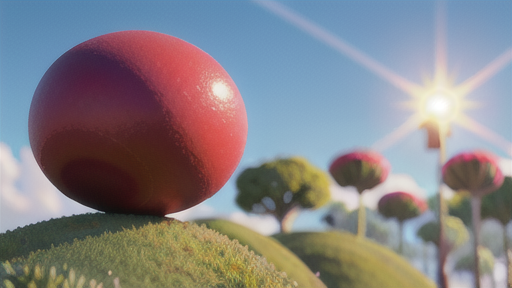 腸内環境に関する解説
腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康『ブドウ球菌』
ブドウ球菌とは?
ブドウ球菌とは、ブドウ球菌属に属するグラム陽性球菌の総称です。その名の通り、光学顕微鏡で観察すると「ブドウの房」のように見えることから命名されました。ブドウ球菌は、ヒトの表皮や粘膜に常在している正常細菌ですが、一部のブドウ球菌は感染症を引き起こすことがあります。
ブドウ球菌の中でも特に知られているのが、表皮ブドウ球菌と黄色ブドウ球菌です。表皮ブドウ球菌は、ヒトの表皮に常在しており、皮膚の健康を維持する役割を果たしています。しかし、免疫力が低下しているときなどに感染症を引き起こすことがあります。黄色ブドウ球菌は、食中毒の原因菌として知られています。また、皮膚感染症や肺炎などの感染症を引き起こすこともあります。
Read More
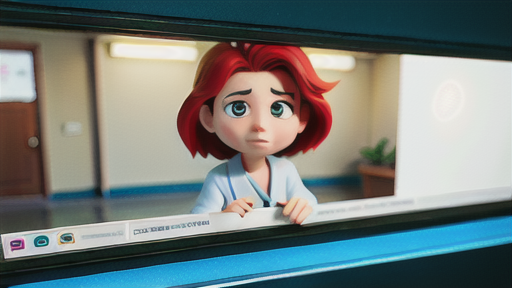 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善に期待大!種麹のチカラ
種麹は、味噌、醤油、清酒、焼酎、みりんなどの醸造食品の製造に用いられる麹を製造する際に、麹菌を蒸米などに加えたものです。通常米などを原料に麹菌を培養し、胞子を十分に着生させた後、乾燥させます。種麹には、整腸作用、免疫力向上作用、抗酸化作用、抗がん作用など、さまざまな健康効果があることが知られています。
種麹の整腸作用は、種麹に含まれる麹菌が生み出す酵素が、腸内環境を整えることによります。麹菌が生み出す酵素には、でんぷんを分解するアミラーゼ、タンパク質を分解するプロテアーゼ、脂質を分解するリパーゼなどがあります。これらの酵素が、腸内細菌の餌となるオリゴ糖やアミノ酸、脂肪酸などを生成し、腸内細菌のバランスを整えることで、整腸作用を発揮します。
種麹の免疫力向上作用は、種麹に含まれる麹菌が生み出すβ-グルカンが、免疫細胞を活性化することによります。β-グルカンは、キノコや海藻などに多く含まれる多糖類で、免疫細胞の表面にある受容体に結合することで、免疫細胞を活性化します。免疫細胞が活性化されると、細菌やウイルスなどの病原体に対する抵抗力が高まり、感染症にかかりにくくなります。
種麹の抗酸化作用は、種麹に含まれる麹菌が生み出すSOD(スーパーオキシドディスムターゼ)が、活性酸素を除去することによります。活性酸素は、体内の代謝によって生成される物質で、細胞を傷つけて老化やがんを引き起こす原因となります。SODは、活性酸素の一種であるスーパーオキシドを分解する酵素で、活性酸素による細胞のダメージを防ぐことができます。
種麹の抗がん作用は、種麹に含まれる麹菌が生み出す麹菌プロテアーゼが、がん細胞の増殖を抑制することによります。麹菌プロテアーゼは、タンパク質を分解する酵素で、がん細胞の増殖に必要なタンパク質を分解することで、がん細胞の増殖を抑制します。
Read More









