 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 健康アップに関する解説
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説
腸内環境の重要性
人間の腸内には、100兆個以上の細菌が生息しています。これらの細菌は、食物の消化や吸収、免疫機能の維持、有害物質の解毒など、さまざまな役割を果たしています。腸内環境が乱れると、これらの細菌のバランスが崩れ、健康に悪影響を及ぼすことがあります。
腸内環境を改善するには、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂ることが大切です。食物繊維は、善玉菌のエサとなり、腸内をきれいにしてくれます。また、発酵食品も善玉菌を増やすのに効果的です。ヨーグルト、納豆、味噌、漬物などは、積極的に摂りましょう。
ストレスを溜めないことも、腸内環境を改善するのに大切です。ストレスを感じると、腸内環境が悪化しやすいことがわかっています。規則正しい生活リズムを心がけ、適度な運動をしたり、趣味を楽しんだりして、ストレスを解消しましょう。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境改善で心筋梗塞を予防・改善
腸内環境と心筋梗塞の関係
心筋梗塞は、心臓を養う冠動脈が詰まり、心筋に血液が行き渡らなくなることで起こる病気です。心筋梗塞の発症には、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が深く関わっています。近年、腸内環境の乱れも、心筋梗塞の発症リスクを高めることがわかってきました。
腸内環境は、腸の中に住む細菌の種類やバランスのことを指します。腸内環境が乱れると、悪玉菌が増殖して善玉菌が減少し、腸内環境のバランスが崩れてしまいます。腸内環境の乱れは、肥満、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病の発症リスクを高めることが知られており、心筋梗塞の発症リスクを高めることも考えられています。
実際、腸内環境が乱れている人は、腸内環境が正常な人に比べて、心筋梗塞の発症リスクが2倍以上高いことがわかっています。また、腸内環境を改善することで、心筋梗塞の発症リスクを下げることができることも報告されています。
腸内環境を改善するには、食生活や生活習慣を見直すことが大切です。食物繊維を多く含む食品や、善玉菌を増やす効果のある食品を積極的に摂るようにしましょう。また、適度な運動や十分な睡眠も腸内環境の改善に効果的です。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境改善でメタボリックシンドロームを予防
腸内環境とメタボリックシンドロームの関係
近年、腸内環境とメタボリックシンドロームの関係に注目が集まっています。メタボリックシンドロームとは、肥満に伴って内臓脂肪が蓄積し、内臓脂肪の働きにより病的な異常がもたらされる結果、軽度の糖代謝、脂質代謝の異常、あるいは血圧の上昇が起こり、個々の病態は軽度でもこれらの病態が重なり合って動脈硬化による心血管病のリスクが高まっている病態を言います。
腸内細菌は、人体に有益な働きをする善玉菌と、有害な働きをする悪玉菌に分類されます。腸内環境が良い状態とは、善玉菌が優勢で、悪玉菌が抑制されている状態です。腸内環境が悪い状態とは、悪玉菌が優勢で、善玉菌が抑制されている状態です。
腸内環境が悪いと、腸から有害物質が産生され、それが血液中に取り込まれて全身を巡り、様々な悪影響を及ぼします。例えば、腸内環境が悪いと、肥満、糖尿病、動脈硬化、心疾患、脳卒中などのリスクが高くなります。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境と健康を守る緑黄色野菜を食べよう!
緑黄色野菜とは、原則として可食部100g当たりカロテン含量が600μg以上の野菜です。カロテンは、体内でビタミンAに変換される栄養素で、皮膚や粘膜の健康維持、免疫力の向上、視力の維持などに役立っています。また、トマトやピーマンなど、カロテン含量が600μg未満ですが、比較的多くのカロテンを含み、摂取量が多いため、栄養指導上緑黄色野菜とされています。
緑黄色野菜には、カロテンの他にも、ビタミンC、ビタミンE、食物繊維などの栄養素が豊富に含まれています。ビタミンCは、免疫力を高め、疲労回復に役立ちます。ビタミンEは、細胞を酸化から守る働きがあり、老化防止に効果的です。食物繊維は、腸内環境を整え、便秘を解消するのに役立ちます。
緑黄色野菜を積極的に食べることで、健康維持や病気の予防に役立てることができます。緑黄色野菜は、生で食べても加熱して食べてもおいしく食べることができます。生で食べる場合は、サラダやスムージーにして食べるのがおすすめです。加熱して食べる場合は、炒め物や煮物、汁物などにして食べるのがおすすめです。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境改善で溶血性貧血を改善
腸内環境と溶血性貧赤血球症の関係は、近年注目を集めています。溶血性貧赤血球症は、赤血球が破壊されて貧血になる病気です。その原因は、遺伝的要因、自己免疫疾患、薬剤など様々です。最近、腸内環境の乱れが溶血性貧赤血球症の発症に関連していることが分かってきました。
腸内には、善玉菌と悪玉菌が共生しています。善玉菌は、腸内を健康に保ち、悪玉菌の増殖を抑えています。悪玉菌は、腸内で有害な物質を産生し、腸内環境を悪化させます。腸内環境が悪化すると、腸壁の粘膜が傷つき、腸から有害な物質が血液中に侵入するようになります。この有害な物質が赤血球を破壊し、溶血性貧赤血球症を発症すると考えられています。
腸内環境を改善することで、溶血性貧赤血球症の発症を予防したり、症状を緩和することができる可能性があります。腸内環境を改善するには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが大切です。そのためには、食物繊維を多く含む食品を食べたり、整腸剤を飲んだりすることが有効です。また、ストレスを溜めすぎないようにすることも大切です。ストレスは、腸内環境を悪化させることがわかっています。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境を改善して脳卒中を予防する
腸内環境と脳の健康の関係
腸内環境は、脳の健康と密接に関係していることが分かってきました。腸内細菌は、神経伝達物質であるセロトニンやドーパミンを産生しており、脳の状態に影響を与えていると考えられています。また、腸内細菌は、腸のバリア機能を担っており、腸から侵入してくる有害物質を防いでいます。このバリア機能が低下すると、有害物質が脳にまで到達し、脳の炎症を引き起こす可能性があります。さらに、腸内細菌は、免疫システムにも関わっており、免疫機能を調整しています。免疫機能が低下すると、脳卒中のリスクが高まる可能性があります。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境と筋持久力
腸内環境が筋持久力に与える影響
腸内環境は、健康に大きな影響を与えるとされています。最近の研究では、腸内環境が筋持久力にも影響を与えることがわかってきました。筋持久力は、筋肉が活動する持久的能力のことです。筋持久力を決定する生理学的要因として、筋線維組成と筋肉内の血液循環が考えられます。一般的に遅筋線維が多く、また筋肉内の毛細血管が多いことが筋持久力にとって重要であるとされています。
腸内環境が筋持久力に影響を与えるメカニズムは、まだ完全に解明されていませんが、いくつかの説があります。その1つとして、腸内環境が筋肉のエネルギー代謝に影響を与えるという説があります。腸内細菌は、短鎖脂肪酸と呼ばれる物質を産生します。短鎖脂肪酸は、筋肉のエネルギー源として利用されることが知られています。そのため、腸内環境が良好な人は、筋肉のエネルギー代謝が活性化され、筋持久力が向上すると考えられています。
また、腸内環境が筋肉の炎症に影響を与えるという説もあります。腸内環境が乱れると、腸の粘膜が損傷し、炎症が起こりやすくなります。筋肉も、炎症が起こると筋力が低下することが知られています。そのため、腸内環境が良好な人は、筋肉の炎症が起こりにくく、筋持久力が維持されやすいと考えられています。
Read More
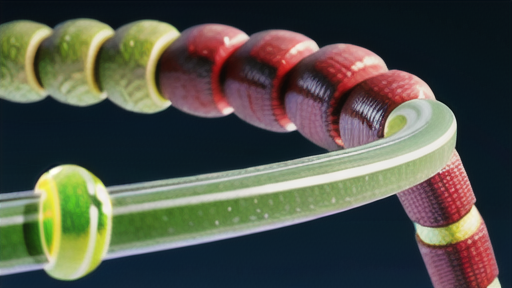 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境改善と健康 ~謎に包まれた糞便移植療法~
糞便移植療法の歴史と概要
糞便移植療法(FMT)は、何世紀も前から馬の慢性下痢や牛、羊の胃のアシドーシスに対する治療法として獣医領域で施行されていました。また、中国では4世紀の晋の時代にヒトの食中毒や重症下痢にFMTが行われ、欧米でも健康回復のため16世紀から行われていました。しかし、食中毒や下痢についてはその後原因菌やウイルスが発見されたため、抗菌薬や輸液などが治療の主体となっていました。
FMTに再度光を当てたのが、2013年にVanNoodらが、抗菌薬では治らなかった再発性Clostridium difficile(CD)感染症に対してFMTを行いCDが除菌できたという論文である。CD感染症とはもともと腸内細菌叢に存在するCDが抗菌薬投与による菌交代により異常増殖し、トキシンを産生し腸粘膜に黄白色の偽膜を作り偽膜性腸炎を呈する病気である。同菌はバンコマイシンやメトロニダゾールに対して感受性であり、本邦ではこの2剤のいずれかの投与により除菌され難治となることは少ない。しかし、欧米では再発性や上記2剤に抵抗性のCD感染があり、臨床的に大問題となっている。これらの難治性CD感染に対して、FMTが唯一有効な治療法と認められて、現在まで多数のFMT治療例が行われ、いずれも80%以上と高い有効率が報告されている。
FMTに再度光を当てたのが、2013年にVanNoodらが、抗菌薬では治らなかった再発性Clostridium difficile(CD)感染症に対してFMTを行いCDが除菌できたという論文である。CD感染症とはもともと腸内細菌叢に存在するCDが抗菌薬投与による菌交代により異常増殖し、トキシンを産生し腸粘膜に黄白色の偽膜を作り偽膜性腸炎を呈する病気である。同菌はバンコマイシンやメトロニダゾールに対して感受性であり、本邦ではこの2剤のいずれかの投与により除菌され難治となることは少ない。しかし、欧米では再発性や上記2剤に抵抗性のCD感染があり、臨床的に大問題となっている。これらの難治性CD感染に対して、FMTが唯一有効な治療法と認められて、現在まで多数のFMT治療例が行われ、いずれも80%以上と高い有効率が報告されている。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境改善とくる病
腸内環境とくる病の関係
くる病は、ビタミンDの欠乏、代謝異常や不応症によって成長期に起こる骨の石灰化障害です。骨端線の閉鎖以前の骨格の石灰化障害によって、骨の成長障害や骨・軟骨の変形を主症状とします。生後間もない乳児では頭蓋骨全体の軟化(頭蓋癆)が、年長の幼児では頭蓋骨の隆起、肋軟骨の肥大、脊柱の前彎症、後彎症、側彎症が、年長の小児や青年では歩行時の痛み、内反膝(O脚)や外反膝(X脚)が発現することがあります。
近年、腸内環境とくる病の関係が注目されています。腸内細菌は、ビタミンDの合成に関与していることがわかっています。また、腸内細菌のバランスが乱れると、ビタミンDの吸収が阻害されることがわかっています。そのため、腸内環境を改善することで、くる病の予防や治療に役立つ可能性があります。
腸内環境を改善するためには、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂取することが大切です。食物繊維は、腸内細菌のエサとなり、腸内細菌のバランスを整えるのに役立ちます。また、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌を含む食品を摂取することも大切です。善玉菌は、腸内細菌のバランスを整え、ビタミンDの吸収を促進するのに役立ちます。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境改善で健康を目指す!
胆道がんの予防にも腸内環境を整えることが大切です。腸内環境が悪化すると、発がん性物質が生成されやすくなり、胆道がんのリスクが高まる可能性があります。一方、腸内環境を良好に保つことで、発がん性物質の生成を抑え、胆道がんのリスクを下げることができます。
腸内環境を整えるためにできることはたくさんあります。まず、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂るようにしましょう。食物繊維は、腸内細菌のエサとなり、腸内細菌のバランスを整えるのに役立ちます。食物繊維は、玄米、野菜、果物などに多く含まれています。
また、発酵食品を摂ることも腸内環境を整えるのに効果的です。発酵食品には、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌が豊富に含まれており、腸内細菌のバランスを整えてくれます。発酵食品には、ヨーグルト、納豆、味噌、漬物などがあります。
さらに、適度な運動も腸内環境を整えるのに役立ちます。運動をすると、腸が刺激され、腸内細菌のバランスが整いやすくなります。また、運動は、ストレス解消にも効果的であり、ストレスが腸内環境に悪影響を与えることを防ぐことができます。
これらのことに気を付けることで、腸内環境を整え、胆道がんのリスクを下げることができます。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境改善でインスリン抵抗性を改善!
インスリン抵抗性とは、食後に上昇した血糖値を正常値に戻すために、過剰なインスリンを分泌する必要がある状態であり、インスリンが効きにくい状態である。インスリン抵抗性が持続すると、血糖値だけでなく、血圧や血中脂質のコントロールが乱れ、糖尿病、高血圧、脂質異常症、それらが重なったメタボリックシンドロームなど、様々な生活習慣病の発症リスクが高まる。インスリン抵抗性を引き起こす主な原因は、内臓脂肪型肥満である。内臓脂肪が過剰に蓄積すると、脂肪から放出されるアディポカインという物質の種類や量が変化してインスリンの働きを妨げるため、インスリン抵抗性に陥ると考えられている。このため、糖尿病やメタボリックシンドロームなどの生活習慣病を予防するためには、インスリン抵抗性やその背景となる肥満の是正が重要であり、これには食生活や運動などの生活習慣の改善が効果的と考えられる。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境改善と健康でうるおい肌へ
腸内環境と乳酸菌発酵エキスの関係
腸内環境は、健康に大きな影響を与えると考えられています。腸内には、さまざまな種類の細菌が存在し、それらの細菌のバランスが腸内環境を左右します。腸内環境が乱れると、免疫力が低下したり、消化器系のトラブルを起こしたりする可能性があります。乳酸菌は、腸内環境を整えるのに役立つ細菌の一種です。乳酸菌を多く含む食品を摂取すると、腸内環境が改善され、健康維持に役立つと考えられています。乳酸菌発酵エキスは、乳酸菌を培養して発酵させた食品です。乳酸菌発酵エキスには、乳酸菌そのものに加え、乳酸菌が産生する乳酸やアミノ酸などの成分が含まれています。乳酸菌発酵エキスを摂取することで、腸内環境を整え、健康維持に役立てることができる可能性があります。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 造血幹細胞と腸内環境の改善
造血幹細胞とは、白血球、赤血球、血小板などのすべての血球系細胞に分化しうる幹細胞のことです。造血幹細胞は、成人では主に骨髄に存在し、胎児では肝臓、脾臓に存在します。骨髄の造血幹細胞は、ニッチとよばれる骨髄と骨組織の境界部位に高濃度に存在します。造血幹細胞は、自己複製と分化をうまく調節しながら必要に応じて血球細胞を供給しています。また、G-CSF投与によって健康人の末梢血中に動員された造血幹細胞を血液疾患治療のための移植医療に利用することもできます。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境改善と健康『ホスファチジルセリン』
ホスファチジルセリン(Phosphatidylserine; PS)は、リン脂質(分子内にリン酸を含む脂質)という油の一種であり、分子内のリン酸にアミノ酸のセリンが結合した構造をしています。動物の細胞はリン脂質で形作られていて、そのうちの10~20%をPSが占めています。
PSは、脳に多く含まれることから特に脳機能との関連で研究が進められ、1986年には牛の脳由来のPSが老人性認知症に対して有効であることが明らかとなりました。その後、欧米を中心とした多くの臨床試験により、高齢者の物忘れや認知症に対する改善効果が示されています。現在では、牛の脳に比べて安価で安全性の高いPSが大豆を原料に製造されており、日本国内で実施された臨床試験により高齢者の物忘れに対する有効性が確認されています。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境改善と健康のしくみ
腸内環境の健康を維持するためには、善玉菌を増やし悪玉菌を減らすことが重要です。善玉菌は体に有益な働きをする細菌で、悪玉菌は体に有害な働きをする細菌です。 善玉菌を増やすには、発酵食品や乳製品などの乳酸菌を多く含む食品を摂取したり、オリゴ糖を摂取したりすることが効果的です。悪玉菌を減らすには、肉類やファストフードなどの脂っこいものや糖分の多い食品の摂取を控えたり、適度な運動をしたりすることが効果的です。
また、ストレスをためないようにしたり、十分な睡眠をとったりすることも腸内環境の健康に良い影響を与えます。腸内環境を整えることで、便秘や下痢、肌荒れ、肥満などのさまざまな体の不調を予防することができます。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境と健康:脊髄の役割
腸内細菌と健康
腸内には、1000種類以上、100兆個以上の腸内細菌が生息しています。腸内細菌は、食物を分解して栄養素を産生したり、有害な物質を分解したり、免疫機能をサポートしたりするなど、私たちの健康に欠かせない役割を果たしています。
腸内細菌のバランスが崩れると、様々な健康問題を引き起こすことがわかっています。例えば、腸内細菌の悪玉菌が増えると、腸内環境が悪化して下痢や便秘、腹痛などの消化器症状を引き起こしたり、肥満や糖尿病、心臓病、がんのリスクが高まったりする可能性があります。
逆に、腸内細菌の善玉菌を増やすことで、腸内環境を改善し、健康を維持・増進することができます。善玉菌を増やすためには、食物繊維を多く含む食品や発酵食品を積極的に摂ったり、適度な運動をしたり、ストレスをためないようにしたりすることが大切です。
腸内細菌は、私たちの健康に大きな影響を与えていることがわかっています。腸内環境を改善することで、健康を維持・増進することができます。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境改善と健康『味蕾』の関係とは?
味蕾とは、味物質を受容する上皮由来の細胞の集合体です。約100個の細胞から成り、一部の細胞は味覚受容体を発現しています。ヒトの場合、舌の乳頭、口蓋、喉頭に約1万個が存在します。
味蕾はタマネギ状の形状をしており、表層部は味孔として外界と接しています。中間、基底部には味神経が連絡し、味覚情報を延髄へと伝達しています。味蕾は、食物中の味物質を感知し、その情報を脳に伝えて、味覚を認識する役割を果たしています。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境改善と健康『平板培養法』について
腸内環境改善と健康の関係
腸内環境は、人間の健康に大きな影響を与えています。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌という3種類の菌が住んでおり、これらの菌のバランスが崩れると、体調不良や疾病の原因となります。善玉菌は、腸内を酸性に保ち、悪玉菌の増殖を防ぐ働きがあります。また、善玉菌は、ビタミンや短鎖脂肪酸を産生し、免疫力を高める働きも持っています。一方、悪玉菌は、腸内をアルカリ性に傾け、善玉菌の増殖を妨げます。また、悪玉菌は、毒素を産生し、発ガンや虚血性心疾患などの原因となります。日和見菌は、善玉菌が優勢なときは善玉菌のように働き、悪玉菌が優勢なときは悪玉菌のように働く菌です。
腸内環境のバランスが崩れると、さまざまな健康被害を引き起こす可能性があります。例えば、腸内環境が悪化すると、便秘、下痢、腹痛などの消化器症状が現れたり、免疫力が低下して風邪や感染症にかかりやすくなったり、肌荒れやニキビなどの皮膚トラブルが起こったりすることがあります。また、腸内環境の悪化は、肥満や糖尿病、虚血性心疾患、がんの発症リスクを高める可能性もあります。
腸内環境を改善するためには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが大切です。善玉菌を増やすためには、食物繊維やオリゴ糖などのプレバイオティクスを多く含む食品を摂取することが効果的です。プレバイオティクスは、善玉菌の餌となる成分であり、善玉菌の増殖を促進する働きがあります。また、ヨーグルトや納豆などの発酵食品を摂取することも善玉菌を増やすのに効果的です。悪玉菌を減らすためには、肉類や脂質などの動物性食品の摂取を控え、野菜や果物などの食物繊維を多く含む食品を摂取することが効果的です。食物繊維は、腸内を掃除する働きがあり、悪玉菌の増殖を妨げます。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境と健康『検便』について
腸内環境の乱れと健康
近年、腸内環境が健康に大きく影響を与えることが明らかになっています。腸内には100兆個以上の細菌が生息しており、これらの細菌は私たちの健康に良い影響を与えるものもあれば、悪い影響を与えるものもあります。善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れると、腸内環境が乱れて健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
腸内環境と病気の関係
腸内環境の乱れは、さまざまな病気のリスクを高めることがわかっています。例えば、肥満、糖尿病、高血圧、動脈硬化、腸炎、大腸がん、アトピー性皮膚炎、花粉症、うつ病などです。これらの病気のリスクを減らすためには、腸内環境を改善することが大切です。
腸内環境を改善する方法
腸内環境を改善するには、いくつかの方法があります。まず、食事に気を付けることが大切です。食物繊維の多い食品、発酵食品、乳酸菌飲料などを積極的に摂取するようにしましょう。また、適度な運動も腸内環境の改善に効果的です。適度な運動とは、週に3回以上、30分以上の運動をすることです。さらに、ストレスを溜めないことも大切です。ストレスは腸内環境を悪化させます。ストレスを溜めないためには、適度な運動をしたり、趣味を持ったり、友人と交流したりすることが大切です。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境改善と健康
フレミングが1929年に抗生物質を発見し、代田 稔が予防医学の重要性を提唱した1929年から1953年頃、日本では多くの感染症が流行していました。結核、赤痢、コレラ、腸チフス、パラチフスなどがその代表です。これらの感染症は、死亡率が高く、国民の健康を脅かしていました。
代田 稔は、感染症の予防には、腸内環境を整えることが重要であると考えました。腸内には、善玉菌と悪玉菌がいて、善玉菌が優勢であれば健康に良いとされています。しかし、ストレスや食生活の乱れなどによって、悪玉菌が増えると、腸内環境が悪化し、感染症にかかりやすくなります。
代田 稔は、腸内環境を整えるために、ラクトバチルス カゼイ シロタ株を開発しました。ラクトバチルス カゼイ シロタ株は、腸内の悪玉菌を抑制し、善玉菌を増やす効果があります。シロタ株を摂取した人々は、感染症にかかりにくくなるという報告があります。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境改善と健康『表在性膀胱がん』
表在性膀胱がんとは、膀胱がんをその形態などから分類したときのタイプの1つです。膀胱は尿を貯めておく袋のような臓器で、がんが袋の内側の粘膜(移行上皮)だけにとどまり、その外側の筋層までは達していないことが特徴です。内視鏡で見ると、表面がぶつぶつした乳頭状を呈しています。組織学的には、膀胱がんの90%以上を移行上皮がんが占めており、膀胱がんの大部分は表在性膀胱がんであるといえます。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境改善と健康『内分泌かく乱化学物質』
内分泌かく乱化学物質とは、体内で作り出される情報伝達物質「ホルモン」の正常なはたらきを乱す化学物質のことです。 一般に、「環境ホルモン」という造語が使われることがありますが、科学的には適切な表現ではありません。
これまでに、数百種類にも及ぶ化学物質にホルモン様作用が疑われていて、代表的な物質の例としては、プラスチックや缶詰の内面塗装の原料に使われるビスフェノールAや、プラスチックの酸化防止剤の原料や界面活性剤の製造原料に使われるアルキルフェノール類が挙げられます。
こうした化学物質は、生態系だけでなく、ヒトの生殖機能や胎児の発達に悪影響を及ぼす可能性があることがわかってきており、ビスフェノール類およびアルキルフェノール類の一部は、欧州において規制対象となっています。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境と高血圧の関係とは?
高血圧とは?
高血圧とは、最高血圧が140mmHg以上、最低血圧が90mmHg以上の状態を指します。血圧とは、心臓が収縮と拡張を繰り返す際に血管壁にかかる圧力のことで、血圧が高い状態が続くと、血管が硬くなって弾力性が失われ、心臓に負担がかかります。その結果、心筋梗塞や脳卒中などの重大な病気を引き起こすリスクが高まります。
高血圧の原因は、遺伝的な要因や食生活、運動不足、肥満、喫煙、過度の飲酒など、さまざまなものが考えられています。また、加齢とともに高血圧になるリスクも高まります。
高血圧の症状は、初期段階ではほとんどありませんが、進行すると、頭痛、めまい、動悸、息切れ、疲労感、胸痛、尿量減少などの症状が現れることがあります。
高血圧の治療法は、薬物療法、生活習慣の改善、運動療法などがあります。薬物療法では、降圧薬を服用して血圧を下げます。生活習慣の改善では、食塩を控え、野菜や果物を多く摂取し、適度な運動を行うことが大切です。運動療法では、有酸素運動を週に3回以上、30分以上行うことが推奨されています。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腎臓と腸内環境の関係性を明らかにする
腎機能と腸内環境の深い関連性
腎機能は、尿の生成と排泄による生体内部環境の恒常性維持と内分泌機能が腎臓の主な機能である。 尿の生成と排泄の基本単位は、腎小体と、尿細管で構成されるネフロンである。腎臓に流入した血液は、糸球体で濾過を受け、生体に必要な成分は尿細管で再吸収し、不要な成分は尿として排泄する。腎臓の内分泌機能は、造血ホルモンであるエリスロポエチン産生、昇圧物質であるレニン分泌、血管作動性物質であるプロスタグランジン、キニン産生、骨代謝に関与するビタミンDの活性化など重要な役割をもっている。
腸内環境は、腸管に住む細菌叢のバランスによって維持されている。腸内細菌叢は、食物を分解して栄養素を取り出し、有害物質を解毒するなど、様々な役割を果たしている。最近の研究では、腸内環境と腎機能が密接に関連していることが明らかになってきた。腸内細菌叢の乱れは、腎機能の低下を引き起こす可能性がある。
例えば、腸内細菌叢の乱れによって産生される有毒物質が、腎臓の細胞を傷つけ、腎機能を低下させることがある。また、腸内細菌叢の乱れは、腎臓の炎症反応を引き起こし、腎機能を低下させることもある。反対に、腸内環境を整えることで、腎機能を改善することができるという報告もある。
腸内細菌叢の乱れを防ぎ、腸内環境を整えることで、腎機能の低下を防ぐことができる可能性がある。そのためには、以下のことに注意することが大切である。
* 食物繊維を多く含む食品を摂取する。
* 乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスを摂取する。
* ストレスを避ける。
* 十分な睡眠をとる。
* 適度な運動をする。
Read More








