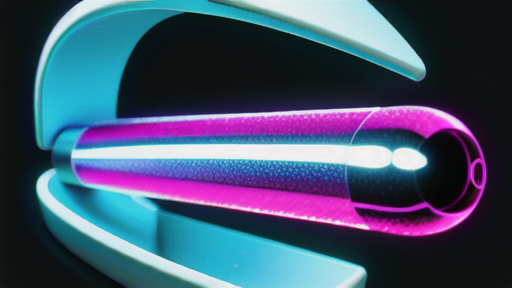 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善に関する解説
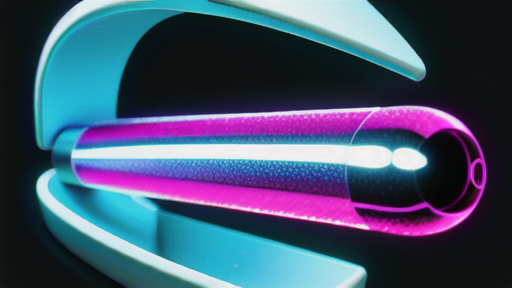 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説
抗生物質とは?
抗生物質とは、微生物が他の微生物の生育を阻害するために産生する物質のことです。主に薬用として使用され、抗生物質を含む食品は法律で禁止されています。抗生物質は、さまざまな細菌やウイルス、寄生虫などに対して効果を発揮します。抗生物質は化学構造によって、ペニシリン系、セファム系、テトラサイクリン系、マクロライド系、アミノグリコシド系などいくつかのグループに分けられます。各グループの抗生物質は、異なる作用機序を持ち、細菌やウイルスを死滅させたり、その増殖を阻害したりします。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康~従属栄養細菌を活用する~
従属栄養細菌とは、有機栄養物を比較的低濃度に含む培地を用いて低温で長時間培養したとき、培地に集落を形成するすべての菌をいう。主に水中では貧栄養状態にあるため、このような環境に長期間存在する菌は逆に栄養物が多い環境では、生育が難しい。従属栄養細菌は、栄養物を合成できないため、他生物から栄養分を得る必要がある。従属栄養細菌は、その栄養要求性によって、さらに細分化される。従属栄養細菌は、栄養物を合成できないため、他生物から栄養分を得る必要がある。従属栄養細菌は、その栄養要求性によって、さらに細分化される。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『TGF-βの役割と活用法』
トランスフォーミング増殖因子β(TGF-β)とは、細胞増殖、分化、アポトーシスを制御するタンパク質の一種です。 TGF-βは、当初は繊維芽細胞の形質転換を促進する増殖因子として同定されましたが、近年の研究で、多くの細胞種に対して増殖抑制、細胞分化やアポトーシスの誘導などにも寄与することが明らかとされています。例えば、骨芽細胞の増殖やコラーゲンのような結合組織の合成・増殖を促進する一方で、上皮細胞や破骨細胞の増殖に対しては抑制的に作用することが報告されています。従って、他の増殖因子と同様に、細胞分化・遊走・接着にも関与し、個体発生や組織再構築、創傷治癒、炎症・免疫、癌の浸潤転移などの幅広い領域において重要な役割を果たしていると考えられています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『コロニー』について
腸内環境改善と健康『コロニー(検査においては微生物が集まって形成される菌集落のこと。)』
腸内環境の重要性
腸内環境は、私たちの健康に大きな影響を与えていると言われています。腸内には、善玉菌と悪玉菌、そして日和見菌の3種類の腸内細菌が住んでいます。善玉菌は、私たちの体に有益な働きをする菌で、悪玉菌は、私たちの体に有害な働きをする菌です。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらかが多い方の菌に味方をする菌です。
腸内環境が良好な状態であれば、善玉菌が悪玉菌の働きを抑えてくれるため、健康を維持することができます。しかし、腸内環境が悪化すると、悪玉菌が増殖して善玉菌が減少します。すると、悪玉菌が腸内で有害物質を産生し、それが私たちの体に悪影響を及ぼします。
腸内環境が悪化すると、様々な健康被害を引き起こす可能性があります。例えば、肥満、糖尿病、高血圧、脳梗塞、心筋梗塞、ガンなどの生活習慣病のリスクが高まります。また、アトピー性皮膚炎、花粉症、ぜんそくなどのアレルギー疾患にもなりやすくなります。
腸内環境を良好な状態に保つためには、日頃から食事や生活習慣に気を付けることが大切です。善玉菌を増やすためには、食物繊維や乳酸菌を多く含む食品を積極的に摂りましょう。また、悪玉菌を増やさないためには、脂っこいものや甘いものを控え、適度な運動を心がけましょう。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境改善と健康『腎臓』についての基礎知識
腎臓は、尿管、膀胱、尿道とともに泌尿器系の臓器の一つで、泌尿器系は体内で生じた老廃物を除去して生命維持を図る。脊柱の両側の後腹膜腔に左右対を成しており、重さは約100g。ソラマメ型で、内側の凹みを腎門、腎門の内側を腎洞といい、尿管、動脈、静脈が出入りする。表面は線維被膜に包まれており、実質は、外表面に向かう皮質と、腎洞に向かって突出する十数個の髄質とに分かれる。腎髄質の先端を腎杯といい、ここに尿が送られる。
腎臓では尿が産生されるほか、体液の恒常性の維持、レニンやエリスロポエチンなどのホルモン産生、ビタミンD活性化など代謝作用にもあずかっている。
腎臓の働きは、主に以下の4つである。
1. 老廃物の排泄尿素、クレアチニン、尿酸などの老廃物を尿中に排泄する。
2. 水分の調整体内の水分の量を調節し、脱水や水中毒を防ぐ。
3. 電解質の調整ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどの電解質の濃度を調節し、体内の電気的バランスを維持する。
4. ホルモンの産生レニン、エリスロポエチン、ビタミンD活性化ホルモンなどのホルモンを産生する。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境を整える動物性食品
動物性食品の種類は大きく分けて、魚介類、肉類、卵類、乳類の4つです。 それぞれに特有の栄養が含まれており、健康維持に欠かせないものばかりです。
魚介類は、良質なたんぱく質に加えて、オメガ3脂肪酸やビタミンDが豊富に含まれています。 オメガ3脂肪酸は、心臓病や脳卒中のリスクを下げる効果があるとされています。ビタミンDは、骨を丈夫にするのに役立つ栄養素です。
肉類は、たんぱく質や鉄分、亜鉛が豊富です。 たんぱく質は、筋肉や臓器を作るのに必要な栄養素です。鉄分は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。亜鉛は、免疫力を高めるのに役立つ栄養素です。
卵類は、たんぱく質やビタミン、ミネラルが豊富に含まれています。 たんぱく質は、筋肉や臓器を作るのに必要な栄養素です。ビタミンは、体のさまざまな機能を正常に保つのに役立つ栄養素です。ミネラルは、骨や歯を丈夫にするのに役立つ栄養素です。
乳類は、たんぱく質やカルシウム、ビタミンB2が豊富に含まれています。 たんぱく質は、筋肉や臓器を作るのに必要な栄養素です。カルシウムは、骨や歯を丈夫にするのに役立つ栄養素です。ビタミンB2は、皮膚や粘膜を健康に保つのに役立つ栄養素です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 凍結前加熱食品で腸内環境は改善する?
凍結前加熱食品とは、凍結する前にあらかじめ加熱をして一次殺菌してから冷凍している食品のことです。ハンバーグや餃子、フライものなどで使われることが多いです。凍結前加熱食品は、冷凍食品の一種ですが、加熱後摂取冷凍食品とは異なります。加熱後摂取冷凍食品は、一度加熱して殺菌したものや、食べる前に加熱するように作られている必要がありますが、凍結前加熱食品は、加熱せずに食べても問題ありません。
凍結前加熱食品のメリットは、調理の手間を省けることです。加熱済みなので、解凍するだけで食べることができます。また、長期保存が可能です。冷凍保存することで、賞味期限を延ばすことができます。さらに、凍結前加熱食品は、栄養価が高いです。加熱することで、栄養価が失われにくいからです。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『官能評価』について
腸内環境改善とは、腸内細菌叢のバランスを整え、健康を維持することです。腸内細菌は、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3つに分類されます。
善玉菌は、腸内環境を整え、免疫力を高め、有害物質を分解する働きがあります。悪玉菌は、腸内環境を悪化させ、感染症を引き起こすことがあります。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらが優勢になるかによって、善玉菌の味方になったり、悪玉菌の味方になったりします。
腸内環境改善には、食生活の改善、運動、ストレス解消などが大切です。食生活の改善としては、善玉菌を増やすために、発酵食品や食物繊維を多く摂るようにしましょう。また、悪玉菌を減らすために、動物性脂肪や加工食品を控えましょう。 運動は、腸の蠕動運動を促し、便通を良くします。ストレス解消は、腸内環境を整えるために重要です。ストレスを感じると、腸内細菌のバランスが崩れ、悪玉菌が増加します。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 離乳期の腸内環境改善と健康
離乳期とは、赤ちゃんが母乳やフォローアップミルクから普通の食事へと移行する時期のことです。 一般的に、生後5~6か月頃から始まり、1歳前後まで続きます。離乳期は、赤ちゃんの成長と発達にとって重要な時期であり、腸内環境を整えることで、健康な体づくりをすることができます。
離乳期を4つの時期に区分されており、各時期により、離乳食回数、母乳・育児用ミルクの回数、調理形態が異なります。
・離乳初期(5~6か月)
母乳やフォローアップミルクを主食とし、離乳食を少しずつ始めます。
離乳食は、1日1回から始め、徐々に回数を増やしていきます。
離乳食は、おかゆや野菜スープなど、消化の良いものから始めます。
・離乳中期(7~8か月)
離乳食の回数を1日2~3回に増やします。
離乳食の種類も、おかゆや野菜スープだけでなく、肉類や魚介類、豆腐など、 varietyを追加していきます。
・離乳後期(9~11か月)
離乳食の回数を1日3回に増やします。
離乳食の種類も、おかゆや野菜スープだけでなく、肉類や魚介類、豆腐など、 varietyを追加していきます。
また、固形物を飲み込む練習をしましょう。
・完了期(12~15か月)
離乳食の回数は1日3回のままで、大人の食事と同じものを与えるようになります。この期間は、大人と同じ食事を食べれるように、味覚の調整、固形物への慣らし、咀嚼の練習を行います。
Read More
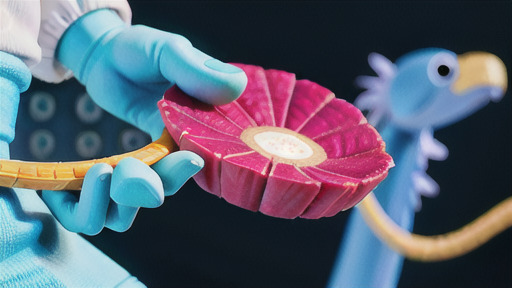 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『洗浄』について
腸内環境とは、腸内に棲息する細菌のバランスのことです。腸内には、さまざまな種類の細菌が棲息しており、その種類やバランスは人それぞれ異なります。腸内環境は、食生活や生活習慣などによって影響を受け、健康に大きな影響を与えます。
腸内環境が良い状態であれば、腸内細菌が食物を消化吸収してエネルギーや栄養素を作り出したり、有害物質を分解・排泄したりするなど、健康維持に役立ちます。逆に、腸内環境が悪化すると、腸内細菌のバランスが崩れ、有害物質が産生されやすくなり、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。
腸内環境を改善するには、食生活に気をつけ、生活習慣を見直すことが大切です。食事は、食物繊維や発酵食品を積極的に摂り、脂肪分や糖分の摂りすぎを控えるようにしましょう。生活習慣では、適度な運動を心がけ、ストレスを溜めないようにすることも重要です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境を整えることで健康を維持する
腸内環境と健康的关系性
腸内環境は、腸内に住んでいる細菌のバランスのことを指します。この細菌は、食べ物を消化したり、栄養素を吸収したり、有害物質を分解したりするなど、人間の健康に重要な役割を果たしています。腸内環境が悪いと、消化不良や腹痛、下痢などの症状が現れたり、免疫力が低下して感染症にかかりやすくなったりします。また、近年では、腸内環境と肥満、糖尿病、心臓病などの生活習慣病との関係も注目されています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『アフラトキシン』について
アフラトキシンとは、カビ毒(マイコトキシン)の一種で、主にアスペルギルス属のAspergillus flabus、A. parasiticus、A. nomiusが産生する毒素です。最强の発癌性物質として知られており、その化学構造によりB1、B2、G1、G2など10数種類に分類されます。アフラトキシン産生株は主に熱帯、亜熱帯地域に生息し、当該地域で収穫された米、麦類、トウモロコシ、ナッツ類、香辛料からアフラトキシンが検出されることが多いです。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境と健康 ~ゲノム解析がもたらす新知見~
腸内環境とは、腸内細菌叢によって構成された腸内生態系のことです。腸内には100兆個以上の腸内細菌が生息しており、それらは善玉菌、悪玉菌、日和見菌に分けることができます。善玉菌は、乳酸菌やビフィズス菌などで構成され、腸内環境を整える働きがあります。悪玉菌は、ウェルシュ菌やクロストリジウムなどの菌で構成され、腸内環境を悪化させる働きがあります。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらにもなる可能性がある菌で、腸内環境の状態によって変化します。
腸内環境は、健康に大きな影響を与えます。腸内環境が整っている人は、免疫力が強く、病気になりにくい傾向があります。また、腸内環境が乱れている人は、免疫力が弱く、病気になりやすい傾向にあります。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『難消化性デキストリン』
難消化性デキストリンとは何か?
難消化性デキストリンとは、トウモロコシデンプンに少量の塩酸を加えて加熱し、α-アミラーゼおよびグルコアミラーゼで処理して得られる食物繊維画分です。水溶性で低粘度の食物繊維であり、甘味度は砂糖の1/10程度と低く、食物繊維部分1gあたりのエネルギー値は1kcalです。食物繊維としての特徴を持つことから、第六の栄養素としての生体調節機能について研究が進められており、主に整腸作用、食後血糖および食後中性脂肪の上昇抑制などの生理機能が確認されています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『感染』について
腸内環境と感染症の関係
最近の研究では、腸内環境と感染症の関係が明らかになりつつあります。腸内には善玉菌、悪玉菌、日和見菌など、さまざまな種類の細菌が生息しています。善玉菌は腸内環境を整え、感染症から体を守る働きがあります。反対に、悪玉菌は腸内環境を悪化させ、感染症にかかりやすくします。日和見菌は、腸内環境が乱れると悪玉菌に変化し、感染症を引き起こすこともあります。
腸内環境が悪いと、感染症にかかりやすくなるだけでなく、感染症が重症化しやすいこともわかっています。例えば、腸内環境が悪い人は、インフルエンザにかかると重症化しやすいと言われています。また、腸内環境が悪い人は、肺炎にかかるリスクも高まります。
腸内環境は、食事や生活習慣によって改善することができます。善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすためには、食物繊維を多く含む食品や発酵食品を積極的に摂るようにしましょう。また、規則正しい生活を送ることも大切です。ストレスをためないようにし、十分な睡眠をとるようにしましょう。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ビフィズス菌増殖促進因子』について
ビフィズス菌増殖促進因子とは、ビフィズス菌の増殖を促進する物質のことです。 ビフィズス菌は、人間の腸内に生息する善玉菌の一種であり、健康を維持するために重要な役割を果たしています。ビフィズス菌を増やすことで、腸内の環境が改善され、健康の増進につながると考えられています。
ビフィズス菌増殖促進因子は、スイスチーズのスターターとして古くから利用されてきたプロピオン酸菌(Propionibacterium freudenreichii)が産生します。プロピオン酸菌は、牛乳を発酵させてチーズやヨーグルトなどの乳製品を作る際に使用される細菌の一種です。プロピオン酸菌が産生するビフィズス菌増殖促進因子は、ビフィズス菌の増殖に特異性を持っており、他の腸内細菌の増殖を促進することはありません。
ビフィズス菌増殖促進因子は、ビフィズス菌の増殖を促進することで、腸内の環境を改善し、健康の増進につながることが期待されています。ビフィズス菌を増やすことで、腸の蠕動運動が促進され、便秘や下痢などの症状を改善することが期待できます。また、ビフィズス菌が産生する酢酸や乳酸などの有機酸は、腸内のpHを酸性にし、悪玉菌の増殖を抑える効果があります。さらに、ビフィズス菌は、ビタミンB群やビタミンKなどの栄養素を産生し、腸の粘膜を強化する効果があります。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康
特定保健用食品とは、「特定の保健の目的で摂取するものに対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品」と定義される食品です。「健康増進法」及び「食品衛生法」の下に消費者庁による許可を受けたものにつき、健康強調表示(ヘルスクレーム)を認めています。特定保健用食品には、個別審査を受けない規格基準型に対して、製品ごとに個別に審査される特定保健用食品と条件付き特定保健用食品に分けられます。条件付き特定保健用食品は、従来の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないが、一定の有効性が確認される食品です。また、保健機能成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、特定保健用食品の許可表示の一つとして疾病リスク低減表示も認めています。特定保健用食品は、ヒトでその生理的有効性や適切な摂取量、摂取に伴う安全性などが医学的・栄養学的に明らかにされた食品であり、健康の保持・増進、生活習慣病の一次予防に役立つことを趣旨とした食品なのです。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『リン酸緩衝液』の知られざる関係
大見出し「腸内環境改善と健康『リン酸緩衝液(細胞生物学、生化学等の細胞を扱う実験でよく利用される緩衝液。リン酸とその塩類が配合されており、pHの極端な変化などを緩衝して細胞を保護する。)』」
小見出し「リン酸緩衝液とは?」
腸内環境改善と健康の鍵として、リン酸緩衝液が注目されています。リン酸緩衝液とは、細胞生物学や生化学の実験でよく利用される緩衝液の一種です。リン酸とその塩類が配合されており、pHの極端な変化などを緩衝して細胞を保護する役割を果たします。リン酸緩衝液は、腸内細菌叢のバランスを整え、腸内環境を改善することで、健康維持に役立つと考えられています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『特別用途食品』
特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示する食品のことです。 病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳及びえん下困難者用食品、特定保健用食品、などの種類があります。特別用途食品のうち、病者用食品のうち、低タンパク質食品、アレルゲン除去食品の許可基準があるものは適合性の審査を受け、個別に審査され、消費者庁による許可を受けたものは特別の用途に適する旨の表示が認められます。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『集落数』の重要性
腸内環境改善と健康「集落数」
腸内環境の重要性
腸内環境とは、腸内に生息する腸内細菌のバランスのことを指します。腸内細菌は、善玉菌、日和見菌、悪玉菌の3種類に分けられます。善玉菌は、乳酸や酢酸などの有機酸を産生して腸内を酸性に保ち、悪玉菌の増殖を抑えています。また、免疫力を高めて感染症を予防する役割も担っています。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらが増えるかによって、どちらの味方につくかを決めます。悪玉菌は、有害物質を産生して腸内を汚染し、腸炎や大腸炎などの病気の原因となります。
腸内環境が悪化すると、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。例えば、便秘や下痢、腹痛、ガス溜まりなどの消化器系の症状が出やすくなります。また、肌荒れ、ニキビ、アトピー性皮膚炎などの皮膚系のトラブルが起こることもあります。さらに、うつ病、不安障害などの精神的な症状が現れることもあります。
近年、腸内環境と健康の関係が注目されており、腸内環境を整えることで、様々な健康問題を予防・改善できると言われています。腸内環境を整えるためには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが大切です。善玉菌を増やすには、発酵食品を積極的に摂ったり、食物繊維が豊富な食品を摂ったりすることが有効です。また、悪玉菌を減らすには、肉類や脂っこい食品、加工食品などの摂り過ぎを控えたり、ストレスをためないようにすることが大切です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 筋肉を鍛えて腸内環境を改善
腸内環境改善の重要性
腸内環境は、私たちの健康に大きな影響を与えています。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌という3種類の種類の細菌が住んでいます。善玉菌は、腸内を健康に保ち、悪玉菌の増殖を防ぐ働きをしています。悪玉菌は、有害な物質を産生し、腸内環境を悪化させます。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌の双方に属する菌で、腸内環境の変化に応じて善玉菌にも悪玉菌にもなります。
腸内環境が悪化すると、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。例えば、肥満、糖尿病、高血圧、動脈硬化、がん、うつ病などです。腸内環境を改善することは、これらの健康問題のリスクを減らし、健康を維持するために重要です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康 『病原大腸菌』
病原大腸菌とは何か?
病原大腸菌とは下痢の原因となる大腸菌の総称です。大腸菌はもともと、人の腸内に常在する菌であり、ビタミン合成や栄養素の吸収、病原菌の侵入を防ぐなど、人の健康維持に役立っています。しかし、病原大腸菌は毒素を産生したり、腸管壁に侵入したりすることで、下痢や腹痛などの症状を引き起こします。
病原大腸菌は5つのタイプに分けられます。腸管出血性大腸菌(EHEC)、毒素原性大腸菌(ETEC)、組織侵入性大腸菌(EIEC)、病原血清型大腸菌(EPEC)、腸管付着性大腸菌(EAEC)です。これらのタイプは、下痢の症状や、毒素を産生するメカニズムが異なります。
病原大腸菌は、食中毒の原因となる菌としても知られており、食品を介して感染することが多いです。特に、十分に加熱されていない肉や卵、未殺菌の牛乳や果汁、生野菜や果物は、病原大腸菌に汚染されている可能性が高いため、注意が必要です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境を整えて健康に『エネルギー(熱量のこと。単位はカロリー、記号はcal。1カロリー(cal)は水1gを14.5°Cから15.5°Cまで1度上昇させるのに必要なエネルギーである。1,000cal=1kcal。ある物質の熱量価が100kcalであるとすると、そのすべてが放出されると100kgの水を1度上昇させる熱量をもつことになる。)』をアップ
腸内環境と健康の関係
人間の腸内には100兆個以上の細菌が生息していると言われています。これらの細菌は、善玉菌と悪玉菌に分けられます。善玉菌は、体に良い働きをする細菌で、悪玉菌は、体に悪い働きをする細菌です。腸内環境が悪化すると、悪玉菌が増え、善玉菌が減ってしまいます。これにより、腸内環境が乱れ、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。
腸内環境が悪化すると、肥満や糖尿病、高血圧、動脈硬化などの生活習慣病のリスクが高まります。また、免疫力が低下して、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなったり、アレルギーを発症しやすくなったりする可能性もあります。さらに、腸内環境の悪化は、うつ病などの精神疾患の発症にも関連していると言われています。
逆に、腸内環境が良好だと、免疫力が向上して、感染症にかかりにくくなります。また、善玉菌が腸内環境を整えることで、肥満や生活習慣病のリスクを減らすことができます。さらに、腸内環境が良好だと、精神状態が安定し、うつ病などの精神疾患の発症を防ぐ効果もあると言われています。
腸内環境を良好に保つためには、善玉菌を増やすことが大切です。善玉菌を増やすには、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂取することが効果的です。食物繊維は、善玉菌の餌になるため、善玉菌を増やすことができます。また、発酵食品を摂取することも効果的です。発酵食品には、善玉菌が含まれており、腸内環境を改善することができます。
Read More
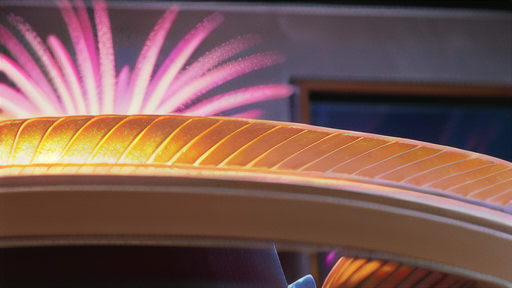 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『酪酸産生菌』
酪酸産生菌とは、酪酸を主な代謝産物の一つとして生成する嫌気性細菌の総称です。酪酸は、酪酸産生菌がブドウ糖などの糖質を分解したときに生成される短鎖脂肪酸の一種です。酪酸産生菌は、土壌中、水、下水、油田などの様々な環境に分布しており、人間の腸内にも生息しています。腸内細菌叢の構成は、その人が住んでいる地域、食生活、年齢、健康状態などによって異なりますが、酪酸産生菌はどの人間にも存在することが知られています。
Read More









