腸内環境改善と健康

腸内環境の研究家
腸内環境改善と健康『予防医学』とは何を意味しますか?

免疫力を上げたい
予防医学とは、病気にかかってから治療するのではなく、病気にかからないための『予防』が重要であると考え、生活習慣を改善することにより疾病の発症や進行を予防する一次予防が重要な社会的課題となった医学のことです。

腸内環境の研究家
腸内環境改善と予防医学にはどのような関係がありますか?

免疫力を上げたい
腸内環境改善は、予防医学の一環として、生活習慣を改善し、疾病の発症や進行を予防するために重要な要素です。腸内環境を改善することで、免疫機能を向上させ、感染症や生活習慣病などの疾病から身を守るのに役立ちます。
予防医学とは。
予防医学の歴史は古く、1929年に英国の細菌学者フレミングが感染症に対する強力な治療薬となる抗生物質を発見したことに端を発します。
日本でも、同時期に医学者である代田稔氏が病気にかかってから治療するのではなく、病気にかからないようにすることが重要であると考え、腸内の感染菌や腐敗菌などを制するラクトバチルス・カゼイ・シロタ株を発見しました。この発見は、プロバイオティクスの先駆けとなりました。
1953年、米国の医学者レベルとクラークは、予防医学を「病気を予防し、生命を延長し、身体ならびに精神の健康と能力を増進する科学と技術である」と定義しました。予防医学には、健康増進・発病予防を目的とした一次予防、早期発見・早期治療を目的とした二次予防、機能維持・回復を目的とした三次予防の3種類があります。
21世紀に入ると、生活習慣病が人類を脅かすようになり、生活習慣を改善することにより疾病の発症や進行を予防する一次予防が重要な社会的課題となりました。これは、代田氏が予見し、提唱した予防医学の時代が到来したことを意味します。
2020年4月以降、ラクトバチルス・カゼイ・シロタ株はラクチカゼイバチルス・パラカゼイ・シロタ株(L. パラカゼイ・シロタ株)に分類されています。
感染症予防とラクトバチルス カゼイ シロタ株

フレミングが1929年に抗生物質を発見し、代田 稔が予防医学の重要性を提唱した1929年から1953年頃、日本では多くの感染症が流行していました。結核、赤痢、コレラ、腸チフス、パラチフスなどがその代表です。これらの感染症は、死亡率が高く、国民の健康を脅かしていました。
代田 稔は、感染症の予防には、腸内環境を整えることが重要であると考えました。腸内には、善玉菌と悪玉菌がいて、善玉菌が優勢であれば健康に良いとされています。しかし、ストレスや食生活の乱れなどによって、悪玉菌が増えると、腸内環境が悪化し、感染症にかかりやすくなります。
代田 稔は、腸内環境を整えるために、ラクトバチルス カゼイ シロタ株を開発しました。ラクトバチルス カゼイ シロタ株は、腸内の悪玉菌を抑制し、善玉菌を増やす効果があります。シロタ株を摂取した人々は、感染症にかかりにくくなるという報告があります。
予防医学の提唱とプロバイオティクスのパイオニア

腸内環境改善と健康
予防医学の提唱とプロバイオティクスのパイオニア
英国の細菌学者フレミングは、感染症に対する治療医学の有力な手段となるアンチバイオティクス(抗生物質)を1929年に発見しました。そのころ日本の医学者であった代田稔は、病気にかかってから治療するのではなく、病気にかからないための「予防」が重要であると考え(予防医学)、腸内の感染菌や腐敗菌などの悪い菌を制するラクトバチルス・カゼイ・シロタ株※を発見し、プロバイオティクスのパイオニアとなりました。
一次予防、二次予防、三次予防
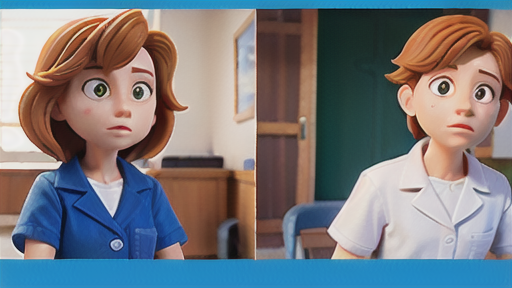
一次予防、二次予防、三次予防
予防医学は、病気を予防し、生命を延長し、身体ならびに精神の健康と能力を増進する科学と技術であると定義されています。健康増進・発病予防は一次予防、早期発見・早期治療は二次予防、機能維持・回復は三次予防と呼ばれています。
一次予防とは、生活習慣の改善などにより、疾病の発症や進行を予防することです。生活習慣病が人類を脅かし始める中、一次予防の重要性が再認識されています。二次予防とは、疾病の早期発見・早期治療を行うことで、重症化を防ぎ、治癒を早めることを目指しています。三次予防とは、疾病の機能維持・回復を図ることで、日常生活への復帰や社会参加を支援することを目指しています。
生活習慣病と予防医学

生活習慣病と予防医学
21世紀に入ると、生活習慣病が人類を脅かし始めました。生活習慣病とは、喫煙、飲酒、不健康な食事、運動不足などの生活習慣が原因で発症する病気のことです。生活習慣病は、がん、心臓病、脳卒中、糖尿病などの疾患を含みます。これらの病気は、日本の医療費の大部分を占めているだけでなく、多くの死者を出しています。
生活習慣病を予防するためには、生活習慣を改善することが重要です。生活習慣を改善するには、喫煙を止め、飲酒を控え、健康的な食事を摂り、適度な運動をすることが大切です。また、定期的に健康診断を受け、自分の健康状態を把握することも重要です。
予防医学は、生活習慣病の予防に大きな役割を果たしています。予防医学は、病気にかからないための予防を重視する医学です。予防医学では、生活習慣の改善、定期的な健康診断、ワクチン接種などの予防策を講じて、病気の発症を予防します。
予防医学は、病気にかかってから治療するよりも、費用が安く、身体への負担も軽くなります。そのため、予防医学は、生活習慣病の予防に欠かせないものとなっています。
生活習慣の改善による疾病予防

健康で長生きをするために必要不可欠なのが予防医学です。
予防医学とは、病気にかかってから治療するのではなく、病気にかからないための「予防」が重要であると考え、そのための科学と技術のことです。予防医学のパイオニアとして知られる日本の医学者、代田 稔氏は、20世紀初頭、腸内の感染菌や腐敗菌などの悪い菌を制するラクトバチルス カゼイ シロタ株※を発見。この発見により、プロバイオティクスの研究が大きく進歩しました。
21世紀に入ると、生活習慣病が人類を脅かし始め、生活習慣を改善することにより疾病の発症や進行を予防する一次予防が重要な社会的課題となりました。代田氏が予見し提唱した予防医学の時代が到来したのです。
※2020年4月以降、ラクチカゼイバチルス パラカゼイ シロタ株(L.パラカゼイ・シロタ株)に分類されています。









