 アレルギーに関する解説
アレルギーに関する解説 下痢
 アレルギーに関する解説
アレルギーに関する解説
食物アレルギーとは、特定の食物を摂取することで、免疫系が過剰に反応してアレルギー症状を引き起こす疾患です。原因となる食物は、小麦や卵、牛乳、エビ、カニ、果物など様々です。
食物アレルギーは、乳児や小児に多く見られますが、大人でも発症する可能性があります。症状は、じんましんや湿疹などの皮膚症状、下痢や嘔吐などの消化器症状、咳や喘息などの呼吸器症状など、様々です。
重度の食物アレルギーの場合、アナフィラキシーショックを起こすことがあります。アナフィラキシーショックは、血圧低下や意識障害などを伴う、生命にかかわる緊急事態です。
食物アレルギーの治療法は、原因となる食物を避けることです。また、アレルギー症状を緩和するために、抗ヒスタミン薬やステロイド薬などの薬が処方されることもあります。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境改善と健康『カルシウム』
カルシウムは、人体に最も多く含まれる無機元素であり、約1kg含まれています。体内のカルシウムの99%は骨に、残りの1%は血液と組織に分布しています。カルシウムは、生体及び細胞のあらゆる機能に関与しており、その役割は多岐にわたります。
カルシウムの役割とは
カルシウムは、骨や歯の形成に不可欠な元素です。カルシウムが不足すると、骨が弱くなり、骨折のリスクが高まります。また、カルシウムは、筋肉の収縮、神経の興奮、血液の凝固などにも関与しています。カルシウムが不足すると、筋肉の痙攣、神経の過敏性、血液の凝固異常などの症状が現れることがあります。
カルシウムの摂取不足は、骨粗鬆症や骨折のリスクを高めます。また、カルシウムの摂取不足は、筋肉の痙攣、神経の過敏性、血液の凝固異常などの症状が現れることがあります。
Read More
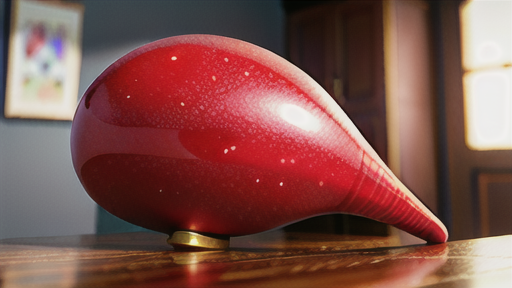 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康 〜出血性大腸炎〜
出血性大腸炎とは、抗生物質を服用した後に起こる大腸の炎症です。抗生物質は、細菌の感染症を治療するために使用されますが、腸内細菌叢にも影響を与えます。抗生物質を服用すると、腸内細菌叢のバランスが崩れ、有害な細菌が増殖することがあります。この有害な細菌が腸の粘膜を攻撃することで、出血性大腸炎を発症します。出血性大腸炎の主な症状は、水様性の下痢、腹痛、血便です。また、発熱や悪寒を伴うこともあります。出血性大腸炎は、通常、抗生物質を中止すると改善します。ただし、重症の場合は、入院して治療が必要になることもあります。出血性大腸炎を予防するためには、抗生物質を正しく服用することが大切です。抗生物質は、医師の指示通りに服用し、途中で服用を中止してはいけません。また、抗生物質を服用中は、ヨーグルトや納豆などの発酵食品を積極的に食べるようにしましょう。発酵食品には、腸内細菌叢のバランスを整える効果があります。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『下痢(下痢とは、便の水分含量が多くなり(85%以上)、泥状ないしは液状の便が反復して出る状態を指します。乳糖不耐症などの浸透圧性下痢は、牛乳に含まれる乳糖などの消化・吸収されにくい物質が多量に腸管内に留まって、腸管内へ水分が過剰に分泌されるために起こります。また、サルモネラ、腸炎ビブリオや腸管出血性大腸菌による腸炎では、傷ついた腸管から多量の水分がにじみ出ることにより下痢(浸出性下痢)が生じます。コレラ菌や黄色ブドウ球菌などが産生する毒素により、腸管内へ水分が過剰に分泌されるタイプの下痢(分泌性下痢)もあります。さらに、ストレスなどにより大腸の運動が活発になり、水分吸収が間に合わなくなるために起こる場合もあります(腸管運動亢進性下痢)。いずれの下痢についても、医師の的確な診断と治療が必要です。)』
下痢とは、便の水分含量が多くなり(85%以上)泥状ないしは液状の便が反復して出る状態を指します。下痢の原因は様々で、感染症、消化器疾患、薬剤の副作用などが挙げられます。下痢は、大量の水分が失われることで脱水症状を引き起こす可能性があり、特に乳幼児や高齢者では注意が必要です。
下痢を引き起こす感染症としては、サルモネラ菌や腸炎ビブリオ菌による腸炎、コレラ菌や黄色ブドウ球菌による食中毒などがあります。消化器疾患としては、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)、過敏性腸症候群(IBS)、便秘などがあります。薬剤の副作用としても、抗生物質や下剤などによって下痢が起こることがあります。
下痢が続く場合は、脱水症状や電解質異常などの合併症を防ぐために、医師の診察を受けることが大切です。医師は、下痢の原因を特定するために、問診、身体診察、検査(便検査、血液検査など)を行います。下痢の原因が特定できれば、適切な治療を開始することができます。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境の改善と健康
過敏性腸症候群(IBS)とは、器質的疾患が通常の臨床検査では認められず、腹痛と下痢や便秘といった便通異常が慢性に持続する状態である。IBSは主要文明国の人口の約10〜15%と高頻度であり、女性に多い。IBSは良性疾患であるが、生活の質(QOL)を障害して、高度にQOLを低下させることも多い。IBSの原因はいまだ不明である。
IBSの症状は、腹痛、下痢、便秘、ガス、膨満感などである。これらの症状は、ストレス、食事、睡眠不足などによって悪化することがある。IBSは、他の病気によって引き起こされることもあるが、ほとんどの場合、原因は不明である。
IBSの治療法は、症状を緩和することを目的とした対症療法が中心である。薬物療法、食事療法、運動療法、ストレス管理など、さまざまな治療法がある。IBSの症状を改善するために、生活習慣を見直すことも大切である。ストレスを軽減する、十分な睡眠をとる、バランスの取れた食事をとる、適度な運動をするなど、生活習慣を改善することで、IBSの症状を緩和することができる。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康 『病原大腸菌』
病原大腸菌とは何か?
病原大腸菌とは下痢の原因となる大腸菌の総称です。大腸菌はもともと、人の腸内に常在する菌であり、ビタミン合成や栄養素の吸収、病原菌の侵入を防ぐなど、人の健康維持に役立っています。しかし、病原大腸菌は毒素を産生したり、腸管壁に侵入したりすることで、下痢や腹痛などの症状を引き起こします。
病原大腸菌は5つのタイプに分けられます。腸管出血性大腸菌(EHEC)、毒素原性大腸菌(ETEC)、組織侵入性大腸菌(EIEC)、病原血清型大腸菌(EPEC)、腸管付着性大腸菌(EAEC)です。これらのタイプは、下痢の症状や、毒素を産生するメカニズムが異なります。
病原大腸菌は、食中毒の原因となる菌としても知られており、食品を介して感染することが多いです。特に、十分に加熱されていない肉や卵、未殺菌の牛乳や果汁、生野菜や果物は、病原大腸菌に汚染されている可能性が高いため、注意が必要です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康【ブリストル便性状スケール】
ブリストル便性状スケールとは?
ブリストル便性状スケールとは、大便の形状や硬さを7段階に分類する指標です。便秘や下痢の診断項目の一つとして使用されています。
このスケールは、英国ブリストル大学のHeaton博士が1997年に提唱したもので、各スコアの特徴は以下のとおりです。
1硬くてコロコロした木の実のような便
2いくつかの塊が集まって形作られたソーセージ状の便
3表面にヒビ割れがあるソーセージ状(バナナ状)の便
4滑らかで軟らかなソーセージ状(バナナ状)の便
5軟らかな半固形状の便
6境界がはっきりしない不定形の便
7水様便
一般的に、BSスコアが1から2は便秘の便、3から5が正常の便、6から7が下痢の便と区分けされます。便秘や下痢の方は、BSスコアが3から5に近づくほど、それぞれの症状が改善されたとみなされます。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『コハク酸』
コハク酸とは、化学式C4H6O4の有機酸であり、クエン酸回路の中間体です。スクシニルCoAからCoAが分離されて生成されますが、同時に放出されたエネルギーはGTP合成に使用されます。ケトン体の一つであるアセト酢酸はアセトアセチルCoAに代謝される際にスクシニルCoAからCoAが供給され、残りがコハク酸となります。したがって、ケトン体を利用する際にGTPを生成するのと同じエネルギーが利用されることになります。プロピオン酸発酵の中間体でもあります。腸内細菌により産生され、高濃度のコハク酸は家畜の下痢の原因と考えられています。大腸での吸収性に乏しく大腸内に蓄積すると極度のpH低下が起こり、大腸の動きを阻害します。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 EPECと健康:腸内環境改善の重要性
腸内環境改善と健康「病原血清型大腸菌」
EPECとは何か?
EPECは、病原性大腸菌の一種であり、小児下痢症を引き起こす主要な原因菌です。 EPECは、腸管管腔内で付着して増殖し、毒素を産生して腸管細胞を傷害することで下痢を引き起こします。EPECは、世界中で下痢症を引き起こしていますが、特に発展途上国での罹患率が高いです。EPECは、乳幼児に感染することが多く、感染すると、発熱、嘔吐、下痢などの症状を引き起こします。EPECによる下痢症は、通常は数日で治癒しますが、重症化すると、脱水症や電解質異常を引き起こすことがあります。EPECによる下痢症を予防するためには、手指の洗浄や、食品の加熱調理を徹底することが重要です。また、EPECに感染した場合は、早期に受診することが大切です。
Read More
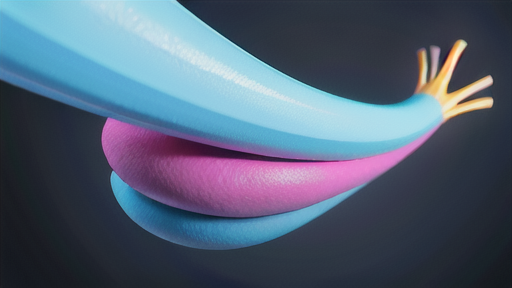 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境を整えて健康に!大腸がん予防と対策
大腸がんは、大腸(盲腸、結腸、直腸)に発生するがんであり、肛門に発生するものを含めることもあります。 多くの大腸がんは大腸ポリープから発生します。ポリープはキノコのような形をしていて、通常は腺腫とよばれる良性腫瘍です。 しかし、そのうちの一部は時間が経つとがんの一種である腺がんに進行します。また現在は、ポリープ由来でない平坦な病変や陥凹性病変から進行大腸がんになることがあることも明らかになっています。
年齢別に見た大腸がんの罹患率は、50歳代付近から増加し始め、高齢になるほど高くなります。 また、大腸がんの罹患率、死亡率はともに男性の方が女性に比べて高く、結腸がんより直腸がんにおいて男女差が大きい傾向があります。 大腸がんの症状は、血便、細い便、残便感、腹痛、下痢と便秘の繰り返しなど、排便に関する症状が多いのが特徴です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で健康に 過敏性腸症候群の症状を和らげる
過敏性腸症候群(IBS)とは、腹痛や腹部膨満感などの腹部症状と、下痢あるいは便秘などの便通異常を主体とする症状が、潰瘍やがんなどが認められないにもかかわらず持続する消化管の機能的疾患です。 IBSは消化器官の機能障害であり、炎症や損傷はありません。
IBSには、便秘型、下痢型、混合型、分類不能型の4つのタイプがあります。便秘型は、下痢がほとんどなく、便秘が主な症状です。下痢型は、便秘がほとんどなく、下痢が主な症状です。混合型は、便秘と下痢を両方経験します。分類不能型は、便秘型、下痢型、混合型のいずれにも当てはまらない症状を経験します。
IBSの症状は、人によって異なります。一般的な症状には、次のものがあります。
・腹痛
・腹部膨満感
・下痢
・便秘
・粘液便
・ガス
・吐き気
・嘔吐
・疲労感
・集中力の低下
・睡眠障害
・不安
・うつ病
IBSの原因は完全には解明されていませんが、いくつかの要因が関与していると考えられています。これらの要因には、次のものがあります。
・腸内環境の乱れ
・運動不足
・ストレス
・食事
・遺伝
IBSは治療法のない慢性疾患ですが、症状をコントロールすることは可能です。治療法としては、次のものがあります。
・食事療法
・運動
・ストレス管理
・薬物療法
・腹痛
・腹部膨満感
・下痢
・便秘
・粘液便
・ガス
・吐き気
・嘔吐
・疲労感
・集中力の低下
・睡眠障害
・不安
・うつ病
IBSの原因は完全には解明されていませんが、いくつかの要因が関与していると考えられています。これらの要因には、次のものがあります。
・腸内環境の乱れ
・運動不足
・ストレス
・食事
・遺伝
IBSは治療法のない慢性疾患ですが、症状をコントロールすることは可能です。治療法としては、次のものがあります。
・食事療法
・運動
・ストレス管理
・薬物療法
Read More
 その他
その他 腸内環境改善と健康『ノロウイルス』
ノロウイルスとは、ヒトに感染し、胃腸炎を起こすウイルスの一種です。一年を通して発生していますが、特に冬季に流行します。潜伏期間は24~48時間、症状は1~2日とされています。子供や高齢者は脱水症状に注意を要します。貝類は体内にウイルスを蓄積しやすく、特にカキは生で食されるため感染源になることもあります。感染者の便や吐物には多量のウイルスが含まれていて、二次感染の防止が重要となります。消毒には85℃、1分以上の加熱や次亜塩素酸ナトリウムが有効です。治療には下痢止めなどが使われますが、ウイルスの排出を抑えて回復を遅らせるという説もあります。ワクチンはまだありません。1968年米国ノーウォークで発見されたため最初はノーウォークウイルス(Norwalk virus)と呼ばれていましたが、2002年からはノロウイルス(Norovirus)と名前が変わりました。この科にはノロ、サポ、ラゴ、ベシの4属があり、ヒト感染性は前2者です。ヒト感染性のものは培養系が確立されていないため、検査や治療方法に関する研究が、他のウイルスより遅れています。
Read More









