 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 健康
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説
-# 腸内環境改善と健康『ケカビ(ケカビ属(Mucor、ムコール)の総称。ケカビは、接合菌の中でもっとも普遍的に見られる種で、土壌、糞、食品、その他、様々な湿った有機物上に出現する。)』-#
-- ケカビとは何か?--
ケカビとはケカビ属に属する接合菌の一種です。接合菌とは、2つの菌糸が融合して生殖を行う菌類の仲間です。ケカビは、土壌、糞、食品、その他のさまざまな湿った有機物上に生息し、広く分布しています。
ケカビは、生殖器官である接合胞子が特徴的です。接合胞子は、2つの菌糸が融合して形成される球状の構造体で、内部に多数の胞子が含まれています。接合胞子は、環境条件が整うと、胞子が発芽して新しい菌糸が生じ、新しいケカビの個体が形成されます。
ケカビは、分解者として生態系において重要な役割を果たしています。ケカビは、有機物を分解して栄養を得ており、その過程で、二酸化炭素や水が生成されます。この分解作用により、有機物がリサイクルされ、新たな生命の誕生に貢献しています。
また、ケカビは、食品や飼料の生産にも利用されています。ケカビは、有機物を分解して発酵させることで、食味や栄養価を高めることができます。ケカビを利用した発酵食品には、チーズ、醤油、味噌、ヨーグルトなどがあります。また、ケカビは、飼料の生産にも利用されており、家畜の栄養価を高めるのに役立っています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境と低出生体重児の健康
低出生体重児は、2,500g未満で出生した新生児であり、近年増加傾向にあります。低出生体重児は、正常な体重で生まれた新生児に比べて、感染症や呼吸器疾患にかかりやすいなど、健康上の問題を抱えるリスクが高いことが知られています。
最近では、腸内環境の乱れが、低出生体重児の健康に悪影響を及ぼす可能性があることが報告されています。腸内環境は、腸内に生息する細菌のバランスによって保たれており、免疫機能や栄養吸収など、さまざまな健康に重要な役割を果たしています。低出生体重児は、腸内環境が正常な体重で生まれた新生児に比べて乱れやすく、腸内環境の乱れが、低出生体重児の健康上の問題を引き起こす可能性があると考えられています。
腸内環境を整えることで、低出生体重児の健康状態を改善することができる可能性があります。腸内環境を整えるためには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが大切です。善玉菌を増やすためには、乳酸菌やビフィズス菌などの乳酸菌飲料を飲んだり、野菜や果物を多く食べたりするとよいでしょう。また、悪玉菌を減らすためには、脂肪分の多い食事や加工食品を控え、食物繊維を多くとることが大切です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『抗菌ペプチド』
抗菌ペプチドとは、名前から想像できるように「菌に抗(あらが)うペプチド」のことを指します。 抗菌ペプチドは、タンパク質の最小単位であるアミノ酸が約十~数十個連なって形成されており、我々ヒトを含めた哺乳類や植物、昆虫などあらゆる多細胞生物に菌と戦うための生体防御の機能として備わっている物質です。ペニシリンに代表される抗生物質が菌のDNA合成を阻害したり、タンパク質の生成を阻害したりするのに対し、抗菌ペプチドは菌の細胞膜を直接攻撃することで殺菌作用を発揮します。その作用は、抗生物質のような耐性菌を生み出しにくいことから、有用性が着目されています。
Read More
 免疫力アップに関する解説
免疫力アップに関する解説 腸内環境改善と健康
菌体外多糖とは、微生物が自分自身を守るために作り出す糖質の一種です。菌体外多糖は、微生物が菌体表面に分泌・産生する多糖の総称で、環境ストレスなどから自身を保護する役割を有します。その構造は、構成される糖の種類や数、結合様式によって多種多様であり、増粘剤や安定化剤などの食品素材としての利用も為されています。微生物が合成する菌体外多糖は、構造的にホモ多糖(1種類の単糖のみの繰り返し単位で構成)とヘテロ多糖(少なくとも2種類の異なる糖から構成)の2種類に大別されます。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 次亜塩素酸で腸内環境改善!健康効果と摂取方法
次亜塩素酸とは?化学式や特徴を解説!
次亜塩素酸は、化学式HOClで表される化合物です。次亜塩素酸ナトリウムや高度サラシ粉の殺菌作用や漂白作用の主体であり、水溶液は次亜塩素酸水と呼ばれています。次亜塩素酸は、常温常圧で不安定な物質であり、光や熱に弱い性質を持っています。その一方で、次亜塩素酸は強力な殺菌作用と漂白作用を有しており、さまざまな用途に使用されています。
次亜塩素酸の殺菌作用は、細菌やウイルスの細胞壁を破壊することによるものです。次亜塩素酸は、細菌やウイルスの細胞壁に含まれるタンパク質や脂質を酸化させ、細胞壁を破壊します。これにより、細菌やウイルスは死滅します。また、次亜塩素酸は、細菌やウイルスの細胞内のDNAやRNAを損傷させることで、細菌やウイルスの増殖を阻害する働きも持っています。
次亜塩素酸の漂白作用は、色素を酸化することで発揮されます。次亜塩素酸は、色素を酸化させ、無色の物質に変換します。これにより、色素が分解され、漂白効果が得られます。次亜塩素酸は、紙や布の漂白や、水泳プールの水の消毒などに使用されています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康に良い『凍結前未加熱食品』とは?
凍結前未加熱食品とは、調理後に凍結直前まで加熱しない冷凍食品のことです。 えびフライなどのフライ類や、コロッケなどの食品で多用されています。凍結前未加熱食品は、調理後すぐに急速に凍結するため、細菌の増殖が抑えられます。また、食品の鮮度や栄養素が損なわれにくく、おいしさを保つことができます。ただし、凍結前未加熱食品は、調理後に加熱する必要があるため、食べる前に十分に加熱する必要があります。また、凍結前未加熱食品は、生鮮食品よりも賞味期限が長いため、保存期間に注意して食べる必要があります。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境を改善して肝臓を健康に保つ方法
腸内環境は、肝臓の健康と密接に関係しています。腸内には、善玉菌と悪玉菌の2種類の細菌が生息しており、そのバランスが腸内環境を左右します。善玉菌は、腸の蠕動運動を促進し、有害物質の産生を防いでくれます。一方、悪玉菌は、有害物質を産生し、腸の蠕動運動を阻害することで、便秘や下痢の原因となります。
腸内環境が乱れると、悪玉菌が優位になり、有害物質が腸内に蓄積されるようになります。すると、腸から有害物質が肝臓に運ばれ、肝臓に負担がかかります。これが、肝臓の健康を損なう原因の一つと考えられています。
反対に、腸内環境が良好であると、善玉菌が優位になり、有害物質の産生が抑えられます。すると、腸から有害物質が肝臓に運ばれることが少なくなり、肝臓の負担が軽減されます。これが、肝臓の健康を守ることにつながります。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境と筋持久力
腸内環境が筋持久力に与える影響
腸内環境は、健康に大きな影響を与えるとされています。最近の研究では、腸内環境が筋持久力にも影響を与えることがわかってきました。筋持久力は、筋肉が活動する持久的能力のことです。筋持久力を決定する生理学的要因として、筋線維組成と筋肉内の血液循環が考えられます。一般的に遅筋線維が多く、また筋肉内の毛細血管が多いことが筋持久力にとって重要であるとされています。
腸内環境が筋持久力に影響を与えるメカニズムは、まだ完全に解明されていませんが、いくつかの説があります。その1つとして、腸内環境が筋肉のエネルギー代謝に影響を与えるという説があります。腸内細菌は、短鎖脂肪酸と呼ばれる物質を産生します。短鎖脂肪酸は、筋肉のエネルギー源として利用されることが知られています。そのため、腸内環境が良好な人は、筋肉のエネルギー代謝が活性化され、筋持久力が向上すると考えられています。
また、腸内環境が筋肉の炎症に影響を与えるという説もあります。腸内環境が乱れると、腸の粘膜が損傷し、炎症が起こりやすくなります。筋肉も、炎症が起こると筋力が低下することが知られています。そのため、腸内環境が良好な人は、筋肉の炎症が起こりにくく、筋持久力が維持されやすいと考えられています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『微好気性細菌』
微好気性細菌とは、低酸素条件下(5%程度)で発育する細菌のことです。酸素を必要とする好気性細菌と、酸素を必要としない嫌気性細菌の中間に位置する細菌です。大腸菌やサルモネラ菌などは、微好気性細菌の代表例です。微好気性細菌は、腸内環境を改善し、健康に良い影響を与えることが知られています。
微好気性細菌は、腸内環境を整え、健康を維持するために重要な役割を果たしています。微好気性細菌は、腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことで、腸内環境を改善します。また、微好気性細菌は、腸内で短鎖脂肪酸を産生します。短鎖脂肪酸は、腸の蠕動運動を促進し、便秘を予防します。また、短鎖脂肪酸は、腸の粘膜を強化し、腸のバリア機能を高めます。さらに、短鎖脂肪酸は、肝臓の機能を改善し、脂肪肝や動脈硬化を予防します。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『多水分食品』について
多水分食品とは、水産練り製品、食肉加工品、魚の半乾燥品などおおむね50%以上の水分を含み、少なくともAw0.87以上、多くはAw0.95以上の食品のことです。多水分食品は、その水分含有量とアミノ酸やペプチドなどの成分によって、腸内細菌叢に良い影響を与えると考えられています。多水分食品を摂取すると、腸内細菌叢の構成が変化し、有害な菌が減少し、有益な菌が増加するとされています。また、多水分食品には、腸内細菌叢を活性化する成分が含まれているため、腸内環境を整え、健康を維持するのに役立つと考えられています。
Read More
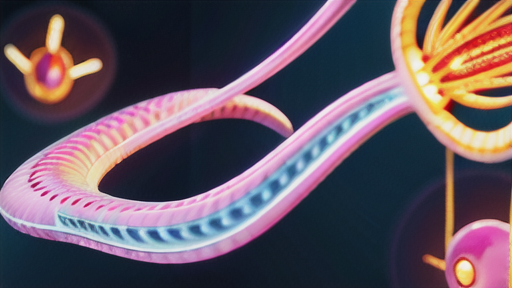 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『放射線殺菌』について
放射線殺菌は、食品の安全性を確保するために用いられる技術であり、食品の品質を低下させることなく、細菌などの微生物を殺菌することができる。海外では、香辛料や乾燥野菜の殺菌、国内では、じゃがいもの発芽抑制などに5~10Kgyの放射線の照射が行われている。
放射線殺菌が消化器系に及ぼす影響については、多くの研究が行われており、放射線殺菌食品を摂取しても、消化器系の機能に悪影響を及ぼすという報告はない。また、放射線殺菌食品を摂取しても、腸内細菌叢に悪影響を及ぼすという報告はない。
放射線殺菌食品は、安全性の高い食品であり、安心して摂取することができる。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善の鍵は『ビタミン』にあり
ビタミンとは、体が成長、生殖、生命維持などのために必須とする微量で生理作用を有する有機成分です。体内で合成系をもたないか、あるいは合成量が必要量に満たないため、食物から摂取する必要があります。脂溶性と水溶性の2つに大別され、ヒトでは前者は4種、後者は9種類があります。
脂溶性ビタミンは、A、D、E、Kの4種類です。これらは、体内に蓄積されるため、過剰摂取に注意が必要です。一方、水溶性ビタミンは、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸、ビタミンCの9種類です。これらは、水に溶けやすく、体内に蓄積されないので、毎日摂取する必要があります。
ビタミンは、健康維持に不可欠な栄養素です。ビタミンが不足すると、様々な健康上の問題を引き起こす可能性があります。例えば、ビタミンAが不足すると、夜盲症や角膜軟化症などの目の病気を引き起こす可能性があります。ビタミンDが不足すると、骨粗鬆症やくる病などの骨の病気を引き起こす可能性があります。ビタミンEが不足すると、貧血や神経障害などの病気を引き起こす可能性があります。ビタミンKが不足すると、出血しやすい状態になる可能性があります。ビタミンB1が不足すると、脚気などの病気を引き起こす可能性があります。ビタミンB2が不足すると、口内炎や皮膚炎などの病気を引き起こす可能性があります。ビタミンB6が不足すると、貧血や神経障害などの病気を引き起こす可能性があります。ビタミンB12が不足すると、貧血や神経障害などの病気を引き起こす可能性があります。ナイアシンが不足すると、ペラグラなどの病気を引き起こす可能性があります。パントテン酸が不足すると、疲労や食欲不振などの病気を引き起こす可能性があります。ビオチンが不足すると、皮膚炎や脱毛などの病気を引き起こす可能性があります。葉酸が不足すると、貧血や神経障害などの病気を引き起こす可能性があります。ビタミンCが不足すると、壊血病などの病気を引き起こす可能性があります。
したがって、健康を維持するためには、ビタミンをバランスよく摂取することが大切です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 健康維持に欠かせない!腸内環境を改善する脂肪細胞の役割
脂肪細胞とは、トリアシルグリセロールを貯留した結合組織細胞のことです。 白色脂肪組織では、大型脂肪滴1個に満たされた白色脂肪細胞が密集しています。白色脂肪細胞は、生体のエネルギー代謝に関連して、短時間内に多量のトリアシルグリセロールを貯蔵したり放出したりします。褐色脂肪組織は、小型脂肪滴を有する褐色脂肪細胞から成り、熱産生を行うことにより、体温維持やエネルギー消費に寄与しています。ヒトでは、脂肪組織の存在部位により、脂肪細胞の数や大きさが異なります。
脂肪組織量は、身体発育に伴って、二つの時期に急速に増大します。第一の時期は、胎生期末期3か月と生後18か月の間であり、脂肪細胞の数が増えます。生後の一年間に体脂肪の絶対量は3~4倍増加します。第二の時期は思春期にあり、脂肪細胞の数の増加が目立ち、大きさも軽度に増します。 この時期の脂肪組織の発育は、男女ともに著しく、特に女性に著明です。ヒトの白色脂肪細胞の半減期は約10年と長いと言われています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境の改善と健康~ポリアミンの健康効果~
ポリアミンとは、世界で初めて顕微鏡で微生物を観察し、「微生物学の父」と呼ばれるリーウエンフックにより、1678年に精液中からリン酸スペルミンの結晶として報告された物質です。 ポリアミンは、原核生物から高等動植物に至るまで、ほぼすべての生物が細胞内に持つ物質であり、その細胞内濃度は数mMから数10mMと高濃度です。生理学的なpH下では正電荷を持つため、核酸、リン酸化タンパク質、リン脂質、ATPなど負電荷をもつ成分と弱く結合し、さまざまな細胞機能を調節することが報告されています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ホモジナイズ』
腸内環境改善と健康『ホモジナイズ』
ホモジナイズとは何か
ホモジナイズとは、機械的あるいは手作業により、食品など、砕いたり、すり潰したり、細分化して、均一な検査試料を調製することです。食品の製造工程において、ホモジナイズは、牛乳や豆乳などの乳製品、マヨネーズなどのソース、ドレッシングなどの調味料、アイスクリームなどのデザートなど、さまざまな食品に適用されています。
ホモジナイズされた食品は、均一な食感と外観を持ち、滑らかで口当たりが良いという特徴があります。また、ホモジナイズによって、食品の栄養素が均一に分散されるため、食品の栄養価を向上させることができます。
しかし、近年では、ホモジナイズされた食品が健康に悪影響を与える可能性があるという指摘もされています。ホモジナイズされた食品には、未ホモジナイズの食品よりもトランス脂肪酸が多く含まれていることが報告されており、トランス脂肪酸は、心臓病や肥満のリスクを高める可能性があると言われています。
また、ホモジナイズされた食品は、腸内環境を悪化させる可能性もあると言われています。ホモジナイズされた食品に含まれる小さな脂肪球は、腸内細菌によって分解されにくい性質を持っており、腸内環境のバランスを崩す可能性があると言われているのです。
ホモジナイズされた食品が健康に与える影響については、まだ研究が進んでおらず、結論は出ていません。しかし、ホモジナイズされた食品を過剰に摂取することは、健康に悪影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康:酸膜酵母について学ぼう
酸膜酵母が腸内環境に与える影響
酸膜酵母は、腸内環境を改善する効果を持っていることが知られています。腸内環境とは、腸の中に存在する細菌のバランスのことです。善玉菌と悪玉菌のバランスが取れている状態が健康的な腸内環境と言われています。酸膜酵母は、善玉菌を増やすことで腸内環境を改善する効果があります。善玉菌が増えることで、腸の蠕動運動が活発になり、便通が良くなります。また、善玉菌は、悪玉菌の増殖を抑え、有害物質を分解する働きがあります。そのため、酸膜酵母を摂取することで、腸内環境が改善され、健康維持に役立つと考えられています。
Read More
 腸内環境に関する解説
腸内環境に関する解説 腸内環境改善で防衛体力アップ!健康な腸のためのヒント
腸内環境とは、腸の中に暮らす細菌のバランスのことです。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の菌が住んでいます。善玉菌は、腸内を酸性にして悪玉菌の増殖を抑え、消化や吸収を助ける働きがあります。悪玉菌は、腸内をアルカリ性にして善玉菌の増殖を抑え、有害物質を産生します。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらが増加するかによってどちらかの味方につきます。
腸内環境は、健康に大きな影響を与えます。腸内環境が良好な人は、免疫力が高く、感染症にかかりにくい傾向にあります。また、腸内環境が良好な人は、肥満や糖尿病になりにくい傾向にあります。逆に、腸内環境が悪い人は、免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなります。また、腸内環境が悪い人は、肥満や糖尿病になりやすい傾向にあります。
腸内環境を改善するには、バランスの良い食事をとることが大切です。善玉菌が増える食品を積極的に摂り、悪玉菌が増える食品を控えることで、腸内環境を改善することができます。善玉菌を増やす食品には、ヨーグルト、納豆、味噌、キムチなどの発酵食品や、食物繊維が豊富な野菜や果物があります。悪玉菌を増やす食品には、肉類、魚介類、乳製品、卵などの動物性食品や、砂糖や油を多く含む加工食品があります。
また、適度な運動をすることも腸内環境の改善に効果的です。運動をすると、腸の蠕動運動が活発になり、便通がよくなります。便通がよくなると、腸内に有害物質が溜まりにくくなり、腸内環境が改善されます。
さらに、十分な睡眠をとることも腸内環境の改善に効果的です。睡眠中は、腸の蠕動運動が活発になり、便通がよくなります。また、睡眠中は、善玉菌が増殖しやすいと言われています。
Read More
 アレルギーに関する解説
アレルギーに関する解説 腸内環境を改善して健康に!アレルゲンを撃退しよう
腸内環境とアレルゲンの関係
腸内環境の状態が、アレルゲンに対する免疫反応に影響を与えることが近年明らかになってきました。腸内環境が乱れると、腸内細菌のバランスが崩れて、アレルギー反応を起こしやすい状態になります。腸内環境改善のためには、食生活に気をつけたり、プロバイオティクスやプレバイオティクスを摂取したり、適度に運動をしたりすることが大切です。また、ストレスをためないようにすることも、腸内環境改善につながります。
Read More
 腸内環境に関する解説
腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康〜水銀の危険性を知る〜
水銀とは?
水銀は、元素記号Hg、原子番号80、原子量200.59の12(2B)族元素です。常温で唯一の液体の金属で、融点は-38.86℃、沸点は356.72℃です。水銀は気化しやすく、水銀蒸気を長時間吸うと酵素などの活性タンパク質を阻害し、神経が冒されることがあります。水銀塩は、種々の有機合成の触媒として用いられ、医薬品、殺菌剤、農薬の製造に用いられます。水銀には広い用途がありますが、有機水銀は特に毒性が強く、公害問題化しています。
Read More
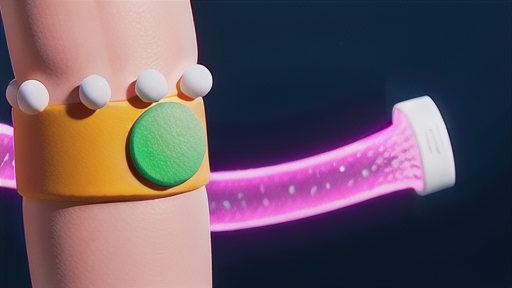 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 健康のカギ:腸内常在菌
腸内には、およそ1000種類、約100兆個の細菌が存在し、複雑な微生物生態系が形成されています。これは、いわゆる腸内フローラと呼ばれ、ヒトの健康に大きな影響を及ぼしていることが知られています。これらの腸内フローラを構成する細菌は、病原菌などの一過的に腸内を通過する細菌と区別して、腸内常在菌と呼ばれます。腸内常在菌は、出生すると間もなく母親や周囲の環境から伝播し、年齢と共にその種類や数が変化していきますが、成人ではそれらは概ね安定しており、その間はヒトとの良好な"共生関係"が築かれていると考えられます。
一方で、病気にかかると腸内常在菌の構成が破綻する場合があることも明らかになってきました。したがって、腸内常在菌との良好な"共生関係"を維持することが健康にとって重要であると言えるでしょう。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康 ~DNA損傷を防いで癌を予防しよう~
腸内環境とDNA損傷の関係
腸内環境は、腸内細菌叢によって構成され、腸内の細菌叢のバランスが崩れると、腸内環境が悪化します。腸内環境が悪化すると、腸内細菌が産生する発がん物質や変異原物質が増加し、DNA損傷を引き起こすことがわかっています。DNA損傷は、細胞の機能を低下させたり、がん化を引き起こしたりする可能性があります。
腸内環境が悪化すると、腸内細菌が産生する発がん物質や変異原物質が増加します。発がん物質とは、がんを引き起こす物質であり、変異原物質とは、DNAを損傷させる物質です。これらの物質は、腸内細菌が食物を分解する過程で産生されます。腸内環境が悪化すると、これらの物質が腸内から吸収されて全身に運ばれ、DNA損傷を引き起こします。
DNA損傷は、細胞の機能を低下させたり、がん化を引き起こしたりする可能性があります。DNAは、細胞の遺伝情報を担っており、DNA損傷によって遺伝情報が破壊されると、細胞の機能が低下したり、がん化したりする可能性があります。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『骨密度』について
腸内環境と骨密度の関係
腸内環境は、骨密度に影響を及ぼすことが知られています。腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸(SCFA)は、骨の形成を促進する効果があることがわかっています。また、腸内細菌が産生するビタミンKは、骨のカルシウム沈着を促進する効果があります。さらに、腸内細菌が産生するセロトニンは、骨の形成を促進する効果があることがわかっています。
逆に、腸内環境が悪化すると、骨密度が低下する可能性があります。腸内細菌が産生する有害物質は、骨の形成を阻害する効果があることがわかっています。また、腸内細菌が産生する炎症性サイトカインは、骨の形成を阻害する効果があることがわかっています。さらに、腸内細菌が産生する活性酸素は、骨の形成を阻害する効果があることがわかっています。
これらのことから、腸内環境を改善することは、骨密度を高めるために重要であると考えられます。腸内環境を改善するために、食物繊維を多く含む食品を摂取したり、運動をしたり、ストレスを軽減したりすることが効果的です。
Read More
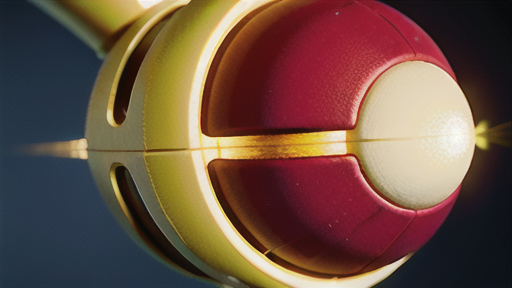 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ディフィシル菌関連下痢症』
ディフィシル菌関連下痢症とは、Clostridioides difficile(クロストリディオイデス ディフィシル;ディフィシル菌)によって引き起こされる下痢症です。ディフィシル菌は酸素に弱い細菌ですが、芽胞という耐性状態を形成することによって、酸素や乾燥などの通常では生存できない条件下でも長期間生き延びることができます。そのため、芽胞で汚染された環境(例えば、トイレの便座やドアノブなど)から手指などを介して、口から体内に取り込まれます。Healthy personでは、ディフィシル菌が体内に入ってきても、腸内フローラや免疫のはたらきによって発症しない場合がほとんどです。しかし、これらの防御機能が抗菌薬の服用や免疫機能の低下などによって乱れると、腸内でディフィシル菌が増殖して毒素を産生し、下痢の発症に至ります。ディフィシル菌関連下痢症は、高齢者や入院患者での発生率が高くなっており、症状が治まっても再発しやすいことも知られています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ビフィズス菌増殖促進因子』について
ビフィズス菌増殖促進因子とは、ビフィズス菌の増殖を促進する物質のことです。 ビフィズス菌は、人間の腸内に生息する善玉菌の一種であり、健康を維持するために重要な役割を果たしています。ビフィズス菌を増やすことで、腸内の環境が改善され、健康の増進につながると考えられています。
ビフィズス菌増殖促進因子は、スイスチーズのスターターとして古くから利用されてきたプロピオン酸菌(Propionibacterium freudenreichii)が産生します。プロピオン酸菌は、牛乳を発酵させてチーズやヨーグルトなどの乳製品を作る際に使用される細菌の一種です。プロピオン酸菌が産生するビフィズス菌増殖促進因子は、ビフィズス菌の増殖に特異性を持っており、他の腸内細菌の増殖を促進することはありません。
ビフィズス菌増殖促進因子は、ビフィズス菌の増殖を促進することで、腸内の環境を改善し、健康の増進につながることが期待されています。ビフィズス菌を増やすことで、腸の蠕動運動が促進され、便秘や下痢などの症状を改善することが期待できます。また、ビフィズス菌が産生する酢酸や乳酸などの有機酸は、腸内のpHを酸性にし、悪玉菌の増殖を抑える効果があります。さらに、ビフィズス菌は、ビタミンB群やビタミンKなどの栄養素を産生し、腸の粘膜を強化する効果があります。
Read More









