 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 健康
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説
VBN(揮発性塩基窒素)とは、食品の腐敗を測定する尺度の一つです。 食品中に含まれるタンパク質、アミノ酸などの窒素含有成分が、微生物の働きによって分解され、アンモニアやトリメチルアミンなどの腐敗臭の原因となる揮発性アミンに分解されます。この量がVBNで、一般的に30mg%を超えると初期腐敗、50mg%以上を完全な腐敗の目安にしています。VBNは、食品の鮮度や品質を評価するために使用されます。VBNが高い食品は、腐敗が進んでおり、食べると食中毒を起こす可能性があります。そのため、食品を購入する際には、VBNの値を確認することが大切です。
Read More
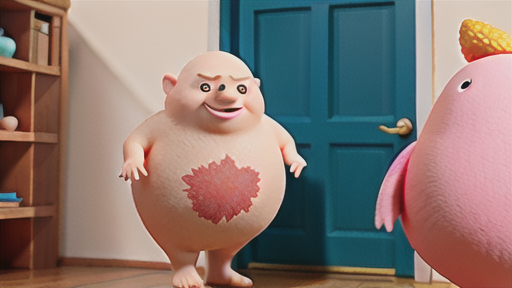 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境と健康改善
腸内細菌と健康
人間の腸には、100兆個もの細菌が生息しています。これらの細菌は、腸内フローラと呼ばれ、私たちの健康に重要な役割を果たしています。腸内フローラは、食べ物を消化吸収したり、有害な物質を分解したり、免疫機能をサポートしたりしています。腸内フローラのバランスが崩れると、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。
例えば、腸内フローラの乱れが肥満や糖尿病、大腸がんのリスクを高めることがわかっています。また、腸内フローラの乱れは、うつ病や不安障害など、精神疾患にも関連していると考えられています。腸内フローラのバランスを保つためには、食生活や生活習慣に気を配ることが大切です。食物繊維や発酵食品を積極的に摂ったり、適度な運動を心がけたりすることで、腸内フローラのバランスを整えることができます。
また、ストレスをためないようにすることも大切です。ストレスは、腸内フローラのバランスを崩す原因の一つになります。腸内フローラのバランスが崩れると、様々な健康問題を引き起こす可能性があるため、腸内フローラのバランスを保つことは、健康維持のために非常に重要です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『アドレナリン』について
アドレナリンは、ストレスを感じたときに副腎から分泌されるホルモンです。アドレナリンは、心拍数を上げたり、血圧を上昇させたり、気管支を拡張させたりするなど、体の様々な機能を活性化させます。このアドレナリンの分泌が過剰になると、ストレスを感じやすくなったり、うつ病を発症したりするリスクが高まります。
腸内細菌は、アドレナリンの分泌を調節する役割を果たしています。腸内細菌の中には、アドレナリンの分泌を抑制する物質を産生するものがあります。このような腸内細菌が優勢になると、アドレナリンの分泌が抑制され、ストレスを感じにくくなります。逆に、アドレナリンの分泌を促進する物質を産生する腸内細菌が優勢になると、アドレナリンの分泌が促進され、ストレスを感じやすくなります。
そのため、腸内細菌のバランスを整えることが、ストレスを軽減し、うつ病の発症リスクを下げることにつながると考えられています。
Read More
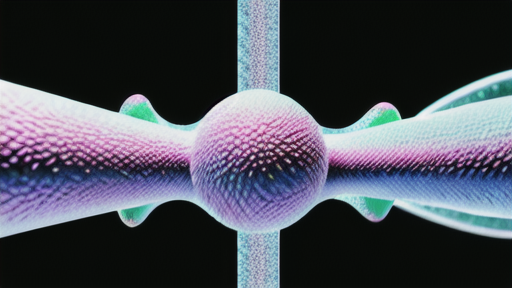 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『界面活性剤』の真実
腸内細菌と界面活性剤の関係とは
界面活性剤は、水と油などの異なる二つの物質の界面で互いの表面張力を弱め、親和性を高めるような働きをする物質です。界面活性剤は、石鹸や洗剤の主成分として使用されています。近年、腸内細菌と界面活性剤の関係が注目されるようになりました。界面活性剤は、腸内細菌の増殖を抑制したり、腸内細菌の構成を変えることで、腸内環境に影響を与える可能性があります。
界面活性剤は、水と油などの異なる二つの物質の界面で互いの表面張力を弱め、親和性を高めるような働きをする物質です。界面活性剤は、石鹸や洗剤の主成分として使用されています。近年、腸内細菌と界面活性剤の関係が注目されるようになりました。界面活性剤は、腸内細菌の増殖を抑制したり、腸内細菌の構成を変えることで、腸内環境に影響を与える可能性があります。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境改善と健康『塩酸イリノテカン』
塩酸イリノテカンは、抗腫瘍効果をもつカンプトテシンの誘導体です。塩酸イリノテカンは、Ⅰ型DNAトポイソメラーゼの阻害という作用機序で、既存の抗がん剤とは各種マウス腫瘍に対して交叉耐性を示さず、広い抗腫瘍スペクトラムを持つことが知られています。この物質は、主に肝臓でカルボキシエステラーゼにより加水分解を受けて、活性本体であるSN-38を生成するプロドラッグです。塩酸イリノテカンは、国内では、肺がん、大腸がん、婦人科がんなど11がん種の適用で承認されています。海外でも100か国以上で承認され、販売されています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 美肌、免疫力、健康腸内環境!寒天パワーの可能性[徹底解説]
寒天とは?
寒天とは、テングサ(天草)、オゴノリなどの紅藻類の粘液質を凍結・乾燥したもので、ゼリーや羊羹などの製菓材料としてよく利用されます。その性状から、微生物培養のため培地の基質としても利用されています。
寒天を食べるとどんな効果があるの?
寒天には、整腸作用、免疫機能向上、コレステロール値低下、ダイエット効果など、様々な効果が期待されています。
整腸作用
寒天は、水溶性食物繊維の一種で、腸内細菌ののエサとなり、腸内環境を整える効果があります。また、寒天には保水性があり、便を柔らかくして排便を促す効果もあります。
免疫機能向上
寒天には、免疫細胞の活性化を促す効果があることがわかっています。免疫細胞が活性化されると、体外から侵入した細菌やウイルスを排除する力が強まり、風邪や感染症にかかりにくくなります。
コレステロール値低下
寒天には、コレステロールを吸着して体外に排出する効果があります。コレステロール値が高い人は、寒天を積極的に摂ることで、コレステロール値を下げることができます。
ダイエット効果
寒天は、低カロリーで満腹感を得られるため、ダイエットにも効果的です。寒天は、水分を吸収して膨らむ性質があるため、少量でも満腹感を得ることができます。また、寒天には、糖質や脂質の吸収を抑える効果もあります。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内細菌と腸上皮細胞のクロストークで健康に!
クロストークとは、種々の情報伝達系の間の相互作用のことです。種々の情報伝達系の伝達分子(リガンド)や受容体(レセプター)のあいだに共通因子が存在すれば、情報伝達の交差作用、相互作用が細胞レベル、分子レベルで生まれます。腸管の表面は単層の上皮細胞で覆われており、腸上皮細胞は腸内細菌からの刺激を最前線で受け取る細胞であると考えられます。以前より、無菌動物と通常動物の比較研究などから、腸内細菌は腸上皮細胞の機能に影響を与えていることが明らかになっていました。近年、両者の間のリガンドや受容体の関係を分子レベルで示す報告が増え、クロストークの解明が進んでいます。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 Полилизинで体の内側から健康になる!
ポリリジンとは、微生物による発酵生産物であり、厚生労働省告示の既存添加物に記載されている保存料の一種です。グラム陽性菌(セレウス菌等)、グラム陰性菌(大腸菌等)、酵母など広範囲の微生物、特に食中毒原因菌に対しても、増殖抑制効果を発揮することが知られています。また、腸内環境改善に効果があることが報告されており、腸内環境を整えることで、健康維持に役立つと期待されています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『抗菌ペプチド』
抗菌ペプチドとは、名前から想像できるように「菌に抗(あらが)うペプチド」のことを指します。 抗菌ペプチドは、タンパク質の最小単位であるアミノ酸が約十~数十個連なって形成されており、我々ヒトを含めた哺乳類や植物、昆虫などあらゆる多細胞生物に菌と戦うための生体防御の機能として備わっている物質です。ペニシリンに代表される抗生物質が菌のDNA合成を阻害したり、タンパク質の生成を阻害したりするのに対し、抗菌ペプチドは菌の細胞膜を直接攻撃することで殺菌作用を発揮します。その作用は、抗生物質のような耐性菌を生み出しにくいことから、有用性が着目されています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『食育』
腸内環境とは?
腸内環境とは、腸内細菌の構成や働き具合のことです。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の細菌が生息しています。善玉菌は、腸の蠕動運動を促進したり、ビタミンを合成したり、免疫力を高めたりする働きがあります。悪玉菌は、毒素を産生したり、腸の炎症を引き起こしたりする働きがあります。日和見菌は、善玉菌が多いときは善玉菌のように働き、悪玉菌が多いときは悪玉菌のように働く細菌です。腸内環境が良い状態とは、善玉菌が優勢で、悪玉菌が劣勢な状態をいいます。腸内環境が良いと、便通が良くなり、肌荒れやアレルギーなどの症状が改善され、免疫力が高まり、病気を予防することができます。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境と健康に与えるアッカーマンシア・ムシニフィラ
アッカーマンシア・ムシニフィラ(AkkermansiamuciniphilaはVerrucomicrobia門に属するグラム陰性の偏性嫌気性細菌である。2004年にDerrienらによって健康なヒトの糞便から分離され、新菌属Akkermansiaとして提唱された。)アッカーマンシア・ムシニフィラは、健康なヒトの腸内フローラに生息する細菌であり、腸内環境の改善や健康維持に重要な役割を果たしていると考えられています。
アッカーマンシア・ムシニフィラは、腸内粘膜のムチン層を分解して利用することができます。ムチン層は、腸内を保護する粘液層ですが、アッカーマンシア・ムシニフィラがムチン層を分解することで、腸内の炎症を抑制することができると考えられています。
また、アッカーマンシア・ムシニフィラは、腸内での短鎖脂肪酸の産生にも関与しています。短鎖脂肪酸は、腸内環境を整え、腸の機能を改善する効果があると考えられています。
さらに、アッカーマンシア・ムシニフィラは、免疫システムの制御にも関与していると考えられています。アッカーマンシア・ムシニフィラが腸内に存在することで、腸内免疫細胞の活性化を抑制し、炎症反応を抑制することができると考えられています。
このように、アッカーマンシア・ムシニフィラは、腸内環境の改善や健康維持に重要な役割を果たしていると考えられています。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境改善でがん撃退!腸内環境改善でがん幹細胞を撃退!
がんの大もとの細胞である「がん幹細胞」は、がんの形成や成長、転移や再発といったさまざまな悪性化を引き起こす役割を担っています。 研究の結果、がん幹細胞は腸内細菌叢の変化と密接な関係があるとされています。腸内細菌叢とは、腸内に生息する微生物の集団のことです。
善玉菌と呼ばれる腸内細菌は、免疫システムを強化したり、有害物質を分解したり、ビタミンを産生したりするなど、人体に有益な働きをします。一方、悪玉菌は感染症を引き起こしたり、毒素を産生したり、炎症を悪化させたりするなど、人体に有害な働きをします。
Read More
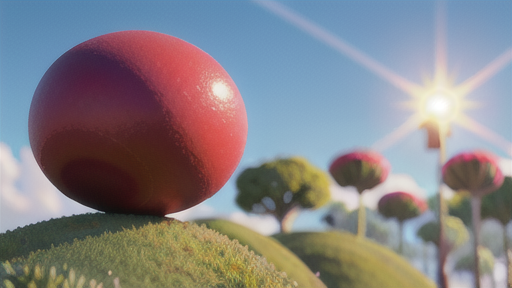 腸内環境に関する解説
腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康『ブドウ球菌』
ブドウ球菌とは?
ブドウ球菌とは、ブドウ球菌属に属するグラム陽性球菌の総称です。その名の通り、光学顕微鏡で観察すると「ブドウの房」のように見えることから命名されました。ブドウ球菌は、ヒトの表皮や粘膜に常在している正常細菌ですが、一部のブドウ球菌は感染症を引き起こすことがあります。
ブドウ球菌の中でも特に知られているのが、表皮ブドウ球菌と黄色ブドウ球菌です。表皮ブドウ球菌は、ヒトの表皮に常在しており、皮膚の健康を維持する役割を果たしています。しかし、免疫力が低下しているときなどに感染症を引き起こすことがあります。黄色ブドウ球菌は、食中毒の原因菌として知られています。また、皮膚感染症や肺炎などの感染症を引き起こすこともあります。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境を整えて健康に!便秘の基礎知識と改善方法
便秘とは、排便回数が減る、便が硬くなり排便に困難を感じる、腹部の不快感や残便感を覚える、といった状態を指します。 便秘の医学的な定義は無く、「便秘である」と感じる基準は人それぞれです。排便回数が減ったことを便秘と捉える人もいれば、毎日排便があってもすっきりしないので便秘であると感じる人もいます。
便秘は、その原因によって「器質性便秘」と「機能性便秘」に大別されます。「器質性便秘」とは、病気が原因で腸に狭い部分ができるなど、構造上の異常により便通が妨げられて起こる便秘です。一方、「機能性便秘」には、腸の動きが弱く便を十分押し出せなくなる「弛緩性便秘」、直腸の反応が鈍くなり便意を感じにくくなる「直腸性便秘」、腸の動きが活発になりすぎて便が通りにくくなる「けいれん性便秘」の3種類へとさらに分けられます。男性よりも女性の方が便秘になりやすく、便秘である女性の数は男性の約2倍といわれています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康の秘訣
腸内細菌の種類と働き
人間の腸内には、1000種類以上の腸内細菌が生息しています。これらの腸内細菌は、食物を分解してエネルギーを産生したり、ビタミンを合成したり、免疫機能をサポートしたりと、人体にさまざまな恩恵をもたらしています。
腸内細菌の種類は、その人の食生活や生活習慣によって異なります。例えば、肉食の人は、野菜を多く食べる人に比べて、腸内細菌の種類が多様で、腸内環境が良好であることが知られています。また、運動をしたり、ストレスをためないようにしたりすることも、腸内環境を整えるのに効果的です。
腸内細菌の働きは、その種類によって異なります。例えば、ビフィズス菌は、乳酸を産生し、腸内環境を酸性に保つことで、有害な細菌の増殖を防いでいます。また、乳酸菌は、タンパク質や糖質を分解してエネルギーを産生するほか、ビタミンを合成しています。大腸菌は、腸内の水分を吸収して便を形成しています。
腸内細菌は、人体にとってなくてはならない存在です。腸内細菌の種類や働きを理解することで、腸内環境を整え、健康を維持することができます。
Read More
 検査に関する解説
検査に関する解説 腸内環境を改善して健康に→ フローサイコメトリー法で解き明かす腸内細菌
腸内環境と健康の関係とは?
腸内環境は、私たちの健康に大きな影響を与えています。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌という3種類の菌が住んでおり、これらがバランスよく保たれていることが理想的です。善玉菌は、腸内を健康に保ち、悪玉菌の増殖を抑える働きがあります。悪玉菌は、毒素を産生し、腸内環境を悪化させます。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらの勢力が強い方に味方する菌です。
腸内環境が乱れると、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。例えば、便秘、下痢、腹痛、ガスが溜まる、消化不良、口臭、肌荒れ、アレルギー、肥満、糖尿病、心臓病、がんのリスク上昇などが挙げられます。
腸内環境を整えるためには、バランスの良い食生活、適度な運動、ストレスをためないことが大切です。また、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌を積極的に摂ることも効果的です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『トリプトファン(Trp)』
トリプトファンとは?
トリプトファンは、糖原性・ケト原性のアミノ酸の一種であり、必須アミノ酸に分類されます。必須アミノ酸とは、人間の体内では合成できないため、食事から摂取する必要があるアミノ酸のことです。トリプトファンは、タンパク質を構成する20種類のアミノ酸のうち、8番目に多いアミノ酸です。トリプトファンは、インドール核をもつ芳香族のアミノ酸で、わずかに苦味があり、水に溶けにくいという特徴があります。また、トリプトファンは、セロトニン、メラトニン、ナイアシンなどの生合成の前駆体として重要な役割を果たしています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で健康に 過敏性腸症候群の症状を和らげる
過敏性腸症候群(IBS)とは、腹痛や腹部膨満感などの腹部症状と、下痢あるいは便秘などの便通異常を主体とする症状が、潰瘍やがんなどが認められないにもかかわらず持続する消化管の機能的疾患です。 IBSは消化器官の機能障害であり、炎症や損傷はありません。
IBSには、便秘型、下痢型、混合型、分類不能型の4つのタイプがあります。便秘型は、下痢がほとんどなく、便秘が主な症状です。下痢型は、便秘がほとんどなく、下痢が主な症状です。混合型は、便秘と下痢を両方経験します。分類不能型は、便秘型、下痢型、混合型のいずれにも当てはまらない症状を経験します。
IBSの症状は、人によって異なります。一般的な症状には、次のものがあります。
・腹痛
・腹部膨満感
・下痢
・便秘
・粘液便
・ガス
・吐き気
・嘔吐
・疲労感
・集中力の低下
・睡眠障害
・不安
・うつ病
IBSの原因は完全には解明されていませんが、いくつかの要因が関与していると考えられています。これらの要因には、次のものがあります。
・腸内環境の乱れ
・運動不足
・ストレス
・食事
・遺伝
IBSは治療法のない慢性疾患ですが、症状をコントロールすることは可能です。治療法としては、次のものがあります。
・食事療法
・運動
・ストレス管理
・薬物療法
・腹痛
・腹部膨満感
・下痢
・便秘
・粘液便
・ガス
・吐き気
・嘔吐
・疲労感
・集中力の低下
・睡眠障害
・不安
・うつ病
IBSの原因は完全には解明されていませんが、いくつかの要因が関与していると考えられています。これらの要因には、次のものがあります。
・腸内環境の乱れ
・運動不足
・ストレス
・食事
・遺伝
IBSは治療法のない慢性疾患ですが、症状をコントロールすることは可能です。治療法としては、次のものがあります。
・食事療法
・運動
・ストレス管理
・薬物療法
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『プラセボ効果』
プラセボ効果とは、偽薬を服用したことにより症状が改善する現象を指します。これは、薬を服用したという思い込みが、脳内の神経伝達物質の分泌を促し、症状を緩和することが原因と考えられています。例えば、痛み止めを服用した際に、実際には痛み止め効果のない偽薬を飲んだにもかかわらず、痛みが軽減することがあります。これは、偽薬を飲んだことで、脳が痛み止めを服用したと認識し、痛みを緩和する物質を分泌したためです。プラセボ効果は、さまざまな症状に効果があることが知られており、痛み、吐き気、うつ病などの症状を改善することができる可能性があります。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康「制御性T細胞」について
腸内環境と免疫システムの関係
腸内環境は、免疫システムと密接な関係があり、腸内環境の乱れは、免疫システムの機能低下につながる。腸内には、善玉菌と悪玉菌が共存しており、善玉菌は、悪玉菌の増殖を抑え、腸内環境のバランスを保つ役割を担っている。しかし、ストレスや食生活の乱れなどによって腸内環境が乱れると、善玉菌が減少して悪玉菌が増加し、免疫システムの機能が低下してしまう。
免疫システムが低下すると、感染症にかかりやすくなったり、アレルギー反応が出やすくなったりする。また、腸内環境の乱れは、肥満や糖尿病、アトピー性皮膚炎などの生活習慣病の発症にも関連している。そのため、腸内環境を整えることは、免疫システムの機能を維持し、生活習慣病の予防や改善につながる。
腸内環境を整えるためには、善玉菌を増やすことが重要である。善玉菌を増やすためには、食物繊維を多く含む食品や、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌を含む発酵食品を積極的に摂取することが効果的である。また、ストレスを軽減したり、適度な運動をしたりすることも、腸内環境を整えるのに役立つ。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康 ~DNA損傷を防いで癌を予防しよう~
腸内環境とDNA損傷の関係
腸内環境は、腸内細菌叢によって構成され、腸内の細菌叢のバランスが崩れると、腸内環境が悪化します。腸内環境が悪化すると、腸内細菌が産生する発がん物質や変異原物質が増加し、DNA損傷を引き起こすことがわかっています。DNA損傷は、細胞の機能を低下させたり、がん化を引き起こしたりする可能性があります。
腸内環境が悪化すると、腸内細菌が産生する発がん物質や変異原物質が増加します。発がん物質とは、がんを引き起こす物質であり、変異原物質とは、DNAを損傷させる物質です。これらの物質は、腸内細菌が食物を分解する過程で産生されます。腸内環境が悪化すると、これらの物質が腸内から吸収されて全身に運ばれ、DNA損傷を引き起こします。
DNA損傷は、細胞の機能を低下させたり、がん化を引き起こしたりする可能性があります。DNAは、細胞の遺伝情報を担っており、DNA損傷によって遺伝情報が破壊されると、細胞の機能が低下したり、がん化したりする可能性があります。
Read More
 腸内環境に関する解説
腸内環境に関する解説 リボソームRNAで紐解く腸内環境と健康
リボソームRNAとは、生物の細胞内でタンパク質を合成する作業を行うリボソームを構成するRNAのことです。 リボソームは、RNAとタンパク質が複合体を成す特殊な構造をしており、その構成RNAがリボソームRNA(rRNA)と呼ばれます。タンパク質合成は生物に欠かせない生理機能であり、それに関係するrRNAは進化の過程で塩基配列が高く保存されています。この特徴は生物種間の進化の違いを検出するのに適していることから、さまざまな生物種においてrRNA塩基配列の解読が進められてきました。
Read More
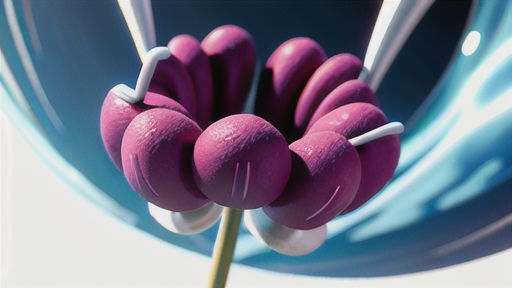 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 健康のための腸内環境改善と『胞子形成亜硫酸還元嫌気性菌』
クロストリジアは、腸内環境改善に重要な役割を果たす胞子形成亜硫酸還元嫌気性菌の一種であり、胞子を形成し亜硫酸を還元して硫化水素を生成する嫌気性細菌である。腸内環境を改善することで、免疫機能を向上させ、感染症やアレルギーに対する抵抗力を高めることができる。また、クロストリジアは腸内における有害物質の分解にも貢献し、腸内環境を清潔に保つのに役立つ。さらに、クロストリジアは短鎖脂肪酸を産生するが、この短鎖脂肪酸は腸内環境を改善し、大腸がんや心疾患のリスクを低減することが示されている。
しかし、クロストリジアは過剰に増殖すると、有害物質を産生して腸内環境を悪化させることもあるため、適切な量を摂取することが重要である。クロストリジアはヨーグルトやキムチなどの発酵食品に多く含まれているため、発酵食品を積極的に摂取することで、腸内環境の改善を図ることができる。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善のカギ、細胞壁多糖とは?
細胞壁多糖は、乳酸菌やビフィズス菌などのグラム陽性細菌の細胞壁を構成する糖鎖のことです。糖鎖とは、グルコース、ガラクトース、マンノース、あるいはラムノースなどの単糖、およびこれらの単糖がアセチル化されたものが鎖状に繋がったものを言います。細胞壁多糖は、細胞の表面にあるため、他の細菌やウイルスなどの病原体から細胞を守る役割をしています。また、細胞壁多糖は、細胞同士の接着や、宿主(ヒト)の粘膜細胞への付着に関与していると考えられています。
細胞壁多糖は、菌株ごとに構造が異なり、その構造によって、細胞の性質も異なってきます。例えば、細胞壁多糖が長い菌株は、細胞壁多糖が短い菌株よりも、他の細菌やウイルスなどの病原体から細胞を守る能力が高いことが知られています。また、細胞壁多糖が長い菌株は、宿主(ヒト)の粘膜細胞への付着能力も高いことが知られています。
細胞壁多糖は、腸内環境の改善に役立つことが知られています。細胞壁多糖は、腸内細菌の増殖を促進したり、腸内細菌の有害物質の産生を抑制したりする働きがあります。また、細胞壁多糖は、腸の粘膜細胞の修復を促進したり、腸の免疫機能を高めたりする働きがあることも知られています。
Read More









