 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説
病原大腸菌とは何か?
病原大腸菌とは下痢の原因となる大腸菌の総称です。大腸菌はもともと、人の腸内に常在する菌であり、ビタミン合成や栄養素の吸収、病原菌の侵入を防ぐなど、人の健康維持に役立っています。しかし、病原大腸菌は毒素を産生したり、腸管壁に侵入したりすることで、下痢や腹痛などの症状を引き起こします。
病原大腸菌は5つのタイプに分けられます。腸管出血性大腸菌(EHEC)、毒素原性大腸菌(ETEC)、組織侵入性大腸菌(EIEC)、病原血清型大腸菌(EPEC)、腸管付着性大腸菌(EAEC)です。これらのタイプは、下痢の症状や、毒素を産生するメカニズムが異なります。
病原大腸菌は、食中毒の原因となる菌としても知られており、食品を介して感染することが多いです。特に、十分に加熱されていない肉や卵、未殺菌の牛乳や果汁、生野菜や果物は、病原大腸菌に汚染されている可能性が高いため、注意が必要です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)』について
腸内環境改善の重要性
私たちの腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の菌が住んでいます。善玉菌は、有害物質を分解したり、免疫機能を強化したりする働きがあります。悪玉菌は、有害物質を産生したり、感染症を引き起こしたりする働きがあります。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらが優勢になるかによって働きが変わります。
腸内環境が悪化すると、悪玉菌が増えて善玉菌が減少し、日和見菌が悪玉菌に味方するようになります。その結果、腸内で有害物質が産生され、免疫機能が低下して感染症にかかりやすくなります。また、腸内環境の悪化は、肥満、糖尿病、高血圧、動脈硬化などの生活習慣病のリスクを高めることもあります。
腸内環境を改善するためには、善玉菌を増やすことが大切です。善玉菌を増やすためには、食物繊維やオリゴ糖を多く含む食品を食べる、乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスを摂取する、適度な運動をするなどの方法があります。また、ストレスを溜めないことも腸内環境改善に効果的です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 結合水とは?腸内環境改善に重要な食品中の水分
結合水とは?
食品中の水分には、食品成分などと結合して存在する結合水と、食品成分と結合せず、比較的簡単に蒸発したり、食品微生物が生育に利用したりできる自由水の2種類があります。結合水は、食品の栄養価や食感、保存性などに影響を与える重要な成分です。結合水が豊富な食品は、自由水の多い食品よりも栄養価が高く、食感も良く、保存性も高い傾向にあります。
結合水は、食品中の糖質、タンパク質、脂質などの成分と結合して存在しています。結合水の量が多いほど、食品の水分活性が低くなり、食品微生物が生育しにくくなります。このため、結合水は食品の保存性を高める重要な役割を果たしています。
Read More
 免疫力アップに関する解説
免疫力アップに関する解説 腸内環境改善と健康『強化培養』
強化培養とは、微生物の能力を高める育種法のひとつです。少ない負荷から始めて徐々に負荷を増やし、より大きな負荷に耐えられるものを選抜していきます。
たとえば生きて腸に届く乳酸菌を「強化培養」するとしましょう。飲用した乳酸菌は、強い殺菌力がある胃液、胆汁にさらされるため、これらの関門に耐える能力を高める必要があります。そこでまず、塩酸などを含む胃液に似せた溶液(人工胃液)に乳酸菌を入れて培養し、生き残った乳酸菌を選びだします。続いて、胆汁酸などを含む腸液に似せた溶液(人工腸液)に乳酸菌を入れて培養し、生き残った乳酸菌を選び出します。この二段階の選抜を通して、生きて腸に届く乳酸菌が「強化培養」されます。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 再生不良性貧血と腸内環境
再生不良性貧血とは、骨髄中の多能性幹細胞が障害されるため、骨髄の低形成を来し、末梢血での赤血球、白血球や血小板の減少などいわゆる汎血球減少症を呈する疾患です。顆粒球数、血小板数及び網赤血球数により重症度分類が行われます。重症では、顆粒球が500個/μL未満、血小板数が20,000個/μL未満、及び網赤血球が20,000個/μL未満の2または3項目を満たすものをいいます。中等症は顆粒球が1,000個/μL未満、血小板数が50,000個/μL、及び網赤血球数が60,000個/μL未満の2または3項目を満たすものをいいます。
原因は先天性と後天性に分けられます。遺伝子異常による先天性再生不良性貧血はFanconi貧血とよばれます。後天性再生不良性貧血の原因として、ウイルス、薬物(クロラムフェニコールなど)、鎮痛薬、抗炎症薬等や放射線等が挙げられています。血液検査では正球性正色素性貧血を呈す。血清鉄および血中エリスロポエチンは増加する。
治療方法は、輸血(白血球除去赤血球)、G-CSFを投与する。また、20歳以下の重症例では、骨髄移植が行われる。20~45歳では、免疫抑制療法、タンパク同化ホルモン療法などが選択されます。
原因は先天性と後天性に分けられます。遺伝子異常による先天性再生不良性貧血はFanconi貧血とよばれます。後天性再生不良性貧血の原因として、ウイルス、薬物(クロラムフェニコールなど)、鎮痛薬、抗炎症薬等や放射線等が挙げられています。血液検査では正球性正色素性貧血を呈す。血清鉄および血中エリスロポエチンは増加する。
治療方法は、輸血(白血球除去赤血球)、G-CSFを投与する。また、20歳以下の重症例では、骨髄移植が行われる。20~45歳では、免疫抑制療法、タンパク同化ホルモン療法などが選択されます。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境改善と健康『肝性脳症』
肝性脳症とは、肝機能が低下したときに起こる症状の1つです。 肝臓は、体内で発生した、もしくは腸管から吸収されたアンモニアや芳香族アミンなどの中毒性物質を解毒する役割を持っています。しかし、肝機能が低下すると、これらの物質が肝臓で解毒されずに中枢神経に到達してしまい、神経症状を引き起こします。
肝性脳症の症状は、意識障害、異常行動、羽ばたき振戦などです。意識障害は軽度なものから深昏睡に至るまで幅広く、異常行動としては、落ち着きがない、興奮する、攻撃的になるなどがあります。羽ばたき振戦は、両手を肩の高さまで上げて、左右に振る動作です。
肝性脳症は、肝不全状態に蛋白質過剰摂取、便秘などの誘因が加わることによって引き起こされます。肝不全状態とは、肝臓の機能が低下して、正常に機能しなくなった状態です。蛋白質過剰摂取とは、必要以上に蛋白質を摂取することです。便秘とは、排便が3日以上ない状態です。
Read More
 腸内環境に関する解説
腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康を守る!ミクロフローラの秘密
ミクロフローラとは?腸内細菌の役割
腸内環境は、健康に大きな影響を与えています。腸内には、さまざまな細菌が棲んでおり、それらが相互に影響し合って腸内環境を形成しています。この腸内細菌叢を腸内フローラといいます。
腸内フローラは、健康な状態では、善玉菌と悪玉菌のバランスが保たれています。しかし、ストレスや食生活の乱れなどによって、このバランスが崩れてしまうと、腸内環境が悪化し、さまざまな健康上の問題を引き起こすことがあります。
腸内細菌は、消化や栄養吸収、免疫機能など、さまざまな役割を担っています。善玉菌は、腸内を酸性に保ち、悪玉菌の増殖を抑える働きがあります。また、ビタミンやアミノ酸などの栄養素を合成する働きもあります。
悪玉菌は、腸内で有害な物質を産生したり、炎症を起こしたりするなど、さまざまな健康上の問題を引き起こすことがあります。しかし、悪玉菌の中には、消化や栄養吸収を助ける働きをするものもいます。
腸内環境を改善するためには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが大切です。善玉菌を増やすためには、食物繊維を多く含む食品や、発酵食品を積極的に摂ることがおすすめです。悪玉菌を減らすためには、ストレスを避け、睡眠を十分にとることが大切です。
Read More
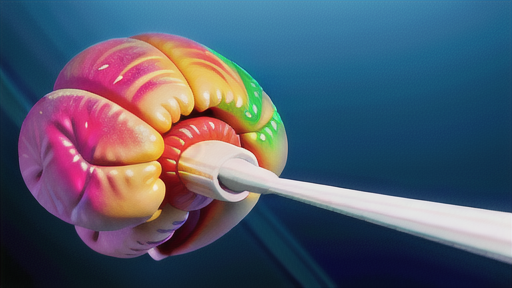 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康
腸内環境と健康の関係
腸内環境は、腸内に生息する微生物のバランスを指します。腸内環境が良好な状態にあると、腸内細菌が食物繊維を分解して酪酸などの短鎖脂肪酸を産生し、それにより腸の運動が促進され、有害物質が排出されやすくなります。また、短鎖脂肪酸は腸粘膜の健康を維持し、免疫機能を向上させる効果もあります。逆に、腸内環境が乱れていると、悪玉菌が増殖して腸内細菌のバランスが崩れ、有害物質が産生されやすくなります。これにより、腸粘膜の健康が損なわれ、免疫機能が低下して、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境を整えて健康に!フコシルラクトースのチカラ
フコシルラクトース(FL)は、フコースとラクトースが結合したオリゴ糖の一種です。ヒトの母乳に最も多く含まれるオリゴ糖であり、ヒトミルクオリゴ糖の代表的なオリゴ糖です。母乳には2種類のFL、2'-FLと3-FLが含まれており、乳腺細胞にあるフコシルトランスフェラーゼという酵素がそれらの合成に重要な役割を果たしています。
母乳に含まれるFLは、大腸まで到達し、ビフィズス菌の餌になります。乳児由来のビフィズス菌には、FLを菌体内に取り込んで増殖するための仕組みを持っている株が多く存在しています。
このような菌株の消化管内への定着は、乳児腸内の有機酸濃度の上昇とpHの低下をもたらし、腸内でのビフィズス菌の割合を増大させ、大腸菌などの割合を低下させることが報告されています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境と健康:乳酸菌とBCP加プレートカウント寒天培地
腸内環境と健康の関係
腸内環境は、私たちの健康に大きく影響しています。 腸内には、善玉菌と悪玉菌の2種類の細菌が生息しており、善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、さまざまな健康問題を引き起こすことがあります。
善玉菌は、腸内を酸性に保ち、悪玉菌の増殖を防ぐ働きがあります。また、善玉菌は、ビタミンやアミノ酸などの栄養素を生成し、腸の蠕動運動を促進する働きもあります。一方、悪玉菌は、腸内をアルカリ性に保ち、善玉菌の増殖を抑制する働きがあります。また、悪玉菌は、有害物質を生成し、腸の炎症を引き起こすことがあります。
腸内環境が悪化すると、便秘、下痢、腹痛などの消化器症状を引き起こすことがあります。また、腸内環境の悪化は、肥満、糖尿病、高血圧、動脈硬化などの生活習慣病の発症リスクを高めることもわかっています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 バイオジェニックスで腸内環境を整えて健康に!
バイオジェニックスとは、食品が本来有する、身体の正常な機能をサポートする成分のことを指します。
例えば、乳製品にはカルシウムが豊富に含まれていますが、カルシウムは骨を強くしたり、神経機能を正常に保つのに役立ちます。また、緑黄色野菜にはビタミンAやビタミンCが多く含まれていますが、ビタミンAは視力を維持したり、免疫機能を正常に保つのに役立ち、ビタミンCはコラーゲンの生成を促進したり、抗酸化作用があります。
このように、バイオジェニックスは、食品が本来有する身体に良い成分であり、健康維持に役立ちます。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『成長因子』
腸内環境改善と健康『成長因子(成長促進因子ともいう。細胞の分化・増殖を促進する物質の総称で、ポリペプチドまたはタンパク質である。細胞の分裂と発育を促す因子神経成長因子(NGF)、インスリン様成長因子I(IGF-I)、上皮成長因子(EGF)、線維芽細胞成長因子(FGF)など20種以上。免疫系の調節に重要な因子リンホカイン、サイトカインなど20種以上。血液幹細胞の増殖、分化を調節するコロニー刺激因子(CSF)など3グループに分けられる。)』
腸内環境と健康の関係
腸内環境は、腸に生息する細菌のバランスが整った状態を指します。腸内細菌は、100種類以上、100兆個以上存在しており、その働きは多岐にわたります。例えば、腸内細菌は、食べ物を分解して栄養素を吸収するのを助けたり、有害な物質を分解して解毒したりしています。また、腸内細菌は、免疫システムを活性化して、感染症から身を守る役割も果たしています。
腸内環境が乱れると、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。例えば、腸内細菌のバランスが崩れると、下痢や便秘などの消化器系のトラブルを起こしやすくなります。また、腸内細菌が産生する毒素が体内に吸収されると、発がん性物質となる可能性もあります。さらに、腸内細菌のバランスが崩れると、免疫システムが正常に働かなくなり、感染症にかかりやすくなることもあります。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康 ~ルシフェラーゼの役割とは?~
発光酵素の役割とは?
発光酵素は、発光バクテリアやホタルなどの生物発光において、発光物質が光を放つ化学反応を触媒する作用をもつ酵素です。発光酵素は、生物の体内で発光物質の化学構造を変化させ、光エネルギーを放出させます。この光エネルギーは、生物のコミュニケーション、獲物の誘引、捕食者の回避など、様々な目的で使用されます。
例えば、ホタルは、発光酵素を利用して、オスとメスが互いに引き合うようにコミュニケーションをとっています。また、深海魚の中には、発光酵素を利用して、獲物を誘き寄せるものもいます。さらに、一部の動物は、発光酵素を利用して、捕食者から身を守るために、体を発光させています。
最近では、発光酵素は、食品衛生の現場で洗浄確認試験として行われるATP検査の触媒としても利用されています。ATP検査は、食品の表面に付着している細菌やウイルスなどの微生物を検出するための検査方法です。ATP検査では、発光酵素が微生物のATPと反応して発光することで、微生物の存在を検出します。
Read More
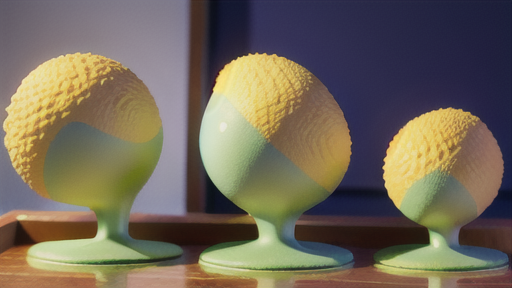 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 健康のための腸内環境改善『放線菌について』
放線菌とは、カビと細菌の中間に位置する微生物です。放線菌の定義は、16S rRNA遺伝子の塩基配列による分子系統学に基づいており、桿菌や球菌も放線菌に含まれるようになりました。放線菌は、一般的には空気中に気菌糸を伸ばして胞子を形成するため、肉眼的には糸状菌のように見えます。放線菌の大部分は絶対的好気性であり、土壌中に生育するものが多くあります。また、抗生物質生産菌の大部分が放線菌に属しており、特にストレプトマイセス属(Streptomyces、ストレプトマイシンの名の由来)に多く見られます。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 セロトニン→ 腸内環境改善と健康の鍵
セロトニンとは、5-ヒドロキシトリプタミン (5-HT) という構造をもつ生理活性アミンです。 アミノ酸のトリプトファンからトリプトファン5-モノオキシゲナーゼとL-アミノ酸デカルボキシラーゼの作用によって合成され、中枢神経系においてセロトニン作動性ニューロンの神経伝達物質として作用します。動物体に広く分布し、腸粘膜のクロム親和性細胞に最も多く含まれます。その他、血小板、視床下部、大脳辺縁系、松果体等にも含まれています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善とタイトジャンクション
タイトジャンクションとは、皮膚・胃・腸などの上皮組織を構成する上皮細胞や、血管内皮細胞に存在する細胞間接着装置のことです。 細胞膜貫通型タンパク質であるオクルディン(Occludin)およびクローディン(Claudin)、ならびに細胞内裏打ちタンパク質であるゾニューラ オクルディン(ZO Zonula occludens)などから構成されています。腸管の上皮細胞に局在するタイトジャンクションは、上皮細胞同士を機械的に繋ぐことでバリアを形成し、腸内細菌や病原菌、毒素といった外来異物の侵入を防ぐ重要な役割を担っています。このバリア機能の破綻は、感染症をはじめ、炎症性腸疾患や糖尿病など、さまざまな疾患の発症に寄与していると考えられています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境の改善と健康
腸内細菌は、私たち人間のカラダに良い影響と悪い影響をどちらも与える可能性があります。腸内細菌のバランスが乱れると、消化器系の不調や炎症性疾患を引き起こしたり、肥満や糖尿病などの生活習慣病のリスクが高まることが知られています。
一方、腸内細菌のバランスが整っていると、免疫機能が高まったり、肥満や糖尿病などの生活習慣病のリスクが低下したり、うつ病などの精神疾患のリスクが低くなることがわかっています。そのため、腸内環境を改善することが、健康維持に非常に重要であると考えられています。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境改善と健康『味蕾』の関係とは?
味蕾とは、味物質を受容する上皮由来の細胞の集合体です。約100個の細胞から成り、一部の細胞は味覚受容体を発現しています。ヒトの場合、舌の乳頭、口蓋、喉頭に約1万個が存在します。
味蕾はタマネギ状の形状をしており、表層部は味孔として外界と接しています。中間、基底部には味神経が連絡し、味覚情報を延髄へと伝達しています。味蕾は、食物中の味物質を感知し、その情報を脳に伝えて、味覚を認識する役割を果たしています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『グラム陽性とグラム陰性』
グラム陽性菌とグラム陰性菌の違い
グラム陽性菌とグラム陰性菌は、グラム染色による細菌の分類方法に基づく2つの主要なグループです。グラム陽性菌は、グラム染色法によって紫色に染まる細菌で、細胞壁に厚いペプチドグリカン層を持ちます。一方、グラム陰性菌は、グラム染色法によって赤またはピンク色に染まる細菌で、細胞壁にペプチドグリカン層と外膜を持っています。グラム陽性菌の例には、乳酸菌、ビフィズス菌、ブドウ球菌、連鎖球菌などが挙げられます。グラム陰性菌の例には、大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌、肺炎桿菌などが挙げられます。グラム陽性菌とグラム陰性菌は、細胞壁の構造や染色性の違いに加えて、代謝経路、抗生物質への感受性、病原性など、様々な点で異なります。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境改善とQ熱リケッチア予防
腸内環境の重要性
人間の腸内には、100兆個以上の細菌が生息しています。これらの細菌は、食物の消化や吸収、免疫機能の維持、有害物質の解毒など、さまざまな役割を果たしています。腸内環境が乱れると、これらの細菌のバランスが崩れ、健康に悪影響を及ぼすことがあります。
腸内環境を改善するには、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂ることが大切です。食物繊維は、善玉菌のエサとなり、腸内をきれいにしてくれます。また、発酵食品も善玉菌を増やすのに効果的です。ヨーグルト、納豆、味噌、漬物などは、積極的に摂りましょう。
ストレスを溜めないことも、腸内環境を改善するのに大切です。ストレスを感じると、腸内環境が悪化しやすいことがわかっています。規則正しい生活リズムを心がけ、適度な運動をしたり、趣味を楽しんだりして、ストレスを解消しましょう。
Read More
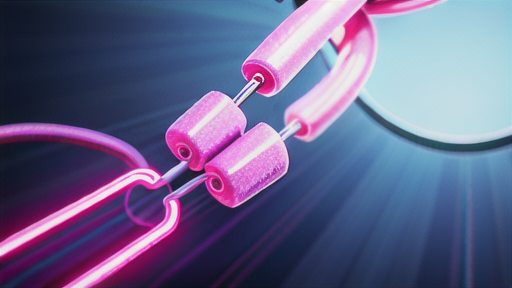 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康 ― 白血球の役割とは?
腸内環境改善と健康
白血球は、感染や外傷から身を守る重要な役割を果たしています。白血球は骨髄で作られ、血液を介して全身を巡っています。白血球には、好中球、好酸球、好塩基球、単球、リンパ球の5種類があります。
腸内環境と白血球の関係
腸内環境は、白血球の働きに影響を与えます。腸内環境が悪化すると、腸内細菌叢が乱れ、炎症が起こりやすくなります。炎症が起こると、白血球が活性化され、過剰に反応するようになります。過剰に反応した白血球は、自己の組織を攻撃する自己免疫疾患を引き起こすことがあります。
また、腸内環境が悪化すると、腸から有害物質が血液中に侵入しやすくなります。有害物質が血液中に侵入すると、白血球が過剰に反応して、アレルギーやアトピー性皮膚炎を引き起こすことがあります。
腸内環境を改善することで、白血球の働きを正常化し、感染症や自己免疫疾患、アレルギーなどを予防することができます。腸内環境を改善するには、食物繊維を多く含む食品を食べる、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌を多く含む食品を食べる、規則正しい生活を送る、ストレスを溜めない、などが挙げられます。
腸内環境を整えることで、免疫機能を高めて、感染症や様々な疾患に罹りにくい体を作ることができます。
Read More
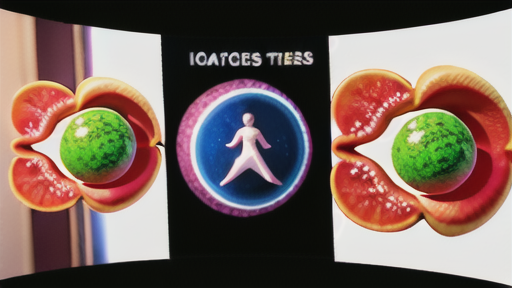 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康〜疫学研究からわかること〜
腸内フローラとは、腸内細菌叢とも呼ばれ、腸内に生息する微生物の総称です。腸内フローラは、健康に重要な役割を果たしており、食物の消化吸収、免疫機能の調節、病原菌からの防御などに関与しています。近年、腸内フローラのバランスが崩れると、肥満、糖尿病、動脈硬化、アトピー性皮膚炎、うつ病などのさまざまな疾患のリスクが高まることが報告されています。そのため、腸内環境を改善することは、健康維持に重要と考えられています。
Read More
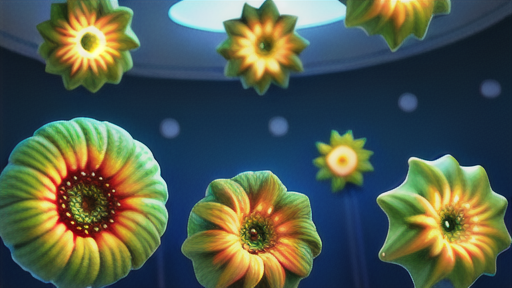 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で免疫力アップ!自然リンパ球と健康の関係
自然リンパ球(ナチュラルキラー(naturalkillerNK)細胞、リンパ様顆粒細胞(lymphoidgranulecellLGC)、グループ3先天性リンパ様細胞(group3innate lymphoid cellsILC3))は、リンパ球類似の形態をもち、Tリンパ球と同様のサイトカインを産生する、抗原受容体をもたない細胞として見出された。自然リンパ球は、リンパ球の一種であり、抗体産生や細胞傷害など、さまざまな免疫機能を担っている。自然リンパ球には、いくつかの種類があり、それぞれに異なる機能がある。例えば、ナチュラルキラー細胞は、ウイルスに感染した細胞やがん細胞を殺す働きがある。リンパ様顆粒細胞は、腸内細菌叢のバランスを維持する働きがある。グループ3先天性リンパ様細胞は、腸管粘膜の炎症を抑制する働きがある。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 サルモネラ属菌と腸内環境改善
サルモネラ属菌とは?
サルモネラ属菌とは、ヒトや動物に対して、チフス症や急性胃腸炎などを起こす多くの菌を含む属です。グラム陰性通性嫌気性桿菌で周鞭毛を有し運動性を持っています。生化学的性状によってⅠ~Ⅴの5亜属に分類され、さらにOおよびH抗原の組み合わせにより2,000以上の血清型に分けられます。サルモネラ属菌は、家畜や家禽、ペット、野生動物などの腸管に常在しており、糞便から環境中に排出されます。人は、汚染された食品や水を摂取することでサルモネラ菌に感染します。
Read More









