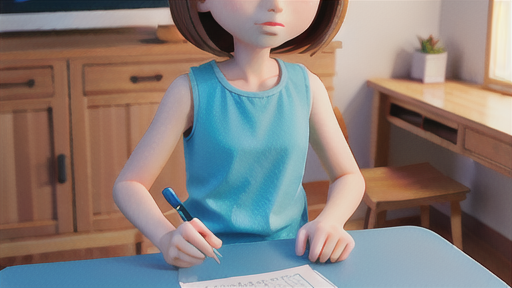 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 「シ」で始まる
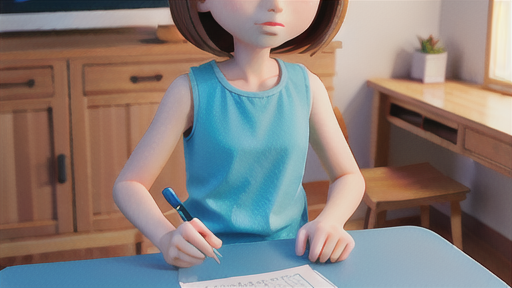 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説
腸内環境とは、腸の中に生息する細菌の種類やバランスのことを指します。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の細菌が住んでおり、これらがバランスを保ちながら共存することで、腸内環境が整い、健康が維持されます。善玉菌は、腸内を酸性に保ち、悪玉菌の増殖を防ぐ働きがあります。悪玉菌は、腸内をアルカリ性に保ち、善玉菌の増殖を防ぐ働きがあります。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらが優勢になるかによって、善玉菌側についたり、悪玉菌側についたりします。
腸内環境が乱れると、悪玉菌が増殖し、善玉菌が減少します。すると、腸内がアルカリ性に傾き、腸内環境が悪化します。腸内環境が悪化すると、下痢や便秘、腹痛などの消化器症状が現れるだけでなく、免疫力が低下したり、アレルギーを発症しやすくなったり、肥満や糖尿病などの生活習慣病のリスクが高まったりします。
Read More
 アレルギーに関する解説
アレルギーに関する解説 腸内環境改善と健康
食物アレルギーとは、ある特定の食品に対して身体が過剰に反応する状態をいいます。アレルギー症状としては、じんましん、湿疹、下痢、嘔吐などがあります。食物アレルギーの原因となる食品は、卵、牛乳、小麦、大豆など、比較的よく摂取する食品が多いです。食物アレルギーは、小児期に発症することが多く、成長とともに自然に治る場合もありますが、成人になっても症状が続くこともあります。食物アレルギーの治療は、アレルゲンとなる食品を摂取しないようにすることが基本です。そのため、食物アレルギーのある人は、食品の成分表示を注意深く確認する必要があります。また、食物アレルギーの症状を軽減するために、抗ヒスタミン薬やステロイド薬などが処方されることもあります。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康のために欠かせない「自由水」の重要性
腸内環境と自由水の関係
腸内環境は、私たちの健康に大きな影響を与えています。腸内には、善玉菌と悪玉菌がいて、そのバランスが健康を左右します。善玉菌は、私たちの体に良い働きをしてくれる細菌で、悪玉菌は、体に悪い働きをする細菌です。善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、さまざまな病気の原因となります。
自由水とは、食品中に含まれる水分で、微生物が生育しやすい水分のことです。自由水のコントロールによって、食品の保存性を高めることができます。自由水の量は、食品の水分活性を示す指標となります。水分活性とは、食品中の水の量と、その水の微生物が生育しやすい程度を示す指標です。水分活性が高ければ、微生物が生育しやすく、保存性が低くなります。逆に、水分活性は低ければ、微生物が生育しにくくなり、保存性が高くなります。
腸内環境を改善するためには、自由水の量をコントロールすることが重要です。自由水の量をコントロールすることで、腸内細菌のバランスを整えることができ、腸内環境を改善することができます。自由水の量をコントロールする方法としては、食品を乾燥させる、塩漬けにする、砂糖漬けにする、冷凍するなどがあります。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 脂肪と腸内環境改善と健康
腸内環境と脂肪の関係性では、腸内環境と脂肪の関係について説明します。脂肪は、エネルギー源として体内に蓄えられる栄養素の一種で、常温で固体のものを脂肪、常温で液体であるものは油と呼びます。脂肪は、体内に入ると、小腸で分解されて吸収されます。吸収された脂肪は、体内に蓄えられたり、エネルギーとして使用されたりします。
腸内環境のバランスが乱れると、脂肪の吸収が促進されることがわかっています。これは、腸内細菌が脂肪を分解する酵素を産生するためです。腸内細菌のバランスが悪くなると、脂肪を分解する酵素を産生する細菌が増加し、脂肪の吸収が促進されてしまいます。
また、腸内環境のバランスが乱れると、脂肪を燃焼する能力が低下することがわかっています。これは、腸内細菌が脂肪を燃焼する酵素を産生するからです。腸内細菌のバランスが悪くなると、脂肪を燃焼する酵素を産生する細菌が減少してしまい、脂肪を燃焼する能力が低下してしまいます。
腸内環境のバランスを整えることで、脂肪の吸収を抑制し、脂肪を燃焼する能力を高めることができます。これにより、肥満を予防したり、改善したりすることができます。また、腸内環境のバランスを整えることで、腸の働きもよくなり、便秘や下痢などの症状を改善することもできます。
Read More
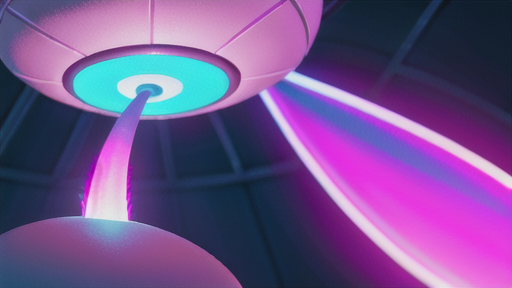 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康を支える紫外線
紫外線による腸内環境改善効果とは、紫外線によって腸内の細菌叢を変化させ、腸内環境を改善することです。紫外線は、殺菌作用があるため、腸内の有害な細菌を死滅させることができます。また、紫外線は、腸内環境を改善する善玉菌を増やす効果もあるとされています。
腸内環境が改善されると、さまざまな健康上の効果が期待できます。例えば、腸内環境が改善されると、便秘や下痢などの腸のトラブルが改善されることがあります。また、紫外線は、免疫力を高める効果もあるため、紫外線による腸内環境改善効果は、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりにくくなることにつながると期待できます。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 初乳で腸内環境を改善し、健康に!
初乳とは、分娩後4~5日間分泌される母乳であり、10日後から分泌される成乳に比べ、高タンパク質、低脂肪、低ラクトースである。脂肪球を多く含む白血球が存在し、これを初乳球という。初乳は、感染防御機能を有するIgAやラクトフェリンを多量に含んでおり、新生児の感染防御に重要な役割を演じる。IgAは食物アレルゲンの吸収を抑制するので、アレルギーの予防にも有効であると考えられている。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『除菌(微生物の死滅は伴わずに、食品にもともと汚染している微生物を、洗浄、ろ過、遠心分離などにより食品や製造環境から取り除き、ヒトの健康を損なわないレベルにまで低下させること。)』について
除菌とは、食品にもともと汚染している微生物を、洗浄、ろ過、遠心分離などにより食品や製造環境から取り除き、ヒトの健康を損なわないレベルにまで低下させることです。除菌は、食品の安全性を確保するために重要な工程であり、食品の製造・販売においては、除菌のための設備や手順が定められています。
除菌には、物理的除菌と化学的除菌の2種類があります。物理的除菌は、熱処理や紫外線照射などにより微生物を死滅させる方法であり、化学的除菌は、塩素や過酸化水素などの化学物質を使用する方法です。
除菌は、食品の安全性を確保するためには必要な工程ですが、除菌によってすべての微生物が死滅するわけではありません。そのため、除菌後の食品も、適切に保存して早めに消費することが重要です。また、除菌によって微生物が死滅することで、食品の味や食感が変化することがあります。
Read More
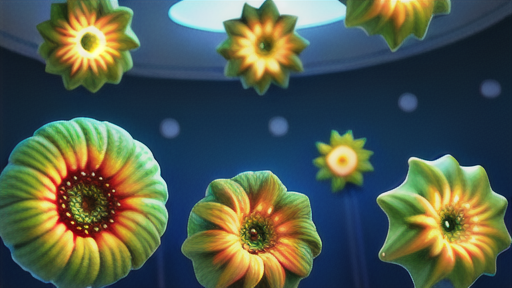 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で免疫力アップ!自然リンパ球と健康の関係
自然リンパ球(ナチュラルキラー(naturalkillerNK)細胞、リンパ様顆粒細胞(lymphoidgranulecellLGC)、グループ3先天性リンパ様細胞(group3innate lymphoid cellsILC3))は、リンパ球類似の形態をもち、Tリンパ球と同様のサイトカインを産生する、抗原受容体をもたない細胞として見出された。自然リンパ球は、リンパ球の一種であり、抗体産生や細胞傷害など、さまざまな免疫機能を担っている。自然リンパ球には、いくつかの種類があり、それぞれに異なる機能がある。例えば、ナチュラルキラー細胞は、ウイルスに感染した細胞やがん細胞を殺す働きがある。リンパ様顆粒細胞は、腸内細菌叢のバランスを維持する働きがある。グループ3先天性リンパ様細胞は、腸管粘膜の炎症を抑制する働きがある。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康
腸内環境とは、人間の消化管内に存在する細菌叢を指します。腸内には、100種類以上、100兆個もの細菌が生息しており、それらは善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3つに分類されます。善玉菌は、食物繊維を分解して短鎖脂肪酸を生成し、腸の蠕動を促進するなど、人間の健康に有益な働きをします。悪玉菌は、有害物質を産生したり、腸の粘膜を傷つけたりするなど、人間の健康に有害な働きをします。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらの働きもする細菌です。
腸内環境は、食事、ストレス、睡眠、運動など、さまざまな要因によって影響を受けます。不規則な生活、偏った食生活、ストレスなどは、腸内環境を悪化させ、健康に悪影響を及ぼすことがわかっています。反対に、規則正しい生活、バランスの良い食生活、適度な運動などは、腸内環境を改善し、健康を維持するのに役立ちます。
Read More
 その他
その他 腸内環境改善と健康『真空包装』
真空包装とは?
真空包装とは、食品やその他の製品を真空状態で密封した包装のことです。真空包装は、一般に好気性細菌やカビは酸素がないと増殖できないという性質を利用して、これらの微生物の増殖を抑える効果があります。真空包装は、食品の鮮度を保持したり、雑菌の繁殖を防いだりするために広く利用されています。真空包装は、食品の鮮度を保持したり、雑菌の繁殖を防いだりするために広く利用されています。真空包装は、食品やその他の製品を保存するための重要な技術であり、多くの分野で活用されています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康~食品衛生法から学ぶ食の安全と健康維持~
健康維持において腸内環境は、重要な役割を果たしており、近年では、腸内環境改善と健康の関係が注目されています。特に、食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ることを目的とした法律です。この法律に基づき、食品の安全性を確保するための規制や措置が講じられています。
健康な腸内環境を保つためには、腸内環境を改善する効果のある食品やサプリメントを摂取することが重要です。腸内環境を整える食品やサプリメントの例としては、乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクス、食物繊維が含まれる食品やサプリメントなどがあります。また、規則正しい食生活や十分な睡眠、適度な運動など、生活習慣にも注意が必要です。
腸内環境が改善されると、免疫機能が強化されたり、代謝が活性化されたり、メンタルヘルスが改善されたりなど、様々な健康上のメリットが得られることが期待できます。腸内環境を改善することは、健康維持のためにも重要なポイントであり、意識的に腸内環境を改善するような生活習慣や食事を心掛けることが大切です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 次亜塩素酸で腸内環境改善!健康効果と摂取方法
次亜塩素酸とは?化学式や特徴を解説!
次亜塩素酸は、化学式HOClで表される化合物です。次亜塩素酸ナトリウムや高度サラシ粉の殺菌作用や漂白作用の主体であり、水溶液は次亜塩素酸水と呼ばれています。次亜塩素酸は、常温常圧で不安定な物質であり、光や熱に弱い性質を持っています。その一方で、次亜塩素酸は強力な殺菌作用と漂白作用を有しており、さまざまな用途に使用されています。
次亜塩素酸の殺菌作用は、細菌やウイルスの細胞壁を破壊することによるものです。次亜塩素酸は、細菌やウイルスの細胞壁に含まれるタンパク質や脂質を酸化させ、細胞壁を破壊します。これにより、細菌やウイルスは死滅します。また、次亜塩素酸は、細菌やウイルスの細胞内のDNAやRNAを損傷させることで、細菌やウイルスの増殖を阻害する働きも持っています。
次亜塩素酸の漂白作用は、色素を酸化することで発揮されます。次亜塩素酸は、色素を酸化させ、無色の物質に変換します。これにより、色素が分解され、漂白効果が得られます。次亜塩素酸は、紙や布の漂白や、水泳プールの水の消毒などに使用されています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『心拍出量』について
腸内環境と心拍出量の関係
腸内環境と心拍出量の関連性を示唆する研究があります。腸内細菌叢の構成は、心拍出量や他の心臓機能の指標に影響を与える可能性があります。例えば、ある研究では、腸内細菌叢の多様性が高いほど、心拍出量が高いことがわかりました。これは、腸内細菌叢の多様性が心臓の健康に有益な影響を与える可能性があることを示唆しています。しかし、腸内環境と心拍出量の関係性はまだ十分に解明されておらず、さらなる研究が必要です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『実体顕微鏡』とは?
腸内環境改善と健康『実体顕微鏡』(比較的低倍率(2-30倍程度)で、観察対象を薄切標本などにせず、そのままの状態で観察するための顕微鏡である。)
腸内環境改善の重要性
腸内環境は、腸内細菌のバランスによって決まります。腸内細菌は、人間の健康に重要な役割を果たしており、免疫機能の維持、消化・吸収、栄養素の合成、有害物質の分解など、さまざまな働きをしています。腸内環境が乱れると、これらの働きが低下し、さまざまな健康問題を引き起こすことがあります。
腸内環境が悪化すると、下痢や便秘、腹痛などの消化器症状だけでなく、アトピー性皮膚炎や花粉症などのアレルギー疾患、肥満や糖尿病などの生活習慣病、さらにはうつ病などの精神疾患にも影響を及ぼすことがわかっています。
そのため、腸内環境を改善することは、健康維持のために非常に重要です。腸内環境を改善するには、食生活や生活習慣を見直すことが基本となります。野菜や果物、発酵食品などを積極的に摂取し、規則正しい食生活を心がけましょう。また、適度な運動や十分な睡眠も腸内環境の改善に効果的です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で自然免疫力を高める
腸内環境と自然免疫の関係
腸内環境は、自然免疫に大きな影響を与えています。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の細菌が住んでいます。善玉菌は、腸内の有害物質を分解したり、免疫細胞を活性化したりする働きがあります。悪玉菌は、腸内に有害物質を産生したり、腸の粘膜を破壊したりする働きがあります。日和見菌は、善玉菌や悪玉菌の優勢によって、善玉菌側にも悪玉菌側にも付く細菌です。善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、自然免疫が低下してしまいます。逆に、善玉菌が優勢な腸内環境は、自然免疫を強化し、病気にかかりにくい体を作ります。
腸内環境と自然免疫の関係については、多くの研究が行われており、腸内環境が自然免疫に大きな影響を与えていることがわかっています。例えば、ある研究では、善玉菌の一種であるビフィズス菌を摂取することで、自然免疫細胞であるNK細胞の活性が向上したことが報告されています。また、別の研究では、悪玉菌の一種である大腸菌を摂取することで、自然免疫細胞であるマクロファージの活性が低下したことが報告されています。これらの研究結果は、腸内環境が自然免疫に大きな影響を与えていることを示唆しています。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『試料原液』について
腸内環境と健康の関係
腸内環境は、近年、健康に大きな影響を与えることが明らかになっています。腸内には、善玉菌と悪玉菌の2種類の細菌が住んでおり、このバランスが崩れると、健康に悪影響を及ぼすことがあります。善玉菌は、体に良い物質を産生し、悪玉菌の増殖を抑える働きがあります。一方、悪玉菌は、体に悪い物質を産生し、腸内環境を悪化させる働きがあります。腸内環境を改善するためには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが重要です。
腸内環境を改善するためにできることはたくさんあります。まず、食物繊維を多く摂ることです。食物繊維は、腸内で善玉菌のエサとなり、善玉菌を増やすのに役立ちます。また、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌を多く含む食品を摂ることも効果的です。さらに、ストレスを避けることも重要です。ストレスは、腸内環境を悪化させることがわかっています。そのため、適度な運動や睡眠を心がけ、ストレスをためないようにすることが大切です。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『シャーレ』
腸内環境とは、腸内に住む細菌やウイルス、真菌などの微生物のバランスのことです。腸内環境は、健康に大きな影響を与えており、腸内環境が乱れると、さまざまな健康上の問題が起こる可能性があります。
腸内環境が乱れる原因としては、食生活の乱れ、ストレス、睡眠不足、薬の服用などがあります。また、加齢によっても腸内環境は乱れる傾向があります。
腸内環境が乱れると、下痢、便秘、腹痛、ガスがたまるなどの症状が現れることがあります。また、肌荒れ、肥満、糖尿病、動脈硬化、うつ病など、さまざまな健康上の問題のリスクが高まる可能性があります。
腸内環境を改善するには、食生活を見直し、食物繊維を多く摂り、発酵食品を積極的に食べることが大切です。また、ストレスをためないようにし、睡眠を十分にとることも重要です。
Read More
 検査に関する解説
検査に関する解説 健康のための腸内環境改善と新体力テスト
腸内環境改善と健康『新体力テスト(→体力診断テスト)』
腸内環境と健康の密接な関係
腸内環境は、私たちの健康に大きな影響を与えています。腸内環境を改善することで、肥満、糖尿病、心臓病、がん、うつ病などのさまざまな病気の予防や改善につながる可能性が示されています。
腸内には、100兆個以上の細菌が生息しています。これらの細菌は、私たちの体に必要な栄養素を作り出したり、有害な物質を分解したり、免疫力を高めたりするなど、さまざまな働きをしています。腸内環境が乱れると、これらの細菌のバランスが崩れ、病気のリスクが高まると考えられています。
腸内環境を乱す要因としては、偏った食事、ストレス、睡眠不足、運動不足、喫煙、飲酒などがあります。腸内環境を改善するためには、これらの要因を改善することが大切です。
腸内環境を改善するのに役立つ食品としては、食物繊維を多く含む食品、発酵食品、プロバイオティクス食品などがあります。食物繊維は、腸内細菌のエサとなり、腸内環境を改善する働きがあります。発酵食品には、腸内細菌に良い影響を与える乳酸菌やビフィズス菌などが含まれています。プロバイオティクス食品には、腸内細菌に良い影響を与える生きた菌が含まれています。
また、ストレスを軽減したり、睡眠を十分にとったり、適度な運動をしたりすることも腸内環境の改善に役立ちます。
Read More
 アレルギーに関する解説
アレルギーに関する解説 腸内環境を整えるための食物アレルギー対策法
食物アレルギーとは、特定の食物を摂取することで、免疫系が過剰に反応してアレルギー症状を引き起こす疾患です。原因となる食物は、小麦や卵、牛乳、エビ、カニ、果物など様々です。
食物アレルギーは、乳児や小児に多く見られますが、大人でも発症する可能性があります。症状は、じんましんや湿疹などの皮膚症状、下痢や嘔吐などの消化器症状、咳や喘息などの呼吸器症状など、様々です。
重度の食物アレルギーの場合、アナフィラキシーショックを起こすことがあります。アナフィラキシーショックは、血圧低下や意識障害などを伴う、生命にかかわる緊急事態です。
食物アレルギーの治療法は、原因となる食物を避けることです。また、アレルギー症状を緩和するために、抗ヒスタミン薬やステロイド薬などの薬が処方されることもあります。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『集落数』の重要性
腸内環境改善と健康「集落数」
腸内環境の重要性
腸内環境とは、腸内に生息する腸内細菌のバランスのことを指します。腸内細菌は、善玉菌、日和見菌、悪玉菌の3種類に分けられます。善玉菌は、乳酸や酢酸などの有機酸を産生して腸内を酸性に保ち、悪玉菌の増殖を抑えています。また、免疫力を高めて感染症を予防する役割も担っています。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらが増えるかによって、どちらの味方につくかを決めます。悪玉菌は、有害物質を産生して腸内を汚染し、腸炎や大腸炎などの病気の原因となります。
腸内環境が悪化すると、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。例えば、便秘や下痢、腹痛、ガス溜まりなどの消化器系の症状が出やすくなります。また、肌荒れ、ニキビ、アトピー性皮膚炎などの皮膚系のトラブルが起こることもあります。さらに、うつ病、不安障害などの精神的な症状が現れることもあります。
近年、腸内環境と健康の関係が注目されており、腸内環境を整えることで、様々な健康問題を予防・改善できると言われています。腸内環境を整えるためには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが大切です。善玉菌を増やすには、発酵食品を積極的に摂ったり、食物繊維が豊富な食品を摂ったりすることが有効です。また、悪玉菌を減らすには、肉類や脂っこい食品、加工食品などの摂り過ぎを控えたり、ストレスをためないようにすることが大切です。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境を整えて健康的な生活を
腸内環境と健康の関係
腸内環境は、私たちの健康に大きく影響を与えると言われています。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の細菌が生息しており、これらのバランスが健康を維持する上で重要です。善玉菌は、腸内環境を整え、悪玉菌の増殖を抑える働きがあります。悪玉菌は、有害物質を産生し、腸内環境を悪化させます。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらの勢力が強い方に味方する細菌です。
腸内環境が悪化すると、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。例えば、肥満、糖尿病、高血圧、動脈硬化、がん、うつ病などです。また、腸内環境の悪化は、免疫力の低下にもつながり、感染症にかかりやすくなります。
腸内環境を改善するには、善玉菌を増やすことが大切です。善玉菌を増やすには、食物繊維を多く摂ったり、発酵食品を摂ったりすることが有効です。また、ストレスを溜めないようにすることも大切です。ストレスがかかると、悪玉菌が増えやすくなり、腸内環境が悪化します。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境を整えて健康になる!人工乳の働きとは
人工乳と腸内環境の関係
人工乳は、母乳の成分に類似させて作られた乳幼児向けの食品です。乳児用調製粉乳、離乳食期用フォローアップミルク、各種疾患対応の治療用特殊粉乳など、さまざまな種類があります。人工乳は、母乳で育てられない場合や、母乳が不足している場合に使用されます。
人工乳は、母乳に比べて腸内環境に与える影響が異なることがわかっています。母乳には、乳幼児の腸内環境を整えるのに役立つさまざまな成分が含まれています。例えば、母乳には、ビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌が多く含まれています。善玉菌は、腸内環境を酸性に保ち、悪玉菌の増殖を抑える働きがあります。また、母乳には、オリゴ糖や乳糖などのプレバイオティクスが含まれています。プレバイオティクスは、善玉菌のエサとなり、善玉菌の増殖を促進する働きがあります。
人工乳には、母乳に含まれる善玉菌やプレバイオティクスが少なめです。そのため、人工乳で育てられた乳幼児は、母乳で育てられた乳幼児よりも腸内環境が悪化しやすい傾向にあります。腸内環境が悪化すると、下痢や便秘などの消化器系のトラブルを起こしやすくなります。また、腸内環境が悪化すると、免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなることもあります。
人工乳で育てられた乳幼児の腸内環境を改善するためには、人工乳にプレバイオティクスやプロバイオティクスを添加することが有効です。プレバイオティクスは、善玉菌のエサとなる成分であり、プロバイオティクスは、善玉菌そのものです。人工乳にプレバイオティクスやプロバイオティクスを添加することで、人工乳で育てられた乳幼児の腸内環境を改善することができ、消化器系のトラブルや感染症の発症リスクを軽減することができると考えられています。
Read More
 健康アップに関する解説
健康アップに関する解説 腸内環境を整えてシガテラ毒から身を守る
シガテラ毒とは
シガテラ毒とは、主に熱帯に生息するプランクトンが作り出す毒素によって汚染された魚介類を喫食したときに発生する食中毒です。シガテラ毒としては、シガトキシン、スカリトキシン、マイトトキシン、シガテリンなどが知られています。シガトキシンは熱に強く、汚染された魚介類を加熱しても、食中毒が発生します。シガテラ毒は、魚介類の体内に蓄積され、食物連鎖によって上位の魚介類にも移行します。そのため、大型の魚介類ほどシガテラ毒に汚染されている可能性が高くなります。
Read More
 腸内環境改善に関する解説
腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と食事
主食とは、食事の中で中心となる食べ物であり、穀類が中心となります。日本では、主食(ごはん)と副食(おかず)という食生活を続けてきました。大正末期から昭和初期には、白米、麦、稗(ひえ)、粟(あわ)などの雑穀類を主食としていましたが、第二次世界大戦中の食糧難時代には、米の節約のためにほかの食品を混ぜた主食を工夫し、穀類、いも類、豆類、野菜類などを食素材とした混ぜ飯、かて飯などを食べました。戦争末期には、茶がら、豆かすも増量材として加えられ、雑炊、粥、すいとんだけでなく、米以外の食品を主食とする麺類、蒸しパン、団子、餅などの代用主食も食べられました。人々が日常食として白飯を食べるようになったのは、終戦後しばらくたった昭和20年代後半からです。日本では、近代になって他国にない主食中心型、和洋中混合型、折衷型の食事文化を短期間に築いてきましたが、今日では、若年層では主食を減らしておかず(副食)を食べる風潮がみられるようになっています。
Read More









